
2024/11/11
――それでは、主要な改訂ポイントについてご解説をいただけましたら。
神田 第一に、サステナビリティに関する新しい章を設けたことです。企業統治においてリスクと機会への対応が重要性を増す中、企業が多様なステークホルダーの利益を考慮しながら持続的成長を実現するための企業統治の枠組みに関しては、これまで原則の各章に断片ずつ分散して表記していたものを、サステナビリティというテーマを基準に独自の章を一つ設けました。株主の権利や取締役会の情報開示等とサステナビリティには、同等の重みが有ることを示したわけです。各章でサステナビリティにかかる議論が難航していたところ、発想の転換で、サステナビリティ関係を横串でまとめて解決しようという戦略を取ったところもあります。
――サステナビリティの新章では、具体的にどのような内容を記載したのでしょうか。
神田 大きく四つのポイントがあります。まず取締役会の責務として、気候変動リスクが自社の事業活動にもたらす影響と機会を適切に考慮しなければならない。次に、サステナビリティ関連の開示については、合理的な投資家が投資判断にあたって重要と考える情報を開示して、一貫性、比較可能性、診断性を確保しつつ、サステナビリティ関連の開示には独立した第三者による保証の導入を段階的に検討しなければならない。三つ目は、コーポレートガバナンスが企業の事業戦略に関連する範囲で企業・投資家・ステークホルダーがサステナビリティについて会話することを許容すべきである。最後が、多様なステークホルダーの権利を許容すべきである、等々です。
――今回の改訂ではさらに、スチュワードシップ・コード(コーポレートガバナンスの向上に向けた機関投資家の行動規範)の導入も明記されたとか。日本では数年前からいち早くスチュワードシップ・コードを取り入れていましたが。
神田 はい、世界の中でも日本は早期にスチュワードシップ・コードを導入した国の一つです。が、前述のように機関投資家の役割がかつてと比べて桁違いに巨大化し、上場企業の最大株主が機関投資家という状況です。かつ、多くの機関投資家はインデックス型投資(特定の株価指数と連動する値動きを目指す手法)を行うためエンゲージメントを行うインセンティブがはたらきません。従って今回、機関投資家にも投資先へのエンゲージメントを促進させるべきという観点の下、ツールとしてスチュワードシップ・コードが例示されました。ただ、スチュワードシップ・コードは多様な投資を前提としており、順守するかどうかは任意であるため、エンゲージメントの在り方を機関投資家自身が選択できる柔軟性はあるものの、実効性の確保という点では心もとないところです。
この点、一部の国ではスチュワードシップ・コードにかかる活動のベストプラクティスを公表していることから、この取り組みについて今回の改訂では初めて例示するなど、いろいろなベストプラクティスを取り入れながら改善を図りました。
日本企業はより積極的に活用を
―――他の留意すべき点などについてはいかがでしょうか。
神田 いくつか細かいポイントがありますが、ピックアップすると以下の三点というところでしょう。
まず、アジアの新興国を主たる対象に、カンパニーグループをどう扱うかという論点。これらの国々では往々にして会社を含む法人が支配的株主になるケースが多く、ことに事業活動が拡大したり国際化したりするにつれてカンパニーグループの構造が複雑化、複層化の一途をたどります。従って関連当事者による取引に対し、どうモニターするのか、資本関係をどう透明化するのか、カンパニーグループにおける適切なリスク管理はどうあるべきか等々の課題が指摘されていました。そこで今回の改訂では、グループのいわば上流に位置する上場企業の取引について情報共有を確保するよう明記しました。併せてブロック構造の透明性、関連当事者取引の強化も示し、利益相反などが起こらないよう抑止をかけています。
二つ目は、改訂した背景の一つであるデジタル化への対応です。コロナ禍で急増したリモート株主総会について、われわれとしても基本はこれを許容しつつ、質問の行使権をはじめエンゲージメントを損なわないような配慮を求めたことに加え、サイバーセキュリティを取締役会の責任として対処すべき重要なリスクであると位置付けました。
最後が、取締役会の機能強化です。現在の取締役会は数々の環境変化に相次いで対応していかねばならず、取締役会にも機能・メンバーともに一層の強化、多様性が要求されます。それ故、改訂においては、取締役会レベルの専門委員会に新たに監査委員会もしくは同等の機能を有する委員会の設置を、またメンバー構成においてはジェンダーだけでなく能力や経歴などをバランスよく評価することを強く求めました。
――数々の大胆な改訂を完遂されたわけですが、内容に対する反応は概してどのようなものでしょう。
神田 各国で言えば法律を通したようなものですから、あとは皆が粛々と内容に従うのみではあるのですが、それでも非常にポジティブな受け止め方が太宗を占めている、と捉えてよいと思います。特に、これから資本市場を発展させていこうとするグローバルサウスといわれる新興国などから極めて好意的に受け止められています。日本のコーポレートガバナンスはこのOECDコーポレートガバナンス・プリンシプルをフォローする形でスタートしたように、多くの国は今回の改訂プリンシプルをそのまま会社法に導入したりしています。ビジネス界からは事業法人だけでなく、金融機関からも多くの賛意が寄せられたほか、海外の大手メディアも頻繁に内容を取り上げてくれるなど、大きな反響がありました。
――日本の産業界からも同様に?
神田 あいにく、日本では各国に比べるとやや反応が薄く感じられるので、企業各社も改訂内容について、もっと積極的に活用してもらえればと思いま
す。魅力ある企業となるには持続的成長、中長期的な企業価値の向上が不可欠であり、そのためにも良好な企業統治がこれまで以上に重要となっています。形式的な体制整備にとどまることなく、企業と投資家の双方において自律的な意識改革を図り、コーポレートガバナンスを実質化していくことが求められます。企業においては構成員のモチベーションが上がり、ステークホルダーから評価してもらえるようになるなど、具体的な変化に結び付けることが大切なのです。
ことに世界で地政学的リスクや不確実性が高まっている現在、アジアにおいて堅実な自由主義、民主主義、市場経済を堅持する日本と日本企業に対し、海外投資家の期待はむしろ高まりを見せています。であればこそ、この機に企業統治のありようを見直し整備すれば、海外投資家はもっと関心を寄せるのではないでしょうか。今はむしろその好機、好環境にあると思われます。
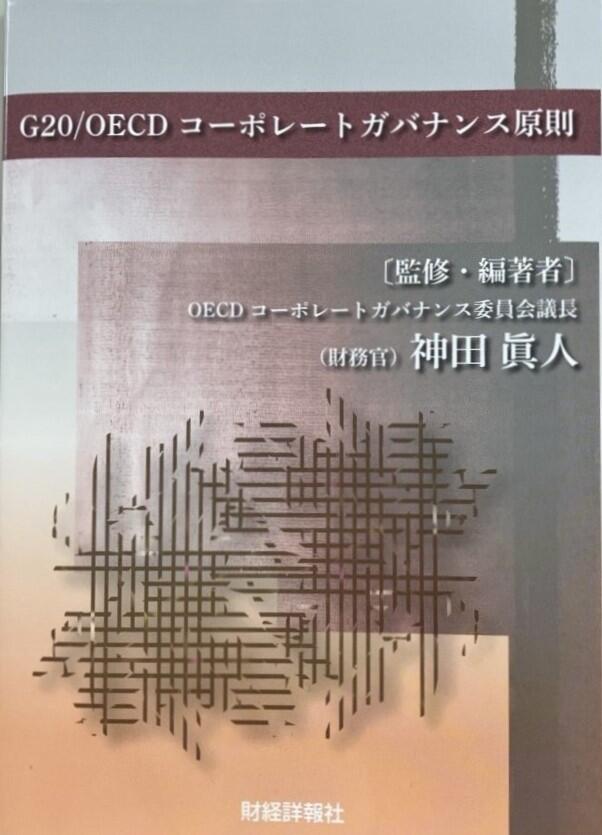
――そして神田参与は本年6月、今回の改訂の要旨を取りまとめ、監修・編著者として『G20/OECDコーポレートがバンナンス原則』を上梓されました。この著作に関して参与の思いをうかがえましたら。
神田 とにかく改訂を発起してから実施までの作業期間が長く、ようやく取りまとめに至りました。しかも改訂に向けてファクトが無いと作業を行うにも説得力がありませんから、その過程で精緻な現状分析と論点整理、解決策の提示について膨大な量のリサーチを行いました。同作業に連動して2021年6月から8本のディスカッション・ペーパーを作成し、これらは全て公表しています。
資本市場の構造変化の中でコーポレートガバナンスが果たすべき役割の変化を分析し、おそらく数千人規模の関係者が議論に参加してきました。その他、50カ国の主要な規制枠組みを一覧にまとめた「OECDコーポレートガバナンス・ファクトブック」を21年5月に公表するなどの成果が、今回の改訂のバックグラウンドに取り入れられており、各国各社の実務に基づく地に足の着いた議論の基盤を構成することができました。こうした質実な議論の土台を提供できたことは画期的だと思います。
神田 もう一つ、今回合意した各国の中には、必ずしも民主主義国家だけではなく、他の政治体制の国々も含まれています。世界の分断が進み、グローバルな合意が全般的に難しくなりつつある中で、相克しがちなテーマを包括しながら世界のコンセンサスを得られたということは大変大きな成果だと考えています。質の高い議論の場を醸成した委員会のメンバー、事務局のスタッフに改めて心から感謝いたします。今回の大きな改訂により、これであと10年ほどは見直しの作業を行わなくても済むでしょう。現状への対応だけでなく、未来に起こり得る事態を想起した内容となっていますので。
――それほどの意義を有し労力を投じた結集ながら、本書は本文100ページというコンパクトな構成です。ご指摘いただいたプロセスも含めて、もっと大著であっても良いかと思われますが。
神田 確かにバックグラウンドとなるデータや資料はそれこそ数千ページに及ぶものの、まさに憲法と同じで、誰もが手を取り要点を読解できる内容にし
たいと思いました。本書の体裁は、可能な限りそぎ落として要点を徹底的に抽出した結果なのです。
ただ現在、法律で言えば政令、省令にあたるようなメソドロジー(実施方法論)を作成しているところです。これは個々の原則について具体的にどのような事例があるのか等、より詳細に改訂のポイントを記載した解説書となります。おそらく年末までには完成するでしょう。
――今度は、その発刊が待たれるところですね。本日はありがとうございました。
(月刊『時評』2024年10月号掲載)