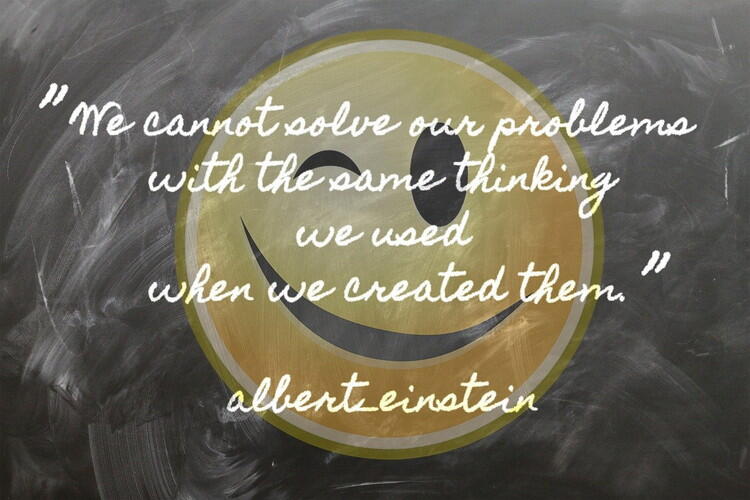
2025/03/03

今年は、日本共産党史上最大の汚点である〝コミンフォルム批判〟から丸70年という節目の年だが、党大会でほとんど言及されなかったことに甚だ違和感を覚える。当時の事件さえなかったかのように基本政策の変更も打ち出すならば、この辺りで〝りべらる党〟にでも党名を変更するべきではないか。
党大会の、三つの焦点
日本共産党が、1月中旬に会期5日の第28回党大会を開いた。
今回の大会の焦点は、三つあるとされていた。90歳に達した不破哲三〝院政体制〟の幕を引き、名実ともに志位和夫主導体制に切り替えられるか。低迷を続け、高齢化が進む党の現状を、どういう目標のもとで再建・活性化していくか。そして、来年秋までには行われる次期総選挙に向けた、野党共闘態勢の構築と、共産党独自の躍進を、どう両立させるか。この三点だ。
これらについて、大会は一応の答えを出した。第一点では、超高齢の不破がなおも中央委員に名を留め、志位時代の完全到来いまだし、の印象を残した。第二点では、党員はピークの50余万人からほぼ半減、機関紙は本誌・日曜版あわせてピークの300万部が3分の1に減った現状から、それぞれ3割増を目指す、控え目というか、現実的な目標に止めた。
問題は第三点で、小選挙区では立憲民主党や社民党などの左翼野党や、だれがどう見ても骨の髄からの保守政治家・小沢一郎が〝仮の棲み家〟とする国民民主党、さらに党大会に来賓として出席した中村喜四郎を筆頭とする保守系無所属、前回の参院選に突如参戦して限定的ながらブームを起こした山本太郎一統まで、大結集するよう呼び掛け、共産党自身も予定候補者の一部を降ろして、野党を打って一丸とした候補者調整を実現。自民・公明側と一騎打ちに持ち込んで競り勝ち、100議席の確保を目指す。一方、前回の総選挙でも前回の参院選でも、500万票にも届かなかった比例代表の共産党の得票を850万に伸ばし、大幅の議席増を図る。それらによって総選挙に勝ち、自民・公明連立政権を打倒して自らも政権に参加する。こういう野心的とも気宇壮大とも荒唐無稽ともいえる目標を掲げた。さらに、そのためには多年金科玉条としてきた基本政策の変更も辞さないとして、16年ぶりに党綱領も一部改定した。
コミンフォルム批判で分裂
それはそれで、議論すべき点や評価の対象にすべき部分もあるだろう。しかし、2020年に開く党大会である以上、もう一つ、というよりもなにごとにも先んじて、日本共産党の党史を総括するうえで、触れなければならない大きな問題点があるはずではないか、という思いが筆者にはある。それに触れる前に、短い文章を紹介したい。
「日本共産党よ 死者の数を調査せよ
そして共同墓地に手厚く葬れ
革命はそれからでいい」。
昭和30=1955年に開かれた日共の第六回全国協議会、いわゆる六全協からしばらくたったころに、東京大学学生新聞の一面コラム「風声波声」に書かれた、同時代人の一部には終生忘れられぬ、痛切な字句だ。
六全協の5年前の昭和25=1950年1月、コミンフォルム批判なるものが突然日共を襲い、これを引き金に日共は中央から末端組織まで、真っ二つに分裂した。その中で一方の〝党〟は翌年、地下で開いた〝全国協議会〟で〝新綱領〟、俗に〝徳球綱領〟と呼ばれた文書を採択、その第三部「軍事方針」で、武装闘争方針を決定した。それに基づき、街頭で火炎瓶を投げたり、交番を襲撃して警官に危害を加えたり、〝山村工作隊〟と称して真冬の山奥で革命の出撃根拠地を作ろうと試みたり、〝民族独立行動隊〟と称して学生と工場労働者が共同で〝軍事生産拠点〟の山猫ストや京浜工業地帯などの街頭で無届けデモを敢行したりして、若者が多数逮捕された。
もう一方の〝党〟はこうした妄動を批判していたが、翌年8月のコミンフォルム第二次批判で〝分派・分裂主義者〟の烙印を押されて、解消せざるをえなくなった。この段階で党活動や運動から離れる者、自己批判書という名の詫び状を書き正統とされた〝武闘派〟に復党を図る者、二つに分かれた。
六全協後も続く混迷
前者はともかく、後者は復党審査の〝総点検運動〟で、ついこの間まで対立していた相手から苛酷な扱いを受け、無意味な妄動を強制されて逮捕の憂き目に遭ったり、山村での困苦の中で疲弊して病死したり、自殺に追い込まれたり、するケースがたくさん出た。この文章は、その経過の、いわば〝総括〟だ。
六全協は分裂抗争で極端に劣化した党勢を再建するための、二つの〝党〟の便宜的な妥協策で、完全に末端党員を抜きにした、幹部だけによるいわば手打ち式として、地下で極秘裡に開かれた。2年前の昭和28=1953年のスターリンの死。それを反映した東ドイツやポーランドやハンガリーで起きた反ソ暴乱。さらにそれに先んじていた、日共書記長・徳田球一の逃亡先・北京での死と、彼が率いた〝党〟の壊滅。こうした事情も、当然ながら反映していた。
日共の混迷は、六全協後も数年は続く。敗戦・被占領から独立回復・復興と再建の時代で、最大の政治的事件だった日米安全保障条約改定をめぐる〝60年安保闘争〟の反対・抵抗側の主役は、明白に社会党左派、それとブロック関係にある労組の総評、そして〝反代々木〟を旗印にする〝新左翼〟がつくるいわゆる〝三派全学連〟で、日共の姿は主戦場の国会議事堂周辺にも、街頭や大学のキャンパスにも、ほとんど無に等しかった。彼らが一定の存在感を回復しはじめるのは〝安保〟の翌年、昭和36=1961年の第8回党大会以降だ。
2020年は、日共が長く〝50年問題〟と呼んできた、10年に及ぶ党分裂と、外は社会に対して、内は〝同志〟の間で、暴力に明け暮れた、一連の党史上の大汚点の出発点である〝コミンフォルム批判〟から、満70年の節目の年なのだ。
野坂参三の理論を徹底批判
いまとなっては一定の説明が不可欠だろうが、コミンフォルムは共産党情報局の略だ。マルクス・レーニン・スターリンは、共産主義政党は一枚岩の国際組織であるべきで、統一指導部が統率し、各国の共産党はその支部として活動する、という組織原則をとっていた。それが共産主義インタナショナルで、日共も大正11=1922年に、三代目のインタナショナル組織、コミンテルンの日本支部として、結成されている。
ところが第二次世界大戦中、武器援助をする条件として、アメリカのルーズベルトがスターリンに対し、コミンテルンの解散を要求した。背に腹は変えられず、これに応じたスターリンが、代わりの情報連絡機関の名目で設けたのが、コミンフォルムだ。なんのことはない、名前こそ変えたが、実態はソビエト共産党を総本山とするコミンテルンを衣替えしただけの、各国共産党をソビエトの手先として動かす仕組みで、戦後に生じた米ソ対立・東西冷戦では、〝東側〟の司令塔になった。そのコミンフォルムが1950年1月、機関誌で〝評論員論文〟の名で、日共幹部野坂参三を名指して、彼が唱える〝敗戦国日本はアメリカ軍の占領下でも平和革命が達成可能だ〟という〝理論〟を、徹底批判したのだ。
親族に明治以降の検察の総元締めともいえる人物を持ち、英国留学経験もある慶応ボーイの野坂は、結成いらいの日共党員だが、昭和3=1928年3月の弾圧で徳田球一や志賀義雄らが一網打尽で逮捕されたときも、なぜか逮捕を免れ、アメリカ経由でモスクワに渡り、コミンテルンで働いた。日中戦争が起きると中国大陸に移って中国共産党軍に協力し、対日本兵士の謀略活動に従事。日本の敗戦直後に当時の中共の根拠地・延安から、戦勝国アメリカの軍用ルートで帰国して、凱旋将軍のように大歓迎され、徳田球一書記長に次ぐ党の〝顔〟になった。
当時から野坂には出自も絡む官憲のスパイ説があり、主流・反主流対立の隠れた伏線にもなっていたが、ソビエト崩壊で共産党独裁下の暗黒政治の実態を示す文書が発掘されるにつれ、コミンテルン時代に日本から逃げていた党員仲間の女性関係を密告して〝粛清〟に追いやったこと、戦前の日本・アメリカの治安当局や、戦後はアメリカ占領軍司令部=GHQや中国共産党とも密かにつながっていた事実、など野坂の二重・三重スパイの証拠が続々出現する。野坂は同郷の宿敵だった宮本顕治が率いる党から、100歳を越す身で除名処分を受け、汚名に塗れて死んだ。
所感派による武装闘争
その野坂が〝凱旋将軍〟時代に唱えた〝平和革命論〟をコミンフォルムが否定したのに対し、徳田らは〝敗戦・占領下では奴隷の言葉で語らなければならない面もある〟という〝所感〟を発表する。これに〝国際権威〟に従え、と主張する志賀・宮本ら反主流が、下部組織まで全党を縦割りにして対立。別個の指導部と指揮系統を持つ、党分裂に至る。世間では主流の前者を〝所感派〟、反主流の後者を〝国際派〟と呼んだ。
その混乱の中で、同年6月25日にスターリン・毛沢東が金日成をそそのかして仕組んだ、朝鮮戦争が勃発する。在日アメリカ軍は国連軍の主力として直ちに応戦、占領軍司令部=GHQは即時日共の国会議員を公職追放し、事実上日共を非合法化する。〝所感派〟幹部は〝国際派〟を置き去りにして地下に潜入。徳田・野坂らは秋口に漁船で密出国し、〝義勇軍〟を出して朝鮮半島でアメリカ軍と激戦を続ける、前年の1949年に成立したばかりの共産党一党独裁国家・中国の北京に密航逃亡して、庇護を受けた。
スターリンは徳田を北京からモスクワに呼びつけ、日本から密航した宮本の代理・袴田里見との〝御前対決〟に引き出す。その場でスターリンは、〝所感〟を自己批判して謝罪した徳田一派を日共の正統と認め、そのかわり、朝鮮戦争の主敵であるアメリカ軍を背後で撹乱すべく日本国内で武力蜂起せよ、と命令する。その結果、翌年春から〝所感派〟の末端党員が、各地で火炎瓶を使った〝武装闘争〟を始めた。
そのピークが、対日講和条約が発効した直後の昭和27=1952年5月1日に、当時〝人民広場〟と呼ばれて大規模デモの舞台になっていた皇居・二重橋前の広場で展開された、いわゆる〝血のメーデー事件〟だ。この事件は、裁判官の誤判か、それとも左翼的・政治的偏向判決か、偶発的事件と認定され、騒擾罪は適用されなかった。だが同時期に起きた大阪の吹田事件、名古屋の大須事件と並べれば、計画的騒乱だったのは明らかだ。
定期検査でアリバイ作り
当時筆者は大学四年になったところ。旧制中学の最終段階から大学前半まで、共産党が仕切る全学連の活動に加わり、分裂に際しては〝国際派〟系だったが、前述した第二次コミンフォルム批判で〝国際派〟が分派と認定されたのを契機に、組織を離れていた。
しかし自治会のポストは残っている。文学部の自治会室で、メーデー当日に〝所感派〟が〝人民広場〟で騒ぎを起こす計画を知り、愚挙の巻き添えを食ってはたまらんと、たまたま軽い肺結核の定期検査時期だったので、当日に病院でレントゲン撮影を受けて、確実なアリバイを確保しておいた。
事件後に、大学内で第六委員長と呼ばれる実質的な学生部長だった尾高朝雄法学部教授に、突然呼び出される。確実なアリバイがあるなら、逮捕された多くの学生に対応するために大学当局と各学部の自治会が共同でつくる救援組織の、学生側代表になれ、という。交渉の当面の相手方のトップは、国島文彦警視庁本富士署長。のちに池田勇人首相の秘書官として、番記者の筆者と連日顔を合わせることになり、最後には警察庁長官となる国島は、筆者の旧制中学の11期、尾高教授は32期先輩だ。両大先輩は、かくかくしかじかで、大学病院のカルテでアリバイは完璧、という筆者の答えに、大笑いしたものだが、この経緯が〝メーデー事件〟の機微を、なにより生々しく証明する秘話といえるだろう。
不得意以前、ゆえの出番
筆者は昭和28=1953年に新聞記者になり、初任地・大阪で一年半ほど社会部のサツ回りをしたあと、政治部に転じて労農記者会に配属され、労組と並んで共産党も担当した。当時は各社とも、東京本社では分裂状態で火炎瓶をブン投げるだけの共産党はもっぱら社会部の警察庁・警視庁クラブに属する公安記者が担当する治安問題の対象で、政治記者が扱う相手ではなかった。だが大阪と京都だけには共産党の国会議員がいて、細々と選挙運動も続けている。そこで大阪本社では府庁・府議会の記者クラブか労農記者会に属する記者が、政党・共産党を受け持っていた。起
当時の日共は六全協の手打ちで〝所感派〟〝国際派〟混成の折衷的な執行部のもと、昭和33=1958年に第七回党大会を開き、〝国際派〟幹部だった宮本顕治―岡正芳ラインが主導権を握り、規約と綱領を一体化した新しい〝党章草案〟を叩き台に、綱領論議をはじめていた時期だ。ただの暴徒を追い回すのなら社会部記者でも勤まるが、共産主義政党の綱領論争となると一定の素養も理解力も必要で、そう単純ではない。さすがに左翼偏向の伝統を誇る朝日新聞には、公安担当と労農担当、いずれもアクの強いヴェテランがいて、張り合うように記事を連発していたが、筆者の属する産経の東京本社社会部公安記者はノンポリの君子で、不得意以前の状態だ。
そこで全学連当時のオルグ経験で日共関西地方委員会の反主流派の数人の幹部とも面識があり、この種の分野には一定の土地鑑が働く筆者に、出番が回ってきた。新興紙の産経が朝日・毎日と対抗するためには、〝テキに入社した学校秀才どもに東大や京大でエンゼツぶってたヤツを採るのが手っ取り早い〟というワンマン社長の採用方針で、他社なら確実にマイナスになる点がプラスに作用する産経では、学生運動の前歴を気にする必要がない。東京本社でも筆者の1年上の年次は、東大国際派組織の指導部のうち、不破哲三とのちに法政大学教授になる力石定一の2人を除く3人が、揃って採用されていた。このうち2人は経済部、1人は外信部で、3人ともすぐ退社して大学院に戻り、のちには揃って大学教授になる。元細胞キャップで経済部記者だった富塚文太郎は、長く東京経済大学の看板教授になり、学長も務めた。
政治記者だけの集まりが誕生
こういう事情で筆者も、駆け出しながら日共の綱領問題で大阪で原稿を書き、東京にも送稿することになる。他社も、なにぶん全国でここだけ日共の国会議員がいるのだから、彼らとの付き合い方を心得た記者がいる。そうした連中が労農記者会に集まり、関西地方委員会と掛け合って綱領問題のレクチャーを聞くようになった。そのメンバーが〝60年安保〟を控え各社一斉に東京本社に転勤、社会党記者クラブに集結する。日共側も〝宮本体制〟強化につれて、多田留治や下司順吉など、関西地方委員会の宮本系が代々木の党本部に移る。安保騒動を経て昭和36=1961年の第8回党大会で綱領を採択するのを控えて、大阪式の綱領レクチャーつき定例懇談会を開く話が双方で持ち上がり、公安担当の社会部記者は入れない、政治記者だけがメンバーの集まりができた。大田区民会館で開かれた〝新綱領〟を採択した第八回党大会も、初日と最終日はこのメンバーに公開された。
筆者はこの大会までは新聞記者だったが、昭和45=1970年の第9回党大会の前年にフリーになり、同じ産経系列の文化放送でニュース番組を持つ一方、執筆活動中心の生活に入る。最初の数年は、戦後日共論、宮本体制下で顕著になった企業内党員の内部告発に重点を置くフラクション活動の解説、さらに、人物・人脈紹介と、日共を対象とする単行本2冊、新書版1冊を立て続けに書いた。保守現実派の位置づけで論壇活動をするのはその後で、まず共産党専門で世に出たのだ。
党史を知らない? 陳謝要求
そうした経験に照らしても、2020年は日共にとって大きな節目の年だったはずだ、といわざるをえない。ところがそうした視点は、今回の党大会の論議でも、一般誌紙の論評でも、全然出ていなかった。そこには甚だ違和感が残る。
〝50年問題〟の教訓がいくつもあることは、明らかだ。70年前とは違い、いまの世の中では〝武装闘争〟の決起も〝国際権威〟への盲従も、表立って唱えるわけには、共産主義者といえども、できっこない。選挙に勝たなければ政権の獲得はありえない、という民主主義の政治システムが安定的に機能している国で、仮にも天下の公党を名乗る以上、たとえ可能性が薄くても、政権を目指す、といわなければ、店を張れない。共産党といえどもそこは同様で、〝革命〟なんか単なる建前でいいが、政権構想というCMは、掲げておかなければ格好がつかない。
そのホンネが古い建前を忘れさせたのか、つい最近、国会の答弁で安倍首相が日共の過去の暴力革命志向に言及したのに対して、日共の議員が取り消しと陳謝を求めるという、昔を知る筆者などにいわせれば、マンガとしかいいようのない珍事が起きた。確かに〝所感派〟が壊滅し、宮本顕治が当初は形式的に野坂をかつぎ、安定以降は上田耕一郎・不破哲三兄弟を両脇に置き、30年に及ぶ主導体制を築く中で、〝暴力革命〟を〝強力革命〟と言い換えたり、〝暴力革命〟必然論を〝敵の出方〟対応論に変えたり、言葉遊びにも似た詭弁を弄しつつ、それでも建前の余韻だけは残してきた。そうしたオールド・ボルシェヴィキの懐メロ的心情も、まして70年前の悲惨を象徴する〝共同墓地〟も知らない、不破とは古い仲間だった筆者にいわせれば若造の議員が、エラソーにいうのには呆れ返らざるをえない。お前サン、ちっとは党史を勉強せい、というほかには、言葉もない。
そろそろ党名を解明すべき時期
いまや、〝50年問題〟そもそもの発端になった野坂参三の〝占領下の平和革命論〟もびっくりの、〝共産主義者にとって選挙は革命の演壇である〟というレーニンの言葉も完全無視した、野党選挙協力による政権獲得を目指すためには党の候補者を降ろすのもためらわない、という選択をしながら、それでも共産党の看板は下ろさないのは、政治的・思想的誠実さの観点から、疑問が残る。
〝国際権威〟にしても、ソビエトに義理を立てて、米ソの部分核実験停止条約をめぐる国会議決で、党決定に反して賛成票を投じて除名された、かつては〝国際派〟の仲間だった志賀義雄とは違い、宮本は、こんなスローガンなんか、徳田〝所感派〟と戦うケンカの棒に過ぎない、と思っていたのだろう。〝自主独立〟という、それなりに剛直な彼の本質に即した立場をとり、ソ中に対し、党対党の関係でも、党として示す外交政策路線でも、明確な距離を置いた。
しかし宮本後継であるはずの不破の主導下の30年は、ソビエト国家が無残に崩壊したのに引き換え、口では共産主義を唱えながらも、実体は党が利権を独占する国家資本主義体制で経済的に急成長した中国には一目置き、それなりの評価をするようになった。
ところが不破の名を一応は残しながら、世間並みの政党感覚により近づいた今回の大会は、最近の中国の覇権主義的体質と、チベットやウイグルに対する人権抑圧が、国際社会で顰蹙を買っているのを反映して、再び一定の距離を置こうとする路線に転換して、綱領を一部修正した。そのあたりは当然といえば当然、機敏といえば機敏で、それなりにスマートな身のこなしといえないものでもない。
しかしそれなら、団地育ちのヴァイオリン少年の面影を残す志位和夫主導の日共は、反体制ムードが売りもののリベラル、いささかの懐古趣味を加えた〝50年調〟では〝りべらる〟の政治集団に過ぎないのではないか。「空想から科学へ」の、〝科学的社会主義〟〝理論政党〟が、〝りべらる〟にヘンシンしたのなら、〝民主的中央集権制〟も〝鉄の統制〟も。〝前衛党〟も昔話、そろそろ〝りべらる党〟に改名すべきだ、という気がする。
(月刊『時評』2020年4月号掲載)