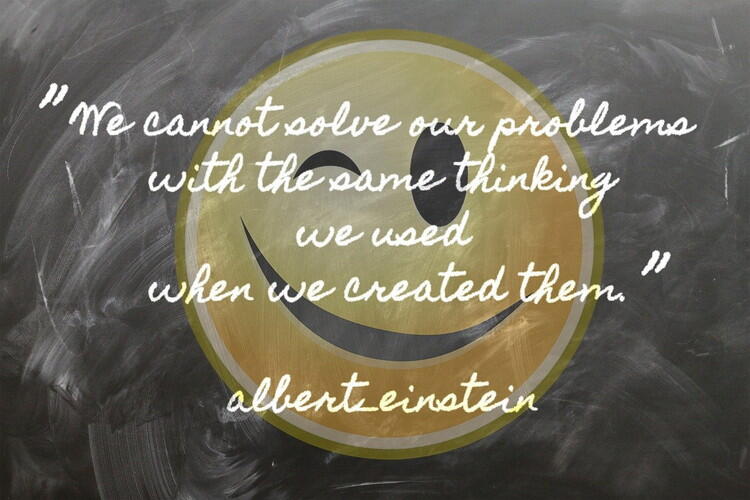
2025/03/03

~政治資金規正法の改正で溝 自民党の〝裏金〟はヒト事 公明党のいいとこ取り不満 政権交替につながりうるか 安定政局混迷化のきざしも~
典型は政治資金規正法改正
自民党と公明党との連立体制に微妙にヒビが入っている様相が、だれの目にもはっきりと見える状態で表面化してきた。
典型的な現れは、今通常国会最大の焦点とされる政治資金規正法改正をめぐって、国会に提出する案文に関する連立与党協議が整わず、自民党案の単独提出でスタートしたことだ。連立政権の与党だから、閣議決定した政府提出の場合は公明党も当然連帯して責任を負い、提出議員に党所属幹部議員の名を連ねるが、議員提出の場合でも両党から提出者を立てて共同提出の形にするのが常道だ、という考え方があり、いままではその通り運んでいた。今回も当初から自民党はそう思っていたようで、再三の呼びかけ、何回かの協議を重ねたにもかかわらず、公明党が乗ってこず、思い通りの姿にはならなかった。
今回の件は改めていうまでもなく、自民党内の派閥が主宰する運営資金の調達が主な目的のパーティ券の売り上げに関し、当選歴・党や政府のポスト歴などに応じてあらかじめ決められているノルマを越える売り上げをあげた議員、とりわけ若手議員に対して、超過分を党から所属議員に給付する政治活動費に上乗せしてご苦労賃の感じでキックバックしていた長年の慣習が、問題になったことに始まっている。万年政権党といえども、民間組織に過ぎない一政党の、さらに私的な集団である派閥のカネの処理を、公金を原資とする議員給付金とひとまとめにして扱っていたのだから乱暴な話で、議論の余地があることは確かだ。野党中の野党・日本共産党の機関紙「アカハタ」の記事がきっかけとはいえ一部の新聞が後追い記事を載せ、さらに特捜検察が刑事事件化したために、それに対処する政治資金規正法の一部改正が不可欠になった。
問題の性質上、政府提出でなく議員提出にするのは当然の処置だが、ことはつねづねカネで問題を引き起こし、検察の手が入ったり世間の批判を浴びたりすることが絶えない自民党がやらかした事案の後始末である。それなら自民党が一人でやればいい。オレたちは関係ない、というのが公明党の立場だろう。
信徒集団の一つから国政勢力に
公明党には、かねがね〝クリーンな党〟をアピールして〝金権腐敗の自民党〟とは対極的な立場にあると主張し、一定の存在感を確立してきたとする自負がある。ここ数年は重病の床に伏して政治的・社会的な発言が伝えられることもなく、久しく世間に存在感を示さないまま最近死去した創価学会の池田大作会長(当時)を〝創設者〟と昂然と謳って発足した政党という、日本憲政史上異色の成り立ちの政党であるだけに、結党当初の段階では、宗教的忠誠心を露わに見せる信者・党員の言動が独善的・排他的だとして、世間とも他党とも摩擦・衝突を生む事態を免れることがなかった。そうした面を持つだけに、〝クリーンな党〟という看板は絶対に守らなければならない党の生命線だったに違いない。
創価学会は日本が先に進出していた満州から中国の北支をきっかけに大陸に手を拡げ、世界大戦にのめり込もうとしていた時期に生まれた、日蓮宗の信徒団体の講、ひらたくいえば信徒集団のひとつだ。敗戦後の混乱の中で急速・大量に会員、つまり同信の信徒を糾合してきた。その過程で、新しい会員を獲得したり、他のグループに属する信徒を切り崩したりして入信を説得する、自ら〝折伏大行進〟と銘打った強引な拡大作戦を実施。〝王仏冥合〟つまり宗教が主導する政治の実現を意図していると受け取られかねないスローガンを唱えて、1950年代後半に東京の下町を中心に問題行動を多発させた。これを読売新聞が咎めて紙面で連日キャンペーンを張った。創価学会はそれに反発し、騒動は関西をはじめ地方にも拡散し、既成宗教・マスコミさらに地域社会も巻き込む摩擦をひろげた。
そうした中で彼らは国政進出を試み、まず参議院大阪地方区補欠選挙に元プロ野球の大投手を立てて獲得した1議席から始めて、60年代には参議院の全国区と主力地方区への展開、70年代に入り公明政治連盟を名乗って衆議院総選挙に進出、という段階を踏み、やがて公明党として社会党・民社党とともに〝社公民〟路線を組み、自民党政権と対決する勢力の一翼を務めるようになる。
公明党がいまとるべき姿勢とは
こうした半世紀の中で創価学会・公明党ブロックは次第に一般の世俗団体とそう変わらない姿に落ち着いていく。かつて日本社会で一定の存在感を示した総評・社会党ブロックや同盟・民社党ブロックが影も形も止めないほど雲散霧消したのに比べれば、創価学会も高齢化・活動力低下は免れないものの、まだそこそこの存在感は残しているし、公明党はいまや自民党と組んで連立政権体制をとり続けて久しく、かつては厚生労働、いまは国土交通という重要閣僚ポストを、首相・内閣が替わっても指定席として専有し続けている。
いずれも対象とする分野が広大・多岐にわたり、従って予算額も大きいし、関連する公的・私的団体から〝裾野〟を全国くまなく張りめぐらす大企業を根幹とする関連業界まで、対象領域も全省庁の中でも群を抜いている。創価学会が拡大期に大量入信した会員の高齢化に伴い伸び悩み、国政選挙の得票数もジリ貧状態を続ける中で、厚労あるいは国土交通の既得権益は手放すわけにはいかないのだろうが、しかしそのことと党の基本線の〝クリーン〟の誇示とはあくまで別次元の問題だ。
自民党が現に問われていて、当面の政治資金規制法改正の直接の対象になっている〝裏金〟疑惑は、要するに自民党が起こした事件にすぎない。それをどう収拾するか。再びそのような問題を起こさないためにどのような法改正をし、どのような規制措置を加えればいいか。こうしたことは問題の当事者である自民党が考えるべき話だ。公明党を含めて他党がいまとるべき姿勢は、自民党が問われている問題を他山の石として注視し、もし必要なら、それぞれの党が法改正・規制措置のあり方を考え、独自の議院提出案件として国会審議の場に出すなり、現に出ている自民党案に対する衆参両院の質疑・採決に至る局面で修正案として明らかにするなりして臨むべきだ。それと連立与党として政治運営の責任を共有する立場にいることとはまったく別次元の事柄で、それ以上のものでもそれ以下のものでもない。そう考えたのだろう。
同一歩調を拒むならば
それとは別の立場から、本来の筋目としていえば、連立を組んで閣外協力ではなく与党として一心同体の関係にあることを明らかにして閣僚を出す以上、たとえ政府提出案件でなく、事柄の性格上の差異もあって議員提出案件にしたとしても、あくまで同一歩調を取るべきだ。それを拒み独自路線をとった以上は、その段階で連立を白紙化するのが憲政の常道、政党政治の枠内での連立政権のあり方だ。こういう議論は当然、成り立ち得る。
筆者も原則的にはこの立場をとるのが妥当と考えるが、新聞もテレビも、どの学者もブラウン管の常連コメンテーターも、こういう趣旨で記事を書いたり、この観点から発言したりしていた事例を、寡聞にして知らない。ただし彼らが見過ごしていたり、一応は気になっていても見て見ぬふりを決め込んでいたりしても、自民・公明両党の少なくともヴェテラン級の政治家の中には、これは公明党がフトコロで当面温めておこうとしている三下り半のアタマ書きの部分だな、と感じる向きが、決して少なくなかったのではないか。
問題の法案は、自民党がぎりぎりまで公明党との連名議院提出を意図して決断を遅らせたため、5月下旬にようやく衆議院の委員会審議が始まった。ここからの単独提出議案のスタートでは、今国会の当初会期が終わる6月23日までに衆参両院を通過して成立するのは本来容易でない。本稿が編集・印刷・製本・流通の段階を経て読者の目に触れる時点では、すでに結果が出ていることだが、国会会期が延長され小田原評定をだらだら続けているか。どこかの時点で公明党が自民党に妥協し自民党の議員提出案を成立させるか。逆にどうしても今国会の当初会期中の成立に漕ぎ着けたい岸田総理総裁が脆くも屈服して公明党案をはじめ別途提出されていた立憲民主党を中心とする野党案を、ひとまとめに丸呑みして修正成立させるか。自民党案の否決で流産に終わるか。これらのうちどれかに決着することになるが、自民単独では参議院の過半数に足りない、という厳しい現実があるから、自民党提出の当初案成立は困難だ。
維新との連立組み換えに直結?
そこでいくつかの打開策が不可欠になるわけだが、日本維新の会が自民党と協議して衆議院を強行突破した当初案を参議院で可決・成立させたとするならば、これは即、連立の組み替えに直結する。仮にそのように事態が運んだとしても、新しい自民・維新連立政権の基盤は極めて脆弱で、ただでさえ内閣支持率が30%を切る、断末魔といわれる水準を半年以上も続けて末期症状だった岸田政権の力が、さらに低下するのは間違いない。つまり政治資金規正法の今回の改正がなんとか実現しても、流産に終わったとしても、岸田内閣は存亡の危機に立たざるをえず、政局が動き出すことは必至と思われるが、その一方でいまの自民党の、そして立憲民主党を中心とする野党陣営の、まるで話にならない、劣弱さ、非力さ、無気力さ、という実情がある。
いままでの自民党なら、とっくにポスト岸田を窺う複数の人物が公然と、あるいは公の場では表明していなくてもだれの目にも察しがつく形で動き出していたに違いない。野党でも政変必至と見てとって、自民党を中心に続いてきた政権の受け皿となる非自民勢力の結集を図る動きが、それぞれの党の基本路線を踏まえ、立ち位置や力関係にも応じて、活発になっていたはずだ。
しかし今回はこうした動きが極めて鈍かった。ゴールデン・ウィーク直後に小泉純一郎と山崎拓という、昔の名前で出ています、とさえいいにくいほどこのところ目立った動静がなかった古豪が、久しぶりに政局の場に登場して石破茂に会って決起を促したとか、それを石破が受け流したとか、ゴシップ・レベルの記事が小さく報じられたが、小泉は石破を短期政権の座に就かせて政界人事の回転速度を上げ、次男の進次郎に順番が早く回るのを期待しているのだろう、と政界雀に大笑いさせるのがせいぜいの結果に止まった。
上川潰しを図るという〝事件〟
その石破・小泉(進)・河野太郎のいわゆる〝小石河〟とひとまとめに呼ばれるポスト岸田候補の常連に代わる、フレッシュな候補として名前が上がることが多くなっていた上川陽子外相は、地元静岡の県知事選挙を支援する女性団体の集会で、女性の〝生む力〟で新知事を生み出そう、と演説したのに関し、子供のいない女性、生みたくてもさまざまな事情で生めない女性に対して無神経、といった批判のための曲解、攻撃するための揚げ足取り、というほかない誹謗中傷を、ネットや一部の〝市民団体〟、立憲民主党の泉健太代表らが浴びせ、それを偏向で定評のある一部新聞や面白半分のテレビ・ワイドショーが伝え上川潰しを図るという〝事件〟が起きた。この騒動に対して、いまやテレビ画面に写るのが唯一の生き甲斐となっているとしか思いようのない岸田首相が、総理官邸毎度の〝ブラ下がり〟でコメントを求めたテレビに、無視して通り過ぎ取り合わなければいいのに、あの発言は適切でなかった、とオゴソカに上司として評価を述べたのは、お笑いだった。
安倍晋三長期政権の後、岸田政権の前にほぼ1年間だけの短期政権を繋ぎ役的に担った菅義偉も、周囲の数少ない側近を動かして再起を期す構えを取ろうとしているという風説を流しているかに見える。現に自民党幹事長である茂木敏充が、時期は示さないものの、いつかは政権を担当したいという意を岸田に伝えた、という新聞記事もあった。岸田首相もまだ9月に最初の任期が切れる自民党総裁としての再選、つまり総理続投を望んでいる感じを漂わせていないものでもない。
本格的な政局展開への期待
しかしなにも仕掛けないで9月までダルマのように座っていて総理総裁の座が転がり込んでくるほど世の中は甘いものではないし、いまの自民党や岸田内閣を取り巻く世間の空気も暖かいものではない。というより、四面楚歌に等しい状況だ。岸田首相は政治資金規正法改正に関する自民党案の独自提出に際して、それで国会を乗り切れると考えているのか、と記者団に問われ、国民の信が大事だ、と自民党総裁改選に先立って衆議院の解散―総選挙に踏み切る可能性もかなり強く匂わせていた。しかしさすがに現状では、ひところ有力視する説がかなり流れていた今国会会期末の解散は、まず考えにくい。
公明党の離反とも取れる政治資金規正法改正案の連立与党による提出が叶わず、単独提出を余儀なくされたのを反映し、かつ来年には確実な参議院の定期改選と任期切れの衆議院総選挙を前に、なにかと準備が整っていない公明党に向けた抜き打ち解散のブラフ、といった側面も、〝国民の信〟発言の背景にはあっただろう。公明党の意外な腰砕けが起きたとしても、今国会の会期末解散がなければそれで当面の政局の緊張は一山越す、という状況ではまったくない。余りの不人気の〝証拠〟続出に岸田首相が再選を断念すればそこで片がつく、というものでもない。
万が一、自民党内の無気力の極、秋の自民党総裁選で岸田再選を阻もうとする対立候補がまったく現れず、無競争再選になってしまうという超レア・ケースが起きたと仮定しても、先に指摘した通り来年初夏には参院選、どんなに遅くても秋には次期総選挙がある。そのときにまだ岸田が居座っていたら自民党がどんな目に遭うかは、だれもが容易に想像できる。だからこそ今国会終了後には自民党内も、さすがに野党も動き出し、本格的政局が久しぶりに展開されることになるだろう。
学会内に永く淀む反自民感情
公明党の〝三下り半のアタマ書き〟は、一応は空振りに終わったが、公明党もただアタマを掻いて引き下がったというわけでもなかろう。夏の政局の展開を見ながら、だれがどのような勢力を集めて遅くとも初秋には行われるに違いない岸田退陣後の自民党総裁選挙に臨むのか、じっくり様子を極めたうえで、組む相手を選ぼうとするに違いない。
その相手が必ずしも新しい自民党総裁だとは限らない。野党が一致して非自民・非共産の陣形を整えることに成功すれば、立憲民主党の泉健太代表よりも総理候補として世間の納得を得られるような重みのある存在、例えば野田佳彦元首相のようなヴェテランを新しい自民党総裁の首班指名出馬への対立馬として推すとしたら、公明党が同調することもありえないとはいえまい。むしろ公明党が裏で動いて立民・維新などに働きかけ、そのような展開を演出していくことだって、まったく考えられないものでもない。
筆者がそう考える背景には、創価学会とりわけ創価学会婦人部に永く淀んでいる反自民感情に公明党が引きずられる可能性が、ことに自民党の不祥事を踏まえて行われるとされる次期総選挙では、強いと見られる面があるからだ。と同時に、その裏を返して見ると自民党内、とりわけ岩盤保守層と呼ばれる自民党の超固定支持者の中に、これ以上の自公連立体制継続には我慢ならん、という空気が急速に広がりつつある、という印象もある。
世論調査を信用できない実例
筆者は新聞・テレビの世論調査というものを余り信用していない。余談になるが例えばこういった極端な実例があるからだ。
ことしの5月3日の憲法記念日の『朝日』『読売』両紙の一面を飾った〝憲法意識〟に関する世論調査。ともに層化無作為二段抽出方式という、科学的に正確公正であることが広く認められている、と定説のある手法で実施した結果だというが、『朝日』の世論調査の解説記事の主見出しは『改憲機運「高まっていない」70%』。脇見出しは『自民支持層でも6割超』。『読売』の本記の主見出しは『憲法改正「賛成」63%』、脇見出しは「9条2項〝改正〟最多53%」。ちなみに9条に関しては『朝日』は本記の脇見出しで『9条改正反対は61%』とあった。
同じ問題を、ほぼ同じ時期に、〝科学的に正確公正〟と定説があるとされる同じ手法で調査して、正反対の答えだ。こんなことがありうるはずがないのに、これが現実だ。これでも、信用しろ、といわれて、そうですか、と簡単に返すわけにはいくまい。
こうなった原因は察しがつかないものでもない。〝調査〟方法は、設問を書いた回答書を郵送し、マークを書き込んで返送してもらう方式だったようだ。送付元・返送先が新聞社宛になっていたか、予断を避けるために調査機関の事務所という形をとっていたか、そこは紙面からは分からないが、回答の宛て先が社名だったり、そうとすぐわかるアタマ隠してシリ隠さずの状態だったりしたら、イマドキの回答者の少なくともかなりの層は、信仰的護憲派の『朝日』には彼ら向けの、保守の『読売』なら相手が喜ぶような、テキトーな回答を書き込んで返送してやるくらいの、遊び心は持ち合わせているのではないか。そうでなければ、層化無作為二段抽出方式で調査して、こんなに見事に正反対の回答が出ることなど、ありえまい。
両党支持者の相互不信は極限に
世論調査は信用できないという私見を証拠つきで書いておきながら、こういうのもいかがなものかという気がしないものでもないが、最近の新聞・テレビ各社の定例世論調査の記事を見ていると、自民党支持の数値の中で、自民党支持者の岸田内閣支持者の比率がかなり低くなっているのが目につく。これは自民党は基本的に支持するが、党内から総スカンを食いながら、公明党にせがまれたと思われるチンケな薄く広いバラ撒き施策を、国債を中心に国の累積債務がGDPの2倍に迫る1300兆円近くなっている財政悪化にもお構いなく続ける、創価学会―公明党だけが頼りの岸田政権には、ほとほと嫌気がさした、という保守層が増えている現れではないか。
最新の衆議院の三つの補欠選挙、さらに静岡県知事選挙の票の流れを見ても、創価学会―公明党票の自民党候補離れは、完璧といっても過言でないほど、全国的・組織的に進んでいると思われる。自公両党の支持者の相互不信は、いまやそれぞれの組織・地域の末端にまで浸透し、もはや極限にきた、というほかないと思われる。
公明党がポスト岸田でどの人物に肩入れして奏功し、新総理総裁の初組閣で従来と同じ閣僚ポストを得ようとしても、相手がその通りに応じてくれるかどうかは、分からない。同様に、麻生太郎政権による解散・総選挙で自民党が敗退して民主党首班の鳩山由紀夫政権実現という結果になったとき、公明党が自民党とともに野党に回った、あのような選択を避け、自民党と手を切って新しい非自民・非共産の陣容を組んで政権交替を実現することも、ないとはいえない。往年の非自民・非共産8党・会派連立の細川護熙・羽田孜両政権のときのように、二つの内閣あわせて一年も保たずに政権を失った失態に終わればまだしも、この状態が続くわけはないとタカをくくれる保証も、はどこにもない。
思えば日本が活気に充ちていた昭和時代の政界は、一寸先が闇、といわれた。闇と活気は本来両立しないだろうが、政界の激動には経済社会の活発な動きが反映していた。平成以降の〝失われた時代〟は、経済が停滞する一方で、政治は予定調和式な安穏さを漫然と続けていて、それが社会の無気力な安定感と直結していた。しかしこれからは経済も社会も明るさを失い続け、政治だけが闇の中の駆け引き、暗闘を続ける姿にならないとも限らない。それがなにを齎すか、そこが問題だ。
(月刊『時評』2024年7月号掲載)