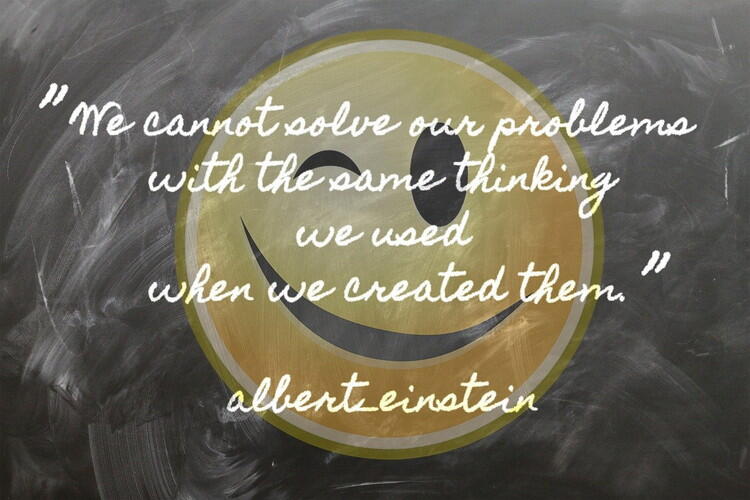
2025/03/03

~民主政治は政党政治 政党に派閥は不可欠 派閥否定は大間違い 政党解消の苦い過去 その主役だったのは~
議会制度のチェックポイント
民主主義といえば議会政治、議会政治といえば政党政治、というのは常識中の常識だ。しかし、そうはいっても、これは中学校の社会科教科書レベルの理解でしかない。議会政治の基礎になる議会制度には、一院制か二院制かに始まり多くのチェック・ポイントがある。
一院制の場合は、一定以上の年齢の全国民を有権者とする普通選挙で成り立っているか。議員定数があらかじめ階層別・業種別・団体別などに分割して割り当てられていて、それぞれから議員を選出する仕組みか。議員定数の相当部分が軍や特定政党に割り当てられていて、一部が普通選挙であるに過ぎないか。議員全員が独裁権力をほしいままにする勢力による任命制か。こうした違いがある。
二院制の場合には、連邦国家と名乗るにふさわしく片方の議院に州・連邦の代表色を強く持たせたアメリカやドイツ型、普通選挙と特定選挙や任命制の議院を並立させたタイプなど、主に上院に特色を持った例が多い。いずれにせよ議会があるというだけで民主政治の保証になるとはいえない。
担い手である政党の定義とは
同様に政党政治といっても、政党が一つしかないか、複数政党制か、に始まる区別がある。権力を握る勢力が自分たちの党だけしか議会の構成組織として認めないか。あるいは実態を粉飾する「用途」でいくつかの小規模な同調政党を配置しておく旧ソビエトや現在の習体制下の共産中国のような姿を取るか。いずれにせよ、これでは議会は一党独裁の専制政治を修飾する装置だとしかいえず、民主主義の対極にあるというほかない。米英式の二大政党対立・単独政権交代型、ヨーロッパ大陸に多い中規模政党分立・連合政府型、国情や歴史的経緯に応じた違いは存在していても、普通選挙で民意を問うて議会の多数を制した勢力が国政を担当し、その後の議会の勢力分布の異動や、もちろん次期総選挙の結果で政権の継続か交替かを決めるのが民主主義政治なのは、いうまでもない。
そこで次に民主主義政治の担い手としての政党の定義が問題になる。一般論として政党の要件として綱領・組織・運動の三点があげられている。独自の政治綱領と一定の方向性を持つ政策の体系。地域や職域に根差した基礎組織から、中間的な管理機関を経て中央に至る確立された組織形態と、それに応じた権限と規律。さらに独自の政治的・社会的・理論的運動を展開している実態。そうした内容を具備した、加入者が個々に自由意思に基づき参加する政治結社を政党と呼ぶわけだ。
鉄の規律を掲げて党議決定に対する党員個人の勝手な意見表明は許さない、という姿も政党の一つの在り方として成り立つのかもしれない。自分の意思で党則や党規を承認して入った以上はそれに拘束されるのは当然、という面があるからだ。しかし少なくともそうした組織は、自由で民主的な性格の政党とは認められないだろう。
派閥に対する感覚は違って当然
そこで出てくるのが派閥の問題だ。既存の綱領・党則を承認した上で入党したといっても、鉄の規律が一国の中だけでなく国際的にも同じ党名を謳う同じイデオロギーに立つ政党の間で共通している党と、「自由」「民主」を真正面に掲げる党では、まったく体質が違う。具体的にいえば、日本共産党と自民党とは「派閥」に対する感覚・感情が違うのは当然、という話だ。
とはいえ日本共産党にも派閥抗争が存在した時期があった。いまも「50年問題」といわれている、敗戦間もない朝鮮戦争下の1950年に、アメリカ軍の日本占領司令部の弾圧を食らったトップの徳田球一書記長以下、主流派幹部が、毛沢東主席で建国して一年もたたない中国・北京に集団「亡命」し、取り残された志賀義雄や宮本顕治らが独自の方針、独自の指導部を構成して、全学連の学生を中心に活動していた時期のことだ。
社会党には長い期間、右派社会党・左派社会党と名乗って派閥がまったく別の政党として国会で活動し、そのあり方が社会でも当然視されていた時期があった。その中でも右派では河上丈太郎派・西尾末廣派など、左派に至っては鈴木茂三郎派・和田博雄派・松本治一郎派・野溝勝派などがシノギを削って抗争していて、その激しさは対保守勢力や対共産党とは桁違いの苛烈さだった。しかも主に左派には各派横断的に、共産中国との貿易利権を握るグループ、ソビエト共産党から継続的に資金援助を受け取るグループ、北朝鮮との特殊な交易ルートを持つグループ、という隠れ派閥さえあったのだ。
成り立ちとして当然、健全な姿
その中で1955年に吉田茂の自由党と鳩山一郎の民主党が「保守合同」してから半世紀以上にわたり、一部の離反・脱落があったとしても大筋で一党体制を通し、ほぼ一貫して政権を維持する自民党に、派閥が存在しないほうがむしろ不自然というものだろう。明治23=1890年の帝国議会開設いらい、当初は薩長勢力中心の「官党」に対抗する旧幕府・佐幕系や町衆が吹き寄せられて集まった「民党」。大正・昭和戦前からの政友会・民政党の二大政党の流れ。そこに吉田自由・鳩山民主それぞれの人脈が交錯して生じた色とりどりの人間模様が加わり、派閥という形で自民党という身体を構成する手足や器官として存在する。こうした姿は、政党の成り立ちとしては当然であり健全というべきだ。
筆者は長らく、自民党は伝統保守とリベラル保守の議員がそれぞれ気の合う仲間で集まった数個のグループ、つまり派閥を基礎単位とする連合政党であって、日本の政治構造は、米英式の常に政権交替の可能性を孕むほぼ同等の力を持つ二大政党が拮抗する構造でも、西欧式の中規模のいくつかの党が連立して中道右派か中道左派いずれかの路線で政権交替を重ねる構造でもない、実質的には特殊な多党制と見るべきだ、と主張してきた。たまたま自民党が一つの形にまとまって政局の中枢に存在しているが、本来の姿は伝統保守から保守系リベラルまでのそれぞれ自己完結した議員グループつまり派閥の群れと、共産党・公明党、さらに率直にいえば保守・リベラル・時流便乗組などそれぞれ何色かに分類できる立憲民主党や日本維新の会の部分、さらにミニ集団、そこに一人一党までが加わり、双方あわせると都合10余プラス・アルファの集団で構成されるというのが日本の議会政治の正体なのではないか。こう見てきたわけだ。
現状は保守派閥連合の自民と畑違いの公明党で連立政権を形成しているが、これは組み合わせの一例に過ぎない。公明の代わりに維新や立民から割れた保守組の片方、あるいはその両方が自民と連立しても、なんの不思議もない。別の視点で見れば、いまの野党が無理に水と油を混ぜたような連合を組んで政権交替を図ろうとするのは、いかにもチエのない話であって、なぜ非自民の保守グループがそれぞれもう少し力をつけた上で意を通じて連合し、自民党を構成する派閥のいくつかを切り取って政権を奪取しようと策謀しないのか、そこが万年野党の野党呆けたる所以だとも思ってきた。
端緒はロッキード事件にあり
それはさておき、そもそも社会党が自民党そこのけの派閥抗争を、しかも労組やその対極にいる資本陣営からはおろか、ソビエトからの現ナマや対中国、対北朝鮮貿易の利権争いも含めた、いかがわしい援助に頼ってやっていたころは、世間も、それをリードするマスコミも全然問題にしなかったのに、なぜ前世紀の末ごろから自民党の派閥だけを、たびたび問題にするようになったのか。
その背景には、社会党が激烈な派閥抗争の末に共倒れ式に消滅し、共産党にもひところの勢いがなくなり、生まれては消える新党もパッとせず、自民党以外に政局記事のネタ元がなくなったことも作用しているだろう。反自民を正義と盲信する左翼偏向した新聞・テレビと、それに便乗した一部の検察の姿勢も大きく作用しているといえるかもしれない。
こうした傾向の端緒になったのがロッキード事件であることはいうまでもない。しかし冷静にいえば、この事件は日本の民間航空会社とアメリカの旅客機製造会社の取引に一部の政治家が関係したかどうか、という問題に過ぎない。この事件とほぼ同時に、巨額の国家予算が投じられる、自衛隊の戦闘機をめぐるダグラス・グラマン社との疑惑が存在していた。それにもかかわらず、田中角栄前首相(当時)が関係するロッキード事件は政府・検察・マスコミが一致して大事件化させた反面、三木武夫内閣の与党幹部として田中と対立する福田赳夫派を代表する存在で、ロッキード事件追及の正面に立っていた松野頼三が関係していたダグラス・グラマン疑惑は、内外の一部で報道されただけで、検察もマスコミも野党勢力も、ピクリとも動かなかった。
リクルート事件で大騒ぎした直後の時期には、前述した社会党議員らのソビエトからの資金受領や、共産中国・北朝鮮との貿易利権が表面化していた。しかしこれらも、1990年のソビエト共産党政権の崩壊に伴って流出した文書がモスクワで発見され、現地で報道されたのが端緒だった。外国のカネが国会議員に定期的に流れていたというのは、国家反逆罪にもなりかねない、たかが人寄せ稼業のリクルートの政治献金とはくらべものにならない大事件のはずだ。しかし現地の報道が伝わり、さすがに日本のマスコミも多少は取り上げ、国会でも形ばかりの質疑は出たものの、かつてダグラス・グラマン事件が、松野頼三がヘドモド弁解しただけでうやむやになったのと同様に、時効の壁や、なによりモスクワ相手では証拠調べ・事実解明が困難だという事情もあったには違いないが、検察は完全にノー・タッチだった。
想定される、裏金の使い道
今回の自民党派閥の政治活動費の裏金問題にしても、そんなことはお前らが現役の政治記者だった「料亭政治」全盛の半世紀以上も昔の話でいまでは絶対にない、という反論が出るに違いないが、少なくとも裏金の相当部分は国会対策上の取引のため、あるいはその下地となる日常の懇親のための、野党との会合―会食費に消えたに違いないと筆者は思っている。それだけでなく、新聞記者やテレビ局の上層部から現場までの多くの関係者、常連コメンテーターの「学者・文化人」、実力派官僚、ひょっとすると元検察の大物も含む弁護士との会食も、あったかもしれない。
現に今回ヤリ玉にあげられた自民党の萩生田前政調会長は、記者団やカメラに取り囲まれる中で、「各方面の多くの政治家や学者・マスコミ関係者との会食」などに使ったと、はっきりいっていた。だがこのやりとりは、とっさには隠しようがないライヴ中継中に一瞬流れてしまっただけで、毎度使い回される裏金問題をめぐるテレビの保存映像には、たぶん局側が不都合と思って神経質につまむ、つまりカットしたのだろうが、筆者の見聞した限り、その後この「絵」は流れていない。
政治資金の裏金問題は、年明け国会でも本来の責務である予算審議そっちのけで、連日野党が取り上げている。正確にいえば、真面目な予算関連の質問もある程度は行われているのだが、火事とケンカと自民党攻撃はデカいほど数字つまり視聴率が取れる、と思い込んでいるテレビがこの攻防だけを取り上げ続けているので、世間にはそういう印象が強くなっている、ということなのだろう。これは筆者のヤブ睨みかもしれないが、この裏金問題に関して、筋からいえば少なくとも当面は自民党の最高責任者として対処しなければならない立場の岸田首相が、むしろ野党の尻馬に乗って、というのが言い過ぎなら野党に調子を合わせて、火の手を掻き立てている観が拭えないでいる。
党内力関係、さらに総裁選へ
筆者の視線の向かう先には、一つにはいまの自民党内の力関係、もう一つにはこの秋に迫る次期自民党総裁選挙との絡みが見えている。岸田は保守本流の自民党池田勇人派・宏池会の後継者を自認しているが、筆者が前々号・前号で指摘した通り、彼は到底宏池会主流の後裔とはいえないし、嫡流を継ぐ出自でもない。池田の政策に関する知見も、筆者ら池田内閣の発足から終焉までを見続けた古参記者から見れば、考えられないほど杜撰だ。
百歩譲って彼が現に宏池会の代表だとしても、この派閥は自民党第四位の位置で、実際に彼は、自民党総裁候補として常に泡沫に毛の生えた存在に過ぎなかった。それが総理総裁になりおおせたのは、史上最長の首相在任を誇った安倍晋三が意外の任期途中の退陣をした後、官房長官から昇格して受け継いだ菅義偉が、安倍の残余任期だけの一年で退陣した、いわば人事空白の埋め草として、図らずも浮上したからだ。
党内基盤の弱い岸田としては、安倍が暗殺された後も党内最大勢力を保つ安倍派や、党内を裏金とともに裏技でも仕切っている二階俊博の動向に、常に留意・配慮しなければならなかった。その目の上のタンコブともいうべき安倍派と二階が、萩生田光一や西村康稔という次期総裁選の有力候補とともに、今回の裏金騒動で動きがつかなくなった。もともとマトモな政策体系を纏めるだけの力量も、派閥を率いる実力も、有力な派内の参謀格や党外のブレーンもなく、もっぱらテレビが騒ぎ立てるトピックス的「課題」を扱ってブラウン管への露出を図ることしか政権維持の手段がなかった岸田としては、この騒ぎは絶好のタイミングで降って湧いた助け舟だった、といえるだろう。
派閥の領袖でもなければ、領袖の側近として派内・党内の切り盛りに腐心したわけでもない岸田は、派閥などは利用できるときだけ利用すればいい、他人が整備して用立てる、都合のいい乗り物のような存在だ、と思っていたのではないか。これも前号で触れたことだが、岸田家と縁戚関係にあり、岸田文雄の父親の文武が常に傍らに付き添っていた宮澤喜一は、レッキとした宏池会の系譜を継いだトップとして総理総裁になったが、派閥運営についてはまるで無関心で、他人事として英字新聞を読み耽る視線の外に置きっ放しにしている、としか思えなかった。
資料で紐解く初代・正記
岸田文雄首相は代議士としては三代目だ。商工・通産官僚出身の先代の父親・岸田文武の存在はよく知られているが、なぜか初代に言及されることは、本人の口からも新聞・テレビなどでも、まずなかった。その点はなんとなく不思議に感じてきていたのだが、彼の派閥に対する視線が極端に冷たいので、改めて岸田父子、さらに初代にまでさかのぼって資料を当たって見て、思わず、そうだったのか、と膝を叩く感があった。『議会制度百年史』全12巻(平成2年11月発行 衆議院 参議院 編集 より大きな判形の別冊『目で見る議会政治百年史』がある)の一冊である『衆議院議員名鑑』213ページを見て、わかったことだ。
引用する『議員名鑑』に、岸田姓の代議士は文武の他には一人しかいない。文雄が政界に進出する前の資料だから載っていないのは当然の話で、したがって初代は岸田正記とわかる。彼の初当選は1928(昭和3)年の初の「普選」で、戦時下のいわゆる「翼賛選挙」まで6回連続当選し、敗戦後の公職追放を経て、現行憲法下の国会には1953(昭和28)年の1回、計7回当選した。この間に選挙制度や選挙区制の変転は何度もあったが、文武、文雄の三人とも、それぞれの時期の広島一区から出馬して当選している。ただ代替わりの間にそれぞれ空白期間があった。
その岸田正記の項をそのまま、引用すると 「岸田正記 広島県第一区選出 自由党
明治28年12月生・広島県出身・大正13年京都帝国大学法学部卒○大連において不動産業を営み、次いで大連及び奉天幾久屋百貨店を経営す、戦後幾久屋商事社長、穏田マンション(株)社長となる、第一次近衛内閣の海軍参与官、小磯内閣の海軍政務次官、大蔵省、大東亜省各委員となり、また立憲政友会会計監督、翼賛政治会国防委員長、大日本政治会大東亜委員長、進歩党会計監督、自由党総務となる・南洋方面視察のため議員団長として派遣さる○当選七回(16 17 18 19 20 21 26)○昭和36年6月3日死去」
となっている。
日常的に継承された表現
この記述から想像できることがある。前号で筆者は、岸田文雄がなんらかの政策課題に新しく着手しようとするとき、「私が先頭に立って」「火の玉のように」取り組む、という言い回しをすることが多く、このフレーズの正体を知らない戦後生まれ世代のテレビのコメンテーターなどからは「火の車」「火だるまになって」といったと歪曲されて揶揄の対象になっているが、この「火の玉」という表現は、シナ事変下の大政翼賛会の国民総決起スローガン「進め!一億 火の玉だ」に由来していると思われる、と指摘した。
このときはここまでで止めて置いたが、戦後の1957(昭和32)年生まれで、祖父が亡くなった年にやっと幼稚園の年少組相当の幼児だった彼が、生まれる20年近くも昔に流行していたこのスローガンを、自然に耳で覚えていたはずがない。とすれば「火の玉」という特異な表現は、日頃のテストから進学受験、もちろん歴代の度重なる選挙でも、岸田家では正念場に臨む心構えとして、祖父・子・孫に至るまで、古びて死語になることなく、日常的に使われてきたのではないかと思われる。
いうまでもなく岸田正記の長い政治生活のハイライトだった翼賛政治会・大日本政治会は、シナ事変に際して国民総動員体制をつくりあげるために近衛文麿内閣下でつくられた大政翼賛会の傘下組織である。この大政翼賛会は、挙国一致の戦争政治体制を固めるために、政友会・民政党から普選後に新勢力として議席を伸ばしてきたいわゆる無産政党までのすべてを強権的に解消させ、ナチ一党独裁のヒトラー・ドイツのように一国一政党体制の戦争推進議会をつくるために、軍部の強い圧力のもとに生まれた組織だ。
『議員名鑑』の記述を見ると、それまでは岸田正記は初当選いらい一貫して政友会に所属していたようだが、ポストに恵まれなかった観がある。その彼にとって、翼賛政治体制下の二つの委員長ポストは、政府入りした海軍参与官・海軍政務次官とともに、生涯のハイライトだったに違いない。その思いが敗戦後も長く尾を引き、「火の玉」というひところは大流行したものの、戦後はぱったりと人々の口に上ることがなくなった特異な表現が岸田家には延々残っていて、総理総裁になった孫のエンゼツや国会答弁、記者とのいわゆるぶら下がりの応答にも、つい出てきてしまったのが、正直なところなのではないか。
党人派と呼ばれるべきところ
「火の玉」だけなら他愛ない話ともいえるが、正記の不遇だった政友・民政時代の政党政治への苦い記憶と、生涯のハイライトだった政党解消・翼賛政治時代への郷愁が、政党不信となって岸田家の家風になっているとすれば、これは容易ではなくなる。父親の文武も、派閥を率いた宮澤喜一の面倒見の悪さもあったのかもしれないが、必ずしもポストに恵まれた政治生活とはいえない面があった。
文雄本人は傍目から見れば実力に照らして破格というほかない総理総裁に登り詰めたとはいえ、政党政治の本則に則って派閥を率い、派閥の合従連衡を通じて多数派を形成し、対抗派閥のライバルと四つに組む公選を経て到達したのではなく、ヒョータンから飛び出したコマのような姿で成り上がったのだから、経歴的には父親のような官僚育ちとは違って党人派と呼ばれてもいいはずなのに、その政党観は偏光レンズを通して見た、いかにも偏向マスコミの描く像に近いように思われる。そうだとすれば、これは問題ではないか。
(月刊『時評』2024年4月号掲載)