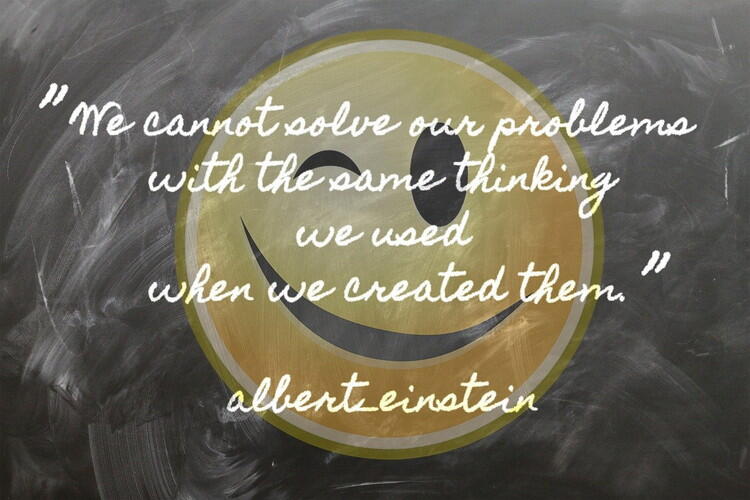
2025/03/03

今年3月末で、産経新聞大阪本社を皮切りに新聞記者生活をスタートしてから満70年となった。この間、新聞社勤務からフリー、そして現在に至るまで、数多くの先輩、上司、そして同志的知友の導きや助力を得てきた。今回はその中で特に、故人5人の先輩・上司・知友を、深い謝意とともに追想したい。
切れ目なしの〝人事異動〟
筆者が産業経済新聞大阪本社編集局社会部で新聞記者の初歩的訓練を受け始めたのは、1953年4月1日である。その日からこの3月末で満70年が過ぎた。
70年というが新聞社在職は16年余だ。6年余を大阪で社会部・政治部に勤務し、東京本社に転じて政治部記者、のち論説委員・朝刊一面コラムニストを兼ねたが、論説委員専任になって間もなく東京在勤10年を区切りに69年8月に辞職、フリーになった。
とはいえ翌9月から系列局の文化放送で、日曜を除く週6日の午後のニュースを2人で担当する一方に起用された。加えて大きな政治的・社会的事件が起きたとき、夕方のメイン・ニュースで専任コメンテーターを務めるほか、政局変動や大事件・大事故が突発するたびに特設される番組を9年間担当した。
引き続き土曜日のラジオを終え日曜を挟む翌週の月曜日から、という切れ目なしの〝人事異動〟で、同系列のフジテレビで、1年間は夕方30分の定時ニュースのキャスターを務めた。しかしこの時間帯はフリーとしての講演活動や雑誌・団体などの座談会・討論会出席に致命的に影響する。そこで勝手をいって深夜15分の定時ニュース担当に移して貰い7年半、都合8年半、系列電波としては合計17年半、フジ・サンケイ・グループ通算では満34年、サラリーマン生活でも定年を突き抜けるほどの長い歳月を務めあげた。
短くても20年超の連載4本
それでも70年の半分にはやや足りない。いまや完全フリーで執筆・講演活動をした期間のほうが長くなった。日程の組み方にもよるが、長旅を伴う九州や東北の巡回講演は体力的にもきつくなり、講演活動は75歳を区切りに依頼があっても辞退するようにし、執筆一本に絞って今日に至っているが、有り難いことにいまも4本の、いずれも短くてもすでに20年を越えた長期連載を抱えている。
その筆頭が1961年以来、社側で見れば創業2年を終えたばかりのころから62年間、時にタイトルを変えながら欠かさず続けてきた本誌『時評』の連載だ。残り少ないこれからの期間も場を与えられ書く力が残っていれば書き続けるつもりだが、どうなるか。
今年が筆者にとって区切りの年だったと同様に、岸田首相の年頭恒例の国会の施政方針演説によれば、日本にとって1868年の明治維新から1945年の敗戦までの「大日本帝国」時代が77年。その後の「日本国」時代が敗戦を起点に2022年で77年。2023からは近代国家・日本の3度目の大転換期に入ったそうだ。この時代区分に検討・議論の余地がないわけではないが、一応これに従うと、筆者は第1期最後の14年9か月と第2期のまるまる77年を体験し、現に第3期の門口に立っていることになる。
合計92年余のうちの満70年をジャーナリズムの世界で現役として活動してきたわけで、この長い道程の途上で数多くの先輩、上司、そして同志的知友の導きや助力を得てきたことは、改めていうまでもない。いまや故人が大半だが、無数の恩人から絞りに絞っていずれもいまは亡き5人の先輩・上司・知友を、深い謝意とともに追想したい。
〝乙幹〟の曹長、瀬川保先輩
まず瀬川保先輩。大阪・産経で見習生として社会部に配属されたときの遊軍キャップで新人訓練の責任者だった。明治大学を出てすぐ兵役につき、大学卒業者に多い将校養成コースの甲種幹部候補生でなく、幹部下士官養成コースの乙種幹部候補生〝乙幹〟を志願、陸軍曹長として北から南まで長期にわたって大陸戦線を転戦。敗戦で復員し産経と一体関係の大阪新聞社会部で新聞記者になった。
補足説明が必要だろうが、元帥・大将に始まるプロ集団の将校の中でのシロウトあがりの最下級の少尉と、徴兵された兵士を訓練・指揮し管理・監督する下士官の最上位の曹長と、どちらのコースを選ぶか。牛後を選ぶか鶏口をとるかの選択だが、後者は軍隊をよく識る、そして旧日本陸軍の価値観に対して批判的な考えの大卒者に多かった。次に述べる吉村克巳先輩も乙幹の曹長だった。
筆者が入社した1953年はまだ敗戦下の用紙不足を引きずっており、新聞は朝刊か夕刊かの一方しか発行できない決まりだった。東京で『朝日』『毎日』『読売』は朝刊紙、夕刊は明治からの〝軟派紙〟『都新聞』を継ぐ『東京新聞』が中心。大阪は朝・毎と『産経』が朝刊紙で『読売』はまだ進出しておらず、夕刊は『大阪新聞』が断トツだった。
『産経』と『大阪』は同じ経営者で事実上一体関係にある。編集も販売も一体だ。つまり当時の『産経』は実態として日本唯一の朝夕刊セット紙だった。記者の名刺には、大阪新聞記者・産業経済新聞記者、あるいはその逆の並びで印刷してある。朝・毎は夕刊がないから昼頃に記者クラブに出てくるが、駅売りだけで毎日60万部を売る。社会面が命の夕刊紙『大阪新聞』をつくる当方は、そうはいかない。全国をカバーしなければならない共同通信やNHKの記者と同様『大阪新聞』の記事を書くため朝から出勤する。共同やNHKは深夜配信も終夜放送もない時代だから早仕舞する。こちらは朝・毎と真っ向勝負の『産経』のため払暁まで働かなければならない。そうした厳しい条件の新人記者教育に、激戦の修羅場で新兵を教育・訓練し、時に実戦を指揮した瀬川デスクほどの適任者は滅多にいない。
〝豊作〟の期にみる指導力
当時の産経本社は、編集局の新入社員はいったん社会部に集め、50日間は休日なしで朝9時から夜9時までの12時間の社内研修。週1日は泊まり勤務で、泊まり明けだけ夕刻5時の退社が許された。社内研修が終われば先輩記者の後について府庁・警察本部・所轄署などを数か月刻みで回って実地体験し、1年後に次の新入社員が社内研修を終えて現場に出るころ一本立ちする仕組みだ。
瀬川先輩は、まず新聞記者の基礎基本の心構えを教え、次にハガキ大の用紙に1行5字3行つまり当時の組み方で紙面1行分の15字で原稿を書くこと、つまり枚数イコール行数になる書き方を叩き込み、先輩記者が出先から電話送稿してくる原稿の書き取りや、与えられたデータに基づきベタ記事を書く練習など、記者のイロハから次第に訓練レベルをあげていった。週1回の泊まり勤務の早い時間帯には、自身の経験に基づく異色の取材テクニック、刑事の家に夜回り取材する際の気配りの仕方など、具体的な秘訣も授けた。
編集採用の同期生は社として空前絶後の25人いたが、この中から産経新聞社長・同大阪駐在副社長・大阪新聞社長・サンケイ出版社長、さらに評論活動や作家として自立してそれなりに世間に通用した存在が、筆者を含めて少なくとも片手の指を越える数はいる。それだけ〝豊作〟の期は産経に限らず他社にもないだろう。この一点だけでも瀬川先輩の指導力の高さは歴然としている。
唯一止めるのは産経の社歌
産経の経営主体が変わって財界が派遣した水野成夫になったころ、司馬遼太郎こと文化部の福田定一記者が、忍者ものという特異分野で中央文壇にデビューした。終生作家気質を持っていた水野は、司馬に当時の新聞最大の目玉だった連載小説執筆を依頼し、その仕切り役として瀬川先輩を文化部次長にした。
しかし財界人の水野が知らない、関西には関西の文壇事情がある。大衆文学分野では織田作之助を筆頭とする大阪土着派と、シナ事変時代の『朝日』に連載されて映画や歌謡曲にもなった「新雪」の藤沢桓夫が中心の阪神間のプチブル感覚のグループが両立する観があるし、より純文学的なグループもいくつかある。京都の地方紙から『産経』に移り、いきなり中央デビューした司馬と、地元文壇との交流が長く自身が純文学派で同人誌を主宰していた瀬川先輩の組み合わせはまずい。
そうした面も作用したか、筆者が東京政治部に転じたころ、瀬川先輩は退社して学生時代から師事していた、戦前活躍したアジア主義の思想家が東京で設けていたアジアからの留学寮の舎監および日本生活の指導役になった。この思想家の実弟は社会党左派の有力代議士で、筆者は彼と交流があった。このころは瀬川先輩ともしばしば会って世間話をし、数々の教えを受けた。先輩はその後、大阪に帰りシニセ女子大の教授になったが、この時代には一度ゆっくり会食しただけだった。
いま瀬川先輩の存在を唯一産経に止めるのは、歌詞の社内公募で選ばれた社歌だ。
一本の このエンピツに心あり
人の世の 正義と自由守るべく
我ら集う サンケイ サンケイ
サンケイの旗に われら集う
という古関裕而作曲の社歌は大阪本社はまだしも東京本社では完全に無視されてきた。筆者は政治部の飲み会で歌を強要されると必ずこれを歌って場をシラケさせたものだ。しかし瀬川門下が社長になってから、年頭恒例の社員総会で斉唱する慣例になったという。
他社も恐れた〝吉村軍団〟
部会で歌うときに、瀬川の詩だ、といつも手拍子を打ってくれた吉村克巳先輩は、マーシャル群島の孤島で20人ほどの部下とともに、サイパンや硫黄島爆撃に飛ぶ敵機を見あげながら自給自足で生き延び敗戦を迎えた。日米開戦の日に、明日からアメリカ映画は見られなくなる、と都内の洋画館を駆けめぐった慶応義塾大学生は、日本が馬鹿な戦争を始めたのは軍人も悪いが新聞がダラシなかったからだ、と思い復員した足で福沢諭吉ゆかりの時事新報社に赴いて入社、板倉卓造、伊藤正徳ら新聞史に残る大幹部の薫陶を受けた。
最初は時事だったという筆者の同期生がいるから、敗戦後復刊した時事新報は50年代半ばに産経と経営統合したようで、東京本社は一時『産経時事』の題号だった。筆者が転勤した〝60年安保〟前夜はすでに『産経新聞』になっていて、吉村先輩は政治部次長で出先を統括していた。安保騒動が終わって同郷でブレーン的存在もしていた池田勇人内閣が成立して間もなく、内勤デスクからすぐ政治部長になり、独特の采配で他社も〝最強〟と恐れた〝吉村軍団〟を築いた。
吉サン、と長く面と向かっても呼んでいたが、先輩の手法は部下の能力・性格・経歴、さらに相手との相性などを考慮して、日常業務とは別に個別に担当する政党・派閥・実力政治家を決め、自由に泳がせ食い込ませて、集めた深く生々しい情報を部会に持ち寄らせて、全員で議論し総合判断するやり方だ。正規の部会だけでなく、給料受け取りや取材費の清算手続きなどで出先から上がってくるデスクでも、朝刊紙面作成のための回り持ちの深夜勤務のときでも、毎夜の飲み屋でも、仲間内での議論を奨励した。政治報道の最大の任務は読者に的確な見通しを伝えることだといい、部下への口癖は〝結論はどうだ〟。常に大局観を持てと説き、判断根拠を明確に示すよう求めた。と同時に、ものを書くときはすべてを書き尽くさず含みを残せ、結論を示しても足の指一本だけは土俵の中に残しておけ、というのが口癖だった。
デスクあるいは部長と部員、編集局次長からフジテレビに転じ報道局長・報道担当専務になってからは担当のトップと出演者、サンケイ出版社長となってからは版元と著作者。没後の追悼録で「上司と部下というより親分子分の関係で30年」と書いた通りだった。吉サンには政治・政治的現象・政治家の見方を教わり、政治家・派閥・政党にジャーナリストとして付き合う際の間合いの取り方、身のこなし方なども、徹底的に仕込まれた。筆者の70年の多くの部分はそのお陰だ。
世間と異なる両先輩の司馬観
産経OBの代表的存在といえば多くは司馬を挙げるが、両先輩は違った。もともと文学青年で司馬の仕切り役兼司馬夫人の上司の瀬川先輩は、ヤツは商売人じゃ、と切って捨てていた。吉サンにはこういうことがあった。追悼録にも書いたが、1964年初夏の、3選を賭けた池田勇人に佐藤栄作が挑戦して金権選挙と騒がれた、〝吉田学校優等生〟の仲間割れの自民党総裁のとき、どうせゴマスリ常習の社会部長の発案だろうが、連載小説に登場させたばかりの水野御大ごひいきの司馬に党大会の観戦記を書かせて一面に乗せよう、という案が〝上〟から降りてきた。政治部長の吉サンは筆者を呼び、キミ、大阪時代から福田(司馬の本名)を知ってるんだろ、ヤツに総裁選のルポを書かせるんだってさ。どうせなにも知らんだろうから案内してやってくれ、と命じたもんだ。
政策論争を中心に総裁選の現場で縷々説明したが、できあがった原稿は週刊誌あたりでネタを拾った、カネの話だけの下劣さで、吉サンは一読して、下らん、と激怒、政治面の水準に達していないと社会部に突き返した。結局掲載したかどうかは記憶にないが、追悼録が出てから、キミのあの原稿は実によかった、という別の先輩の手紙が届き、司馬はよほど嫌われていたんだな、と思ったもんだ。
文化放送ゆかりの友田氏
友田信氏はもともとは講談社出身の文化放送社長で、水野体制になって産経副社長を兼ねた。論説委員会は役員直属だからたまに論説委員会に世間話に現れ、講談者が発行する月刊・週刊誌に執筆することが多くなっていた筆者が相手をするようになった。産経を退社した翌月から、わざわざ枠を新設して産経の給料以上の条件で文化放送の仕事をつくってくれたのは、その結果としか思えない。
文化放送が設立したが持ちこたえ切れなくなってフジテレビに託した日本フィルハーモニーの一部楽員が、〝造反有理〟の毛沢東・中国の流行かぶれで労組をつくり、こともあろうに暮れの〝第九〟公演で満員の客席を無視してストライキと称して演奏を放棄し、騒ぎになった。懇意な楽員に、なんとかならんか、と頼まれた筆者は、古い知り合いの元宝塚交響楽団の指揮者で共産党の須藤五郎参院議員に電話し同様に、なんとかならんか、と演奏会場に急行して貰ったが、あいつらトロツキストや、説得したがどうにもならんわ、と返事してきた。
スト反対派の楽員は常任指揮者小澤征爾を担いで分離独立を図った。ちょうどサンフランシスコ響からボストン響に変わる時期だった在米の小澤と、楽員や山本直純らと国際電話で協議したり、文化庁と折衝したり、側面からなにかと支援したものだ。友田氏は元日本フィル・オーナーとしてこの実績も多としてくれていたようで、前述の文化放送からフジテレビに転じたときは、吉サンの事前の根回しもあったに違いないが即快諾してくれた。
一面コラムコンペを開いた土屋氏
土屋清氏はもともと『朝日』の経済記者・論説委員時代から論客として高名だったが、〝60年安保〟以降の社の左翼路線にあきたらず、水野の説得で『産経』に移り、編集総長の肩書で編集・論説を総覧した。
最初の編集各部を回った紙面改革のための意見聴取の場で筆者は、当時新聞の顔ともいうべき一面コラムの執筆者が、朝刊は評論家の室伏高信、夕刊は東大仏文教授の渡部一夫であるのは社として恥だと述べ、われわれでも執筆はできるはずだと訴えた。これに対し、前述の司馬の自民党総裁選ルポを提案した社会部長などは、あれは水野社長の意志で執筆をお願いしているのだ、お前らに代わりが務まるわけがない、馬鹿なことをいうと逆鱗に触れてクビが飛ぶぞ、といったものだ。
しかし土屋氏は筆者の提案を受け入れ、各部長が推薦する若手記者50人にI週間分7本のコラム原稿を提出させるコンペを開き、東京・大阪(夕刊用)で10人を採用し、分担で実際にコラムを書かせるようにした。筆者は吉サンの推薦でコンペに参加してパス、10人の一部が海外特派員に出たり、辞退したりする中で執筆陣に入り、政治部と兼務で論説委員になった。その後兼務が外れて論説専任になり、朝刊一面コラムのほかに政治・社会保障担当として社説も書いた。
筆者の退社は、水野の退陣に殉じる形で土屋氏が辞任・退社したあと、とかくのいきさつがあった反土屋の頭目でもある社会部長が編集局長になり、コンペに落選して欠員補充の形で夕刊コラムのピンチヒッターをしていた部下の熱望を汲んで朝刊一面コラム担当に起用し、筆者を特任編集委員にして週1回1ページの企画を自由に執筆させる、という情実人事を突然発令したのに対する抵抗だった。この異様な人事には、社内で問題視する向きも少なくなかったが、筆者は、論説委員は役員直属で編集局長の人事権は及ばない、と抗議して辞表を叩きつけたわけだ。
もっとも30代で新聞記者として最高位の論説委員会に入った筆者は、時機を見て独立するつもりだった。実際、社外執筆を増やして筆一本で立つ態勢の整備を進めていた。『朝日』時代から社外執筆や外部講演が抜群に多かった土屋総長は、〝他流試合〟で通用しないような記者では話にならないと公言して、社によっては社員規則で禁止事項にしている社外執筆を、むしろ奨励していた。
講演依頼増加の背景に
1955年に〝保守合同〟が成立した時、自由党総裁の吉田茂が民主党総裁の鳩山一郎と同席はできないとして自民党に入らず、無所属になったのに佐藤栄作が殉じて、無所属に止まったことがある。その佐藤に側近の橋本登美三郎が殉じ、3人が無所属に盤踞した時期が続いた。筆者が退社当時、土屋総長が水野成夫社長に殉ずるならだれかが総長に殉じてもおかしくはなかろう、と冗談でいったのを、総長はどうも本気で気にしたらしい。
独立後すぐ畑違いの経済団体や大企業からの講演依頼が増えた。先方に聞いたわけではないが、どうも土屋氏が、だれかいい講演者はいませんか、と自分の講演後に主宰者から問われて、筆者の名をあげていたのではないか、という感触がある。筆者は生涯に3500回の講演回数を記録したが、大蔵省の財政制度等審議会という重要な審議会の委員に入れ替わりに起用され、正委員2期8年の〝相場〟に加えて特別委員・専門委員などで25年近く関与したこととともに、土屋氏の推輓が働いただろう。『産経』での社員コラムニスト登用に始まる恩義は、忘れられない。
米盛創業社長と初対面の月から
そして米盛幹雄『時評』創業社長。この3月10日が急逝から10周忌だが、1961年初夏からに始まる彼との長い交流については、本誌2013年5月号所載の追悼文で述べた通りだ。初対面の月から、タイトルを変えながら『時評』への執筆は欠かさず続けてきたし、外野席からの気楽な意見ながらも時には経営面の相談にも乗り、実力を見込んだ他紙・他局のヴェテラン記者を常連筆者・ブレーンとして紹介したりもした。
半世紀を越える歳月、さまざまな経済社会の変動を乗り越えて、時評社が「中央官庁や公共企業体・民間の基幹企業、地方自治体と地方公共事業を、縦の関係ではなく横の連携で捉えて組織化し、国家社会の発展につなげる」、「世間的には必ずしも誌名が広く知られていなくても、発行部数がそう多くなくても、的確な情報の宝庫であることをクロウトの読者から評価される、知る人ぞ知る存在」(前記追悼文)」として、嗣子の康正社長のもと、基本路線を貫徹していささかの姿勢の緩みも見せない堅実・重厚な誌面を読者に提供し続けていることは、一瞬で消え去り忘れられる軽薄な〝デジタル時代〟に出版・雑誌が主体の活字文化が沈没しかねないと喧伝されている折から、偉業というほかない。
物書きは書く場あっての物書きだ。場がなくなれば書かなくなり、それが長引けばやがて書けなくなる。60年余にわたって父子2代で自由に書く場を与え続けられた恩義は絶大だ。深く感謝する所以である。
補足だが、脇タイトルの句は旧制一高寮歌「ああ玉杯に花享けて」の第3節だ。「花咲き 花は移ろひて 露置き 露の干るがごと 星霜移り人は去り」と続く。今後は数少ない〝戦後77年〟完走世代の〝露〟の一滴として、書き続けたいと念じている。
(月刊『時評』2023年4月号掲載)