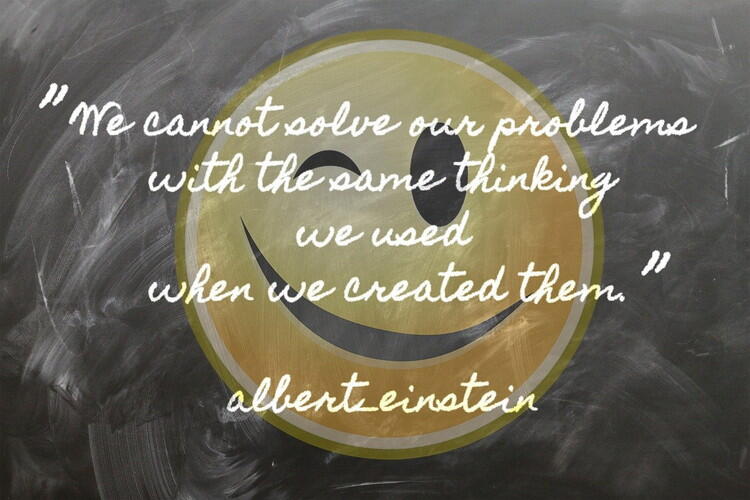
2025/03/03

コロナの流行に覆われた過去3年間を振り返ると、ビジネス、教育や医療・看護の現場などで、従来と大きく異なる様相が際立った。また生死にかかわる問題と領域を接する宗教問題も異様な方向で社会をにぎわせた。流行4年目に突入した現在、メディアでは検証されていない各種論点を、斜めの観点から整理してみたい。
過去の相場に比べて異様な長さ
新年に入り、ひとつきが過ぎた時点で、日本の新型コロナの流行は満3年を超え、4年目に入った。香港から日本に向かうクルーズ船内で感染者が発生し、そのまま入港して横浜沖に投錨・停泊したのが始まりだったが、この呼吸器感染症のパンデミック=世界規模の大流行は、発現地とされる中国・武漢周辺では、前年の2019年初秋には起きていたという。それならなんと、今年で足掛け5年目に入ったことになる。
流行初期に、筆者は手元の年表・辞典、疫病に関するいくつかの大衆書などで、ほぼ100年前の〝スペイン風邪〟を中心に、中世のペストに始まる多くの大流行病に関する初歩的な知識を確認した。その一部は当連載でも触れたが、この種の疫病は世界規模で見て足掛け3年、国別では満2年以内、そのうち最流行期というか、猖獗を極めた期間は長くても1年に満たないのが〝相場〟だった、と記憶している。それならコロナ禍は、全般的に見れば少なくとも〝スペイン風邪〟やコレラやペストなどと較べて、致死率など深刻な様相はそれほど強くないとしても、異様な長さで続いているわけだ。
しかもこの期に及んで、世界を一巡して二巡目に入ったのでもなかろうが、発現国・中国では、いままで習近平政権が誇示してきた〝ゼロ・コロナ〟など、どこへやら。激しい流行が表面化して、各地の火葬場には霊柩車の大行列が絶えないと伝えられ、その超渋滞の姿が情報統制のきつい当の共産党独裁中国はいざ知らず、テレビ映像で容赦なく写し出されて、世界中に流れている。
高い共同体意識と各種付帯要素
新型コロナが正体不明、しかも感染力が極めて強く、病毒性も侮れない深刻な伝染病だとして、多くの国が公衆衛生上の見地から人と人との接触を厳しく制約してきたことは、改めていうまでもない。〝家元〟の中国、欧米先進国、さらにアジア・アフリカの一部の国も、自由民主主義国か、権威主義的独裁国かの区別なく、ごく普通の軍事法制・緊急事態対処法制を持つ国なら当然の対応として、感染者が出た地域一帯の外出禁止から、都市全体の封鎖までを実施してきた。しかし敗戦後に占領軍に押し付けられた異様な憲法体系のもと、そうした法制が欠落したまま漫然と70年余を送った日本には、国民に対して強制力を伴う緊急措置を取る権限を政府に与える法的根拠が存在しない。そこで専ら〝お願い〟ベースで国民に行動自粛を求めてきた。
もともと日本・日本人の社会は、全体として公衆衛生の水準が抜群に高い〝神州清潔の民〟の国という定評がある。筆者は一部偏向新聞やその同調者が批判がましく唱える、日本人は極めて同調性が高く、常に他人の目を気にして行動し、権威・権力の意向を過度に忖度して指示された方向に集団的に流れる、という見方を採るものではない。しかし最近は、乱れてきたと嘆く声が一部では高いが、他国に較べればまだまだ社会を律する共同体意識が高いことも、明らかな事実である。それが日本の患者発生数・死亡者数の抑止に、世界レベルで出色の成果を上げる要因になったのは疑う余地がない。
それに加えて、流行初期に著名な芸能人の感染死が相次いだのが作用し、コロナの脅威がより強烈に意識されたこと。法に基づく強制でなく、政府からの〝お願い〟だったために、かえって警戒態勢から緩和への路線転換が明確でなく、転換しても緩和が徹底しにくかったこと。こうした要因で、人と人との接触や社会活動全般の抑制が欧米先進国に較べて、だらだら長く続いた点も否定できまい。
日常を送る老人ゆえの視点
疫病が広がる過程で、有名・無名の多くの〝専門家〟が、群盲象を撫でる体でさまざまな解説・予測、というより不確か極まる感想やご託宣を並べ、テレビがそれを煽った。中には、この勢いでは1カ月後には全国で80万人が死ぬ、という説も流れ、世間の不安をことさらに強めていたが、さすがにひどい誇張で、この説に同調していた〝学者〟やコメンテーターの姿は、最近は見かけない。
この疫病の病原体の変異の激しさや病態の変容など、まだ未解明の問題点が山積している医学的な領域については、筆者は議論に加わる能力などいっさい持ち合わせない、一介の門外漢に過ぎない。史上類を見ない異様に長期化した摩訶不思議な疫病の中で、90歳を超えた老人としての日常生活を送っているだけだが、それでも、それだからこそ、見えてくる状況も少なくない。
コロナ禍の困難の中で経済を回転させ、社会機能を維持しようと苦闘している現役世代の心情と苦労は察するに余りあるが、彼らが気づかないまま、見逃しがちな世相のアヤ。あるいは直接の当事者は痛感しているが、新聞・テレビなどは不注意か、取材の不行き届き、というより、むしろあえて直視を避けているとしか思えない、従来とはかなり違った風景や状況があるように思われる。そこで今回は、こうした面でヒマな老人だからこそ耳目に入りやすいポイントを、斜めからの視線で捉えた、いくつかの事柄に触れたい。
リモートの旧・新を問わず
まずコロナ禍でビジネス社会から教育界全体まで、急速に進んだリモート化だ。その利点と不具合の議論はそれぞれの状況に応じて各所で盛んだが、思えば老人の世界は昔からリモートで動いていた。ただその手段が、昔はもっぱら手紙か葉書、最近までは加入電話か携帯電話の声、それが最近になってやっと携帯メールか、気の若い一部の老人の間ではSNSが日常化しはじめた状態だったのだ。
古い国民歌謡のように、「むかしの仲間も遠く去れば また日ごろ顔あはせねば 知らぬ昔と変りなきはかなさよ」(木下杢太郎)だ。学友はもちろん、古い職場での付き合いも、親族間の行き来さえも、途絶えがちになり、ごくごく限られた範囲で旧式・新式のリモートによって細々と消息を伝え合うのを、数少ない楽しみとしているのが、老人の一般的な暮らし方だった。
その若かりし昔とつながる細い糸が、コロナ禍でぷっつり切れた。少なくともかつてのように簡単には通じなくなった。電話してみても、ただいま出ることができません、という自動音声の応答が返ってくることが多い。老人を狙うオレオレ詐欺などを撃退するために、いつもこうした仕掛けを設定しておいて、掛かってきた相手の番号をかねて登録ずみの画面で確認した上で返電する、というのが、当今は多くの老人家庭で習慣化していて、当家もそうしている。しかしそれでも反射的に、アイツはどうしているのか、ひょっとして入院でもしているのではないか、と思うことが多い。そして実際にそうなっているケースが、決して少なくないのだ。
うんと対象者が減った、季節の贈答を重ねてきた相手に宅配便を届ける配送会社のドライバーから、3回ポストに不在通知を入れましたが応答がありません、どうしたらいいでしょうか、と連絡が入ってくることもある。実は温泉地の別荘にいっていた、というヤツもいたが、暮れのうちに応答がなく、気にしていたら年明けになって、実は孤独死していた、と知らせがきた例が、昨年あった。夫人に先立たれ、子供もなく、80代後半になってはいたが、まだ元気でときどき拙宅を訪ねてくれた数少ない友人の一人だった。
筆者には、年末年始原稿の書き溜めに追いまくられていた新聞記者時代から、年賀状を出す習慣がない。いただいた相手には電話で返礼と新年の挨拶をすることにしていたのだが、こまめに年賀状が来ていた知友たちの中にも、70歳とか75歳とかを区切りに、今回を最後とさせていただきます、という向きが多かった。手間も費用も考えれば当然の判断だが、そうなると恒例化していた年賀電話のきっかけも、掴みにくくなる。
機能させるのは濃密な接触
昔ふうを続けるか、デジタルを駆使するのか、いずれにしてもリモート式の交流も「互いに顔」をあわせることが日常的に行われていたからこその話で、そうした前提がなければ到底スムースに運ぶものではなかろう。それまでは濃密な接触が続いていたこと。いまもときには会っていること。少なくとも聞き慣れた声であること。こういった条件がリモートを機能させている面は、意外に認識されていないのではないか。
最新流行の執務スタイルだから、政府が本腰をいれて進めようとしているから、事務スペースの費用も通勤時間のロスも省けて合理的だから、といったことでビジネス社会のリモートが長く成り立ち、定着していくとは、到底思えない。全国どこに住んでもリモートで仕事ができるようになり、地方が活性化する、などというのは、永田町か霞が関の定住者が勝手に描いた、空想というのも上等すぎる妄想に過ぎまい。人間社会とは、文字通り人と人との間、相互関係で成り立つものであることはいうまでもない。人間同士の対話・対面の意味について、きちんと考えようともしない〝デジタル屋〟どもの非常識さ、薄っぺらさについ釣られてしまうと、将来エライ目にあうのを避け難いのではないか。
岸田政権は旧年末、「デジタル田園都市国家構想」の5か年計画を閣議決定し、年間1万人を東京圏から地方に移住させ、全国1500の地方自治体をデジタル化する、と称している。岸田が代議士のイスを受け継いだ父親・文武の親分だった大平正芳が40年以上前の1980年に提唱した、〝田園都市国家〟構想のパクリであることは明白だ。岸田はこれで吉田茂―池田勇人―大平と流れる〝保守本流〟の正統であることを誇示し、傍流とされる鳩山一郎―岸信介―福田赳夫―安倍晋太郎―安倍晋三ラインと、一線を画そうと意図したのだろう。
しかし大平の構想は、池田の〝所得倍増計画〟や盟友・田中角栄の〝日本列島改造論〟と平仄を合わせた気宇壮大なもので、臨海の重化学工業地域と後背地の農村を一体的に開発し、高度な輸出製品の生産の飛躍的拡大と高度で勤勉な労働力の確保を図り、〝農工両全〟で日本を高度経済成長させようという現実的・具体的な政策案で、実際に日本を世界2位の経済大国に押し上げる結果を残した。これと較べると岸田の構想は、〝新しい資本主義〟とやらの〝成長戦略の柱〟というフレコミだが、新聞報道などを見ている限りでは、国民にはなんのカンケイもない、単に役場の事務処理をラクにさせるだけの話で、それ以上のメリットは感じ取れない。羊頭狗肉もいいところ、というほかなかろう。
様相が一変した通院・入院
話題を変えて、いくつかの老人の暮らしの問題点にもざっと触れておくと、老人といえば通院や入院はつきものだが、コロナ禍いらい病院の様相が大きく変化した、という見方がある。感染防止のためにいろいろな措置がとられ、さまざまな制約が生じるのは当然のことだが、通い続けてきた患者にとってはそれが、いつもとやり方が違う、厄介だ、面倒くさい、と感じられる場合も少なくない。非常事態だから、原則として受忍すべきなのはやむをえないとしても、基礎疾患で定期的に通院する患者と、コロナ感染を疑って新規に訪れ〝発熱外来〟に並ぶ患者では、院内の行動でも病院側との応答でも違いが出てくる。
検査・通院だけなら多くの病院はゾーンを分けて対応したが、入院となると状況が違ってくる。流行初期の段階では入院自体、厳しい隔離対象とされるコロナ患者や陽性者・濃厚接触者などでベッドが塞がってしまい、古くからの常連でも病状が悪化した場合も容易なことでは入院できず、大騒ぎになった。
運よく入院・加療できるまでに漕ぎ着けたとしても、ウイルスを持ち込む恐れのある部外者の病棟内への立ち入りは、家族といえども一切禁止だ。よくても特別に設けられた対面スペースまで動ける患者に限って、ガラス越しに顔だけを見られる、という奇妙な〝面会方法〟が、去年の夏ごろまでの2年半ほどの間は多くの病院で行われたのではないか。
看護スタッフの権力者化
いわゆる心療内科的疾患の疑いでとりあえず入院した患者が、病棟の医局長から、診断結果によっては2年間の入院が必要になる場合もあり得る、といわれたついでに、家族がこう続けられた、という話を聞いたことがある。コロナの影響もあるが、病気の性質からも、家族との面会・電話などの通信は、全面禁止です。治療の経過は定期的に通知しますが、次に患者に会うのは退院のときになります。その前に死亡すればお知らせします。こういったというのだ。
これはさすがに特異なケースだったとしても、コロナ関連の入院患者が亡くなった場合は、よほど配慮が行き届いた病院では、顔のところだけを透明にして、家族が霊安室で顔を見届けるよう配慮したというが、多くの病院では密封した袋に入れて病院から火葬場に直行させ、遺骨になってから家族に引き渡すのが、むしろ普通だったという。
患者と家族の面会がなくなることは、患者の扱いに対する家族からのクレームがなくなることと直結している。そうなると医師はまだしも、看護スタッフの態度が豹変して、権力的に振る舞うケースが目立ったという。面会禁止は差し入れ禁止を伴うが、保健医療費で金額が決まっている入院者の病院メシの質も、エネルギー価格をはじめとする諸物価高騰も影響して、低下する一方だったそうだ。看護スタッフの権力者化には、人手不足・需要拡大・コロナ感染の危険性の反射、世間一般にも見られる極端な労働力の流動化、といった要因が絡まっているのだろうが、似たような状況は、児童の保育施設や老人の介護施設での、職員の暴行発覚の多発が俄に社会問題化した背景にも、存在するのだろう。
戦後を支えた世代の簡素な葬送
コロナ禍は、少子高齢化・経済成長の行き止まりと景気の長期停滞、それにもかかわらず安定社会の成熟・分別といった状態には辿り着いていない日本の抱える弱点を、まとめて炙り出した印象がある。なにを考えているのか、ひょっとすると日本以上に急速に膨張した経済が破裂寸前にある中国から、いまのうちに脱出しようとしている成り金どもの逃げ場所として売りつける目論見か、と疑わざるをえない新築の超高層マンションが林立する一方で、東京を筆頭とする大都市圏の周辺には、高度成長期に建てられ、どうやらやっと長期ローンを完済したと思われる、築40年前後の、住めず・貸せず・売れずの〝三ず住宅〟が、よくて高齢夫婦世帯、多くは一方が亡くなった単身生活、一部は核家族がさらに核分裂して無住の廃墟になって放置されている、というアンバランス加減が、いまの時代相を端的に示しているように思われる。
子供と同居するつもりだった家を売って老人ホームに入った友人。同様に夫人を亡くしたあと、いったんは呼び寄せ同居した娘一家との折り合いがつけにくく、別荘を売って病院付設の老人ホームに移った友人もいる。しかし彼らは、もちろん自分の長年の勤労・努力の成果とはいえ、よほど恵まれた部類に属しているわけで、敗戦日本の復興に貢献してきた世代の多くの人たちは、より厳しい老後を強いられている、といえるのだろう。
終活、という厭味な言葉が流行語化して久しいが、うまくいったのは少数の例外で、詐欺師のワナに嵌まったり、そこまではいかなくても結局のところ古物商のエジキになってたいした結果にはつながらなかった向きが、大半だったのではないか。
コロナ禍は多くの感染死者を出したが、彼らの葬送は、突然の死に至った経緯と、人の集まりが慎まれた世相を反映して、総じて極めて簡素だったように伝えられる。それとは別の次元で、しかし同様に人の集まりを忌避する流れの中で、法事とか年忌といった仏教行事も行われにくく、寺は閑散、坊主あがったり、といった状況が目立ったようだ。
新興宗教ゆえの二世・三世問題
宗教といえば、安倍晋三元首相の銃撃による暗殺犯の犯行動機に関連して浮上した、旧統一教会の問題、とりわけ信徒に対する献金のマインド・コントロールによる強要や、親が信徒で家産を献金に投げ出してしまったために苦難の道を歩まざるを得なかった〝宗教二世〟の存在が、メディアや、さらに国会をはじめ政治の場でも大きく取り上げられて、〝コロナ世相〟の中で大きな関心を集めた。
前回も触れたように、統一教会のやり方にさまざまな問題があることは明らかだが、献金というか寄付というか、喜捨というか布施というか、賽銭というか奉納というか、いずれにせよあらゆる宗教団体が、信者・信徒が納める資金によって支えられていることは、否定すべくもない事実だろう。
そしてまた、あらゆる宗教が自分たちの教義を唯一無二の絶対的な真理と位置付け、他のあらゆる思想・信条を、相手によって多少の程度の差はつけるとしても、断固否定・否認していることも、明らかな事実だ。自然信仰や伝説に由来する祖先信仰的宗教色を帯びる民族慣習は別として、あらゆる近代宗教はこれも強弱の差はあるとしても、例外なくマインド・コントロールの上に成立しているといっても過言ではない。
〝宗教二世〟にしても、第2次大戦後の朝鮮戦争直後の韓国で文鮮明が始めた統一教会だから〝二世〟が問題になるが、昭和戦前の日本で牧口常三郎らが始めた創価学会はすでに三世の時代に入っている。〝一体不二〟の関係にある、とかつては自ら誇示してきた公明党の国会議員には、創価学会の池田大作名誉会長を創設者と仰ぐ、創価大学出身議員も少なくない。新興宗教だからこそ二世・三世が話題になるのであって、伝統宗教の場合は三十世も五十世も、百世だって、いないとは限るまい。現にプーチン・ロシアのウクライナ侵略で揺れるヨーロッパで微妙な位置にあるドイツでは、ハインリヒ十三世と自称する老人が、俄仕立てのクーデタ容疑で仲間とともに逮捕されたという笑えない話もあった。
際立った、宗教の存在感の希薄さ
前回論じたように、献金といいマインド・コントロールといい、〝二世〟が示す家族間の摩擦といい、憲法が定める信教・結社・思想・言論の自由や、私有財産の所有者の自由処分権の保障の問題、さらに〝法は家庭に入らず〟という近代法の原則、法は基本的に特定の対象ではなく普遍的にその字句に即して運用されるという基本に照らしても、徹底的に論議すべき点が山積していたはずだ。
しかしメディアがスクラムを組んで遵法マインドなど蹴散らし、いままでは政府ともども見て見ぬふりをしてきた特殊な〝宗教悪〟の糾弾に走って、センセーショナルに伝えた。日ごろ何事につけケンポー擁護を振り回す野党も、選挙目当てのポピュリズム的策略に目がくらみ、憲法が定めるさまざまな国民の基本的な権利との関係を顧慮する最低限の見識もなく、取り締まりの姿勢が緩いと政府を攻撃し続けた。
そうした中で、最低限の線はなんとか守ったとはいえ、本来なら刑事・民事の既存法規できちんと対処できるはずの問題を、特別立法で対応することにした岸田政権の意気地なさも、情けないというべきだろう。
大衆書の範囲内の知識でいうと、中世のペスト禍をはじめ悪疫の大流行は、それまで社会の主流を制していた宗教の存立基盤を揺るがし、宗教の改革機運を高め、その実現につながった、と記述されていることが多い。
しかしコロナ禍の日本では、旧統一教会騒動を例外に少なくとも既成宗教の領域では、これまで信者だけでなく多数の人も加わって盛大に行われてきた宗教行事が、感染防止の観点からほぼ休止されたのをはじめ、葬儀の簡素化を含めて宗教の空白化・存在感の薄さが際立ったように見える。宗教の存在意義の観点は、〝コロナの時代〟を考える上で、こんご一つの論点になるのではないか。
(月刊『時評』2023年3月号掲載)