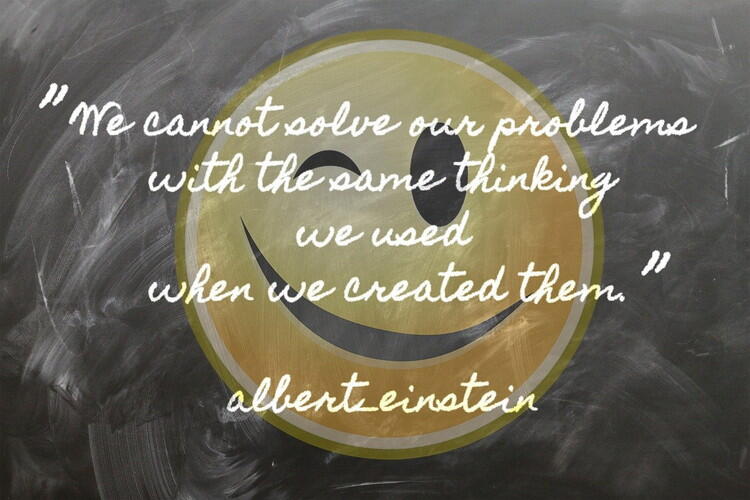
2025/03/03

秋篠宮悠仁親王の筑波大学附属高等学校進学を、筆者は甚だ不適切だと考える。不適切の背景には、宮廷官僚の劣化や〝御学友〟の喪失など様々な問題がある。日本固有の〝天皇学〟を身に付けるには、校風の変節を経たとはいえやはり学習院がふさわしい。
不適切な〝持ち上がり〟進学
秋篠宮悠仁親王がこの3月、附属幼稚園から附属小学校、附属中学校と、いわゆる〝持ち上がり〟で12年間在籍していたお茶の水大学の附属教育機関を卒業し、筑波大学附属高等学校に進学することが決まった。お茶の水と今回と、再度の競争試験突破の経緯についてはこの際問わないが、率直にいって今回の選択は、悠仁親王にとっても皇室にとっても、日本国にとっても、不適切と思わざるを得ない。親王自らの希望だったとか、秋篠宮家も同様だったとか、風聞があるが、それは真偽を問う以前に問題の本質を逸れている。
いうまでもなく、秋篠宮家は現行皇室典範に定める皇嗣家で、悠仁親王はいずれ皇位を継承すると確定した、特別な身分と地位と権能を持つ立場にある。その反面、見方によってはいくつもの側面で一般的な意味での人権を制約される、不自由な立場でもある。
筆者はその〝いくつもの側面〟の重要な一部に、教育の問題があると考える。皇族は憲法をはじめ法律に基づき、国家がさまざまな環境を保障・整備しているが、同時に地位に応じた知見を積むこと、地位にふさわしい挙措をとることが、期待されている。加えて世界の王室・王族との社交儀礼のマナーや、そのための高い語学力、巧まざるユーモアを漂わせた会話術、相手国の歴史・習俗・宗教儀礼などへの理解なども求められる。映像の撮られ方によっては思わぬ反応を内外の世間から生みがちな高貴なVIPには、世界は一瞬の油断もできない舞台なのだ。
皇室をはじめ日本民族に固有の宗教である神道の宗家として、また宮中神事・祭事を執行する祭主として、特別の修練やその基礎になる多くの故事・由来・変遷に精通すべく、一般人には想像もつかぬ重い責任感のもとでの、深い思索と弛まぬ努力が求められよう。
日本固有の〝天皇学〟
そうした一言でいえば〝帝王学〟を超える日本固有の〝天皇学〟は、極めて高度な精神的・知的な修学の場で、だからこそ過去には東宮御所・東宮御学問所という存在があり、公卿家や華族に学識経験者を加えた〝御教育掛〟が存在した。昭和天皇の皇太子だった平成の天皇、現上皇の明仁親王までは、大日本帝国憲法のもとで完成され整備された皇室制度の道筋に沿い、幼少期に両親である天皇・皇后や兄弟姉妹である親王・内親王と切り離され、ただ一人で東宮御所に移り、宮廷官僚や〝御教育掛〟の教師・学者、日常の奉仕に当たる専従職員まで、オトナに囲まれて暮らし、学ばなければならなかった。
学校教育の場には学習院が国立、当時の呼び方では官立の一貫校で存在していたが、同じ官立でも東京帝国大学が頂点の一般教育機関が文部省管轄なのに対して、学習院は皇族の教育機関を前提とした宮内省管轄だった。
蛇足ながら、いまのメディアは宮内省を宮内庁の前身と説明するが、宮内庁は総理府の外局に過ぎない。宮内省は内閣とも総理大臣の統率・指揮とも、他の行政省庁とも一線を画す皇室の直属組織で、外国との関係調整に当たる外務省や警察を所管する内務省との人事の出入りはあるが、次官は省庁人事とは別に決められ、侍従長はじめ宮廷官僚や一般職員も、別途独自の基準で採用されていた。
都会風私学への変容
学習院は一般入学志望者も受け入れたが、まず皇族、次に皇族から「臣籍」に「降下」した元宮家の子弟。古くからの「廷臣」である公卿家や側近として皇室を守り支える「藩屏」と呼ばれる華族の子弟の教育機関だ。したがって家庭から切り離され、他人のオトナだけに囲まれて日常を送る皇太子には、普通科と呼ぶ小学校に入った直後から、学校当局や宮内省・内務省が慎重に人選に当たったのだろうが、まず皇族や「臣籍降下」組。次いで「廷臣」や「藩屏」家、そしていまふうにいえば帰国子女を含む実業家の子弟などから選定された「御学友」がいた。
彼らの一部は校舎内で皇太子の身辺にいるだけでなく、時には御所にも召集され、長じてからも電話や直接の面談で、関係が続いたという。近侍する宮廷官僚とは違う次元で、世情の情報源や私的な相談相手、場合によっては「直諌」もできる存在だったとされる。しかしそうした旧憲法下の宮廷秩序は、敗戦とそれに伴うアメリカ軍による占領支配によって大きく変化した。旧憲法に代わって占領軍が敗戦日本に押し付けた新憲法のもと、皇室を残す一方で、東宮御所や東宮御学問所は消滅していった。その一環で学習院は一般私立校と変わりない〝開かれた学校〟、必ずしも難関とはいえない教育機関になった。幼稚園・小学校からの〝持ち上がり〟をベースに、各段階で〝中途参入者〟を加え、大学は東京・山の手の好環境のキャンパスで学生数が他に較べて少なく、定年になった東京大学の教授OBをはじめ東大系の教員が多いのがウリの、都会風私学になった。
しかし腐っても鯛、由来が由来だけに、学習院の学習院たる基本的性格はいまも残っている。そもそも上皇・天皇をはじめ皇族は、秋篠宮家が中心の少数の例外を別とすれば、一貫して学習院だ。上皇は〝新憲法〟秩序のもとで皇太子である徳仁親王、すなわち今上天皇と弟宮の現秋篠宮を、平たくいえば両親のもとで生活し一つ屋根の下に暮らす家族の形を、おそらくは強い意思で築いたと察せられる。しかし皇太子が成人・成婚後に皇嗣を儲けることを当然の前提として、弟宮が一定の時点で新宮家を創設する旧憲法いらいのしきたりは、昭和天皇と秩父宮・高松宮・三笠宮、そしていまの上皇と常陸宮の例と同様に残り、早い段階で秋篠宮家が創設された。
秋篠宮家をめぐる状況の変化
兄皇太子と弟親王が成長するにつれ、皇太子には学習院での学業に加えて、皇太子としての少なからぬ〝公務〟、さらに次代の天皇に不可欠な〝課業〟が、学業と別の次元で連日のように数多く組まれたはずだ。これに較べ弟親王は、一般の学習院生とさほど変わらないキャンパスライフを送ることが可能だったと思われる。その違いがそれぞれ妃を迎えて家庭を築いたあとの姿にも、内親王への視線や教育方針にも、反映されたのだろう。
それが秋篠宮家の眞子元内親王の結婚をめぐる一連の〝騒動〟に現れた、とは多くの読者が感じるところだろうが、いま秋篠宮家や悠仁親王をめぐる状況は、大きく変わった。秋篠宮は歴代の皇太子と同列の立場にある皇嗣、悠仁親王は次代の皇嗣、さらには次々代の皇位の継承が確定的だ。そうである以上、状況変容が具体的に明らかになった、悠仁親王が中等教育課程に進む時点で、学習院への転校が実現していなければならなかった。
そうならなかったのは、敗戦憲法下で「補弼の責」に任ずる宮廷官僚が、かつての「藩屏」たちが支えていた宮内省時代と較べて、劣化したというか、フツーの官僚になってしまい、独自の使命感で皇室を支えようという視点にも意欲にも欠けていたから、と見るほかあるまい。いまの宮内庁はどう見ても三流官庁に共通する〝その日暮らし〟的な〝ことなかれ主義〟に堕しているとしか思えない。
宮内庁のトップは警察官僚から起用されるのが慣行化しているが、率直にいって彼らの〝終点ポスト〟の中で、警察庁長官や警視総監、いわゆる事務系官房副長官など、退官後も部内に長く影響力を残すエース級が座る席ではない印象が強い。ことさら〝毛並み〟が意識された人事が行われている感じも薄い。
微かな〝余韻〟も埋没し
昭和天皇が戦時、そして敗戦・占領と憲法改定による皇室体制の激変、そして占領軍指令で行われた財産税徴収を理由とする、膨大な皇室資産の根こそぎ的国庫移管。これら数々の苦難に耐え、自ら〝巡幸〟して戦災で荒廃した全国各地を訪れて国民を激励し、急速な復興に導いた背後に、幼少期からの〝御学友〟の支えがあった点は広く知られている。
かつての〝天皇学〟の余韻は、平成の天皇すなわち現在の上皇の時代までは残っていたのではないか。なんといっても幼時から東宮御所で過ごし、初等教育を旧憲法下の学習院で受け、大学まで一貫して学習院だ。幼時からの〝御学友〟もいまも存在するようだ。祖父は明治・大正時代の内務官僚で内務次官や宮内次官を歴任、父親は昭和天皇の〝御学友〟。最近亡くなった本人は元外務官僚で、侍従長として平成の天皇の在位後半を献身的に補佐した、という例がある。そうした人事の妙が微かな〝余韻〟につながったに違いない。
しかしそうした余韻は、大衆化社会状況の雑音・騒音に埋没して消え去ってしまった。皇嗣となったからには、古くから皇室に伝わる〝天皇学〟の伝授は必要要件だが、初老の秋篠宮には健康上の負担を配慮して、最重要な点に集中せざるをえまい。しかし次々代の皇室を担う悠仁親王には、遅れて始まる感を否めないとしても、最善を尽くすべきだ。それには一般的にも人間形成に決定的な意味を持つとされる、後期中等教育の時期を逸することはできないし、高校生活の段階でこそ、将来を見据えた然るべき〝御学友〟チームの編成が不可欠になる。そのためにも学習院に進むことが、絶対に必要なのではないか。
悠仁親王や秋篠宮家の考えがいかにあろうと、皇室の将来にとって、皇室を〝国民の総意〟に基づき〝国家と国民の統合の象徴〟にする日本の未来にとって、翻意を願って進むべき道を用意するのが、「補弼の責」に任ずる「君側」にある宮廷官僚に課せられた役割のはずだ。〝御意〟と平伏して引き下がったのか、〝ご無理ご尤も〟と折れたのか、それともハナからなんの疑問も感じないほど劣化していたのか、それはさておき悠仁親王の筑波大附属高校進学はあるべき選択ではない。
皇室と筑波大附属との接点は
そもそも筑波大附属高という名が出てきたとき、これはちょっとまずい、と感じなかった宮内庁の官僚・職員が、そしてマスコミがまったくいなかったのだろうか。筆者にはそこに、到底信じがたい、という感覚がある。
基本的に学習院一色の皇室で、筑波大附属高、古くは東京高等師範学校附属中学校という校名は、うちうちの存在で鷹司平通という人の母校というのが唯一の接点と思われる。鷹司家は五摂家、藤原家の後身である近衛家を筆頭とする最高位の公卿五家の三番目に位置する。当主は1890年の帝国議会開設から1947年の新憲法施行による廃院まで、代替わりによる短期間を除き、一貫して貴族院の公爵議員を務めた。平通という人は昭和天皇の内親王、つまり平成の天皇、現上皇にとって、平たくいえば姉の夫君、義兄にあたり、具体的な言及は憚るが、普通なら起きえない状況・理由の不慮の事故で亡くなった。
彼が旧制東京高等師範学校附属中学校の第50回卒業生。筆者は57回卒業だから、彼は存命ならいま数え年で100歳の見当になる。筆者は昭和12=1937年に当時の東京高等師範学校附属小学校に入り、父親の転勤で2年の3学期からは兵庫県芦屋の、6年の2学期からはやはり父親の転勤で東京市本郷の小学校に転校した。ここを卒業して昭和18=1943年に、本来なら高師附属小から無試験で行けた附属中に外部受験で入学した。
なにぶん戦時下、そして敗戦下の混乱時代だ。昭和23=1948年3月に6533の旧制の附属中を卒業するまでにも変化があった。入学早々、すべての中学校が4年制になる。それまでは4年修了で旧制高校に〝飛び級〟受験できたが基本は5年制だった。しかしその年に、戦局不利で若い兵士が必要だとして〝学徒出陣〟になり、旧制中学は4年制になって、昭和20=1945年3月には、附属中では54回と55回が同時卒業する。しかし8・15の敗戦で5年制に逆戻りして翌年は卒業ゼロ。56回は昭和22=1947年に卒業、翌年が筆者らの57回だ。
敗戦後は占領軍が強制した〝学制改革〟の嵐だ。明治いらいのヨーロッパ型の6533制をアメリカ型の6334制にしたわけで、筆者ら当事者は、入学したときには5年制の中学が4年制になり、5年制に戻って卒業したが、中等教育が3プラス3の2段階で6年になるから、後半の新制高校の3年に横滑りしろ、というのだ。新旧切り替えの特例で、1年後に廃校になる旧制の高等教育の前半の旧制高校を受験、合格すれば1年だけ在学して、翌24=1949年に新学制による4年制新制大学の入試を受けるか。旧制中学卒業後に引き続き新制高校に衣替えした出身校3年に進級し、翌24=49年に卒業して新制大学を受験するかは、生徒の選択だという。
1学年下のクラスからは全員一律で新制に横滑り移行したから、入学・卒業の期数は旧制中学も新制高校も同じ数になる。筆者は附属中学も東京高等師範学校附属高等学校も57回卒業で、旧制の第一高等学校がキャンパスはそのまま看板を掛け替えた新制東京大学教養学部に第1期生で入学。2年の課程を終え、旧制大学に相当する本郷の2年生の専門課程は文学部倫理学科に進んだ。
高師附属中の存在意義に関係
いったんは東京教育大学附属高と名乗り、いまは筑波大学附属高となった母校の、この春の卒業者はたぶん130回になるはずだ。筆者の附属小入学は85年前、附属高卒業からでも73年たつ勘定だから、そんな昔話は悠仁親王の進学とは関係ない、という読者も多いだろう。だがそんなものでもない。これは高師附属中の存在意義に関係するからだ。
旧学制下で国立の中学校はたった2校しかなかった。東京高師附属と広島高師附属だ。同様に女学校も2校、東京女高師(現お茶の水大学)と奈良女高師(現奈良女子大学)の附属だけ。他に俗に〝7年制〟といわれた、5年制の中学と3年制の旧制高校をあわせた8年を一貫校にして1年短縮し、7年で大学入試に挑戦するようにした東京高等学校と、当初は私立ですぐ校舎ぐるみ国に寄付して国立化した富山高等学校、そして前述した宮内省管轄の学習院中等部だ。
いまは旧師範学校を教育学部に変えた国立大学の附属小・中学校が多いが、旧制では小学校教員を育成する師範学校は府県立、したがってその附属小も府県立だった。中等学校の教員は高等師範か、大学の卒業者でなければならず、旧制大学の卒業者は格別の免許はいらないが、〝駅弁大学〟つまり駅弁を売る駅があるくらいの町なら国立大学がある、といわれたほど旧制師範や各種の専門学校が国立大学化してからは、国公私立を問わず教育課程の単位を取得し教員免許を得て卒業しなければ教員になれなくなった。
旧制師範・現教育学部の附属小学校は、教師になる学生の実習用の児童・生徒集団だ。私立の附属小学校は中・高・大学に続くエスカレーターの1階に相当する。これに対し高師附属は、男女とも一般大学の卒業者が少なくない旧制中学・高女の教員の中核になる幹部級教員を育てる、いわば〝士官学校〟の将校教育用だ。それもかなりタチの悪い、高師に入って威張っているイナカの秀才をヨボと呼び、教科実習で難問責めにして教壇で立往生させ、教師職業の厳しさを骨身に徹しさせる役割を受け持つ、特定教科だけはそこらの大学生よりよほど高い学力の生徒を、教師が日頃から目をかけて育成する、一般のエリート教育とは一味違った一点突破型の能力を磨かせる、かなり特異な校風だった。
さらに高師附属にはもう一つ、別の役割がある。文部省の直轄校として、小中学校の教科内容・教科書・教師用の学習指導要領を改定するときの実験台、モルモットになることだ。実験が成果につながることもあるが失敗するときもある。いったん採用して失敗した場合はまだしも、試してみたら失敗とわかって即やめた、という場合は、附属の生徒だけリスクを負うわけだ。ヨボいじめはいざ知らず、モルモットは存在意義の核心だから、いまの筑波大附属も続いているのではないか。
尤もいまは、せいぜい〝ゆとり教育〟の採用と見直しとか、大学共通テストに対応するための教科内容の微調整とかで、生徒の負担も軽いだろうが、筆者たちは大変だった。なにしろ入学早々、5年制が4年制になる。なにを残して、なにを割愛するか、その試行錯誤が、翌年からの全面実施を目指し、附属で1年先にテストされたのだ。5年制への復帰は元に戻すだけだから簡単だったろうが、6533の旧制教育から6334の新制教育に切り替えのときは、いろいろと混乱した。
筆者はこの段階で旧制中学5年からの旧制高校入りはどうせ1年だけの話だと見切りをつけ、新制高校のモルモットに徹したから、翌年の新制東大の入試は楽だった。逆に白線帽とマントの旧制高校生活に憧れ、首尾よく合格したが翌年は新制大学入試に失敗、浪人して後輩になってしまった級友もいた。
あちこちで作られる〝附属会〟
マスコミは筑波大附属高の偏差値が高いとか、超難関校だとかというが、そんなにいい学校だとは思わない。昔から、できの悪いのに限って群れたがり、あちこちで〝附属会〟なるものを作りたがる。笑わせるのは夏に軽井沢に出没する〝軽井沢附属会〟なるものがあり、暑さを逃れて老来小部屋に籠もる筆者夫婦をスーパーあたりで見かけたのだろう、何回か誘いがきた。当然無視したが、OGはいざ知らず、別荘持ちのマトモなOBが入会しているという話は聞いたことがない。
附属小からの〝持ち上がり〟は、どこのフゾクも同様だろうが、上と下に見事に成績がわかれる。オトナになっても群れる〝附属オンチ〟は圧倒的に下位グループに多い。そこで意外にも中学から入ってきたのが目立つ。ハキダメのツルづらをしたヤクニンや会社持ちが混じることもあるが、ハキダメに集まるのはつまるところゴミのたぐいだろう。
悠仁親王が筑波大附属高に入ったのは、3年後の東大受験を目ざすからだ、という風説があるが、そもそも東京大学は、役人であれ学者であれ、技術者であれ、報道・言論に携わるものであれ、天職、使命職、ドイツ語でいうベルーフを求め、築こうとする若者が学ぶところ、と筆者は考えている。
悠仁親王、そして皇室には、はっきりしたベルーフが憲法、皇室典範によって定められている。悠仁親王は、その大道を、脇道に逸れるのではなく、ベルーフのより高みを目指して、歩まれるべきであって、学業の時間以外はひたすら〝天皇学〟に徹し、なるべく幅広く〝御学友〟の輪をつくっておくことが、不可欠だろう。
そのためには、皇室とのかかわりも深く、上皇、今上天皇、父君の秋篠宮をはじめ、多くの皇族が学び、単に教育環境だけでなく、警護や周辺への目配り・気配りにも積年のノウハウを蓄積している学習院への進学が、当然のこととしてふさわしい、と筆者は確信する。古いOBとしていえぱ、筑波大附属と呼ばれるようになってからは、伝統的気風も薄れ、左傾教員の噂も聞こえてこないでもない〝あそこ〟は、到底お勧めできない。
(月刊『時評』2022年5月号掲載)