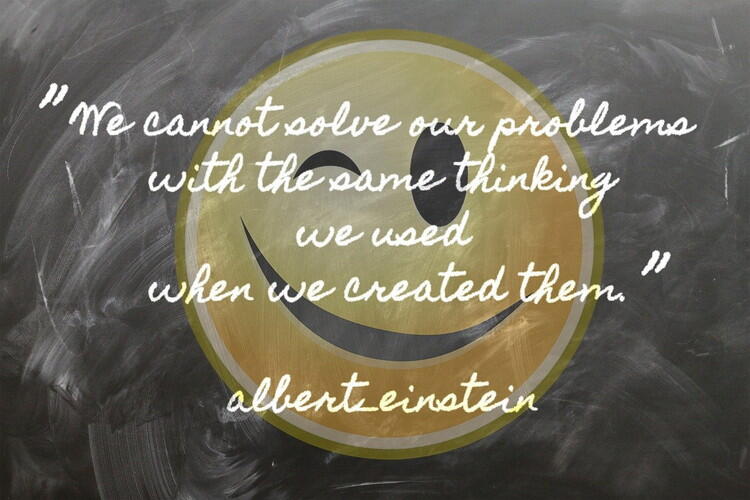
2025/03/03

投票前には優勢の評もあった河野太郎が破れて岸田文雄が新総裁に就任した。一連の流れは、第一期安倍内閣が政権を投げ出したあと政治的混乱が発生した時に通じる既視感を覚える。退陣した菅内閣は、コロナ対策では、偏向メディアが唱えるほどには決して失政とは言えないが、いくつかの課題は岸政権が宿題として引き継ぐことになる。
既視感と状況再現への懸念
菅義偉首相の突然の退陣表明を見て、一種の既視感、つまり過去に見た光景の再現と、それに由来する芳しからぬ状況が、あの再現はあってはならない、という思いを伴って浮かんでくるのを、避け難い感じだ。
2007年9月、第1次内閣がまる1年を迎えたころ、安倍晋三首相が突然政権を投げ出した。持病の潰瘍性大腸炎が急激に悪化した、という説明だった。臨時国会を開いて所信表明演説を終え、週末を挟み各党代表質問を受けるタイミングで急激な病状悪化に見舞われ、血便の下痢が続いて答弁のために議政壇上に立つのが不可能になった、という。
急遽後継の総理・総裁選びになり、安倍内閣で官房長官を務めた福田康夫とヴェテランの麻生太郎が争い、福田が勝った。彼は父親の福田赳夫元首相の総理秘書官を務め、議席を引き継いでいたが、民間企業サラリーマンからの転身で、官界歴も地方議員歴もない。政党政治家としての訓練も乏しい。頑固で斜に構えがちな性格も作用して、党内他派や官僚世界との折り合いがよくなく、北海道・洞爺湖畔のサミット=先進国首脳会議はなんとかこなしたが、首相在任1年で、やはり投げ出す感じで政権の座を降りてしまった。
後は麻生が引き継いだが、長引くバブル崩壊の後遺症に追い打ちをかけるように、リーマン・ショックが起きる。麻生は解散―総選挙で態勢を建て直そうとするが、金融危機と福田との総裁選のしこりが残る党内抗争に災いされて、なかなか機会が掴めない。そうこうするうちに、不況の祟りもあって内閣支持率が20%を割り、在任10か月を経た2009年7月にやっと解散―総選挙に持ち込んだが、結果は惨敗。自民党は下野の余儀なきに至り、超無能の鳩山由紀夫―菅直人―野田佳彦が1年刻みで交替する「悪夢の民主党政権」(安倍晋三)3年4か月が始まった。
本人も含めて予測不能?
今回も共通した印象が拭い難いが、当然違う状況もある。前回も今回も発端は安倍晋三の突然の政権放棄だが、前回の彼は在任1年にすぎなかった。今回はその安倍がまず野党・自民党の総裁に帰り咲き、総選挙に圧勝して民主党から政権を奪還して首相に復活。このときを含めて連続6回の国政選挙に勝ち、意外にも超長期政権を築いた。
彼は勢いに乗じて党規約を改定し、任期2年・2期まで、直前の国政選挙に圧勝すれば1年程度のボーナスあり、という総裁在任期間の限度を3年・最大3期に引き伸ばし、9年の長期政権像を描いた。そして第2次・第3次、さらに第4次と、郷党の大先輩・桂太郎が保持していた憲政史上最長連続政権の記録を破る7年8か月に達し、任期満了まであと1年余を残すところまできて、またも突然の潰瘍性大腸炎の悪化で退陣したわけだ。
後継の総理・総裁が安倍の官房長官だったのは前回と同様だが、前回が閣僚歴なし・官房長官になって1年の〝新人〟福田康夫だったのに較べて、今回は過去に閣僚歴を持ち、官房長官としても安倍長期政権を支えたヴェテランの菅だ。菅の当初任期は安倍が途中降板した自民党総裁の残り任期の1年余だが、本人も覚悟していた既定路線だから、1年余り務めた段階で迎える次期自民党総裁選不出馬・再選断念・即総理退陣表明になるとは、本人を含めてだれも予測しなかったろう。
しかし結果的に前回同様1年そこそこで2度の政変つまり総理・総裁の交替になった。今回の自民党総裁選挙は、全党員・全国会議員が関与する、いわゆる〝フル・スペック〟方式で9月29日に行われ、岸田文雄・高市早苗・河野太郎・野田聖子(出馬表明順)の4人が争い、衆知の通り岸田が第1回投票では僅差のトップ、河野との決選投票は圧勝して、新しい自民党総裁になった。
任期満了間近という違い
この総裁選挙については後で触れるが、今回の経緯は前回と共通していても、まったく別の要素がある。1年そこそこで2回の政変なのだから、新総裁は就任直後に開かれる臨時国会で首班指名を受け、新内閣を発足させたら、なるべく早く衆議院の解散―総選挙を行い、民意を問う必要性・必然性がある。これは、政党政治・議会制民主主義・議院内閣制の本旨に照らして当然の筋道だ。
前回は主に党内事情に妨げられ、半年以上も解散のタイミングを掴めず、内閣支持率の低下から総選挙の惨敗につながった。しかし別の視点でいえば、解散―総選挙まで、それだけの時間的な余裕があった。今回は違う。衆議院議員の任期満了が迫っている。憲法45条は衆議院議員の任期を4年と定め、解散があった場合にはその時点で終了する、としている。公職選挙法は、衆院議員の任期は総選挙の投票日から起算する、と規定する。前回の総選挙が行われたのは2017年10月22日だから、このとき選ばれた衆議院議員の任期は10月21日に終わる。仮に解散・総選挙で議員を改選する過程、という憲法が予定する手続きに沿った状況ではないのに、衆議院に〝住人〟がいない〝空き家〟の状態になれば、こういう姿は敗戦後初、つまり現行憲法下では初の珍事になる。岸田新総理・総裁として、そんな醜態は避けたいのは、当然の話だ。
菅政権で解散―総選挙をしておく手があったのは確かだが、そこに持っていく運びのまずさも作用して、菅は再選出馬を断念、総裁選が先行した。岸田新総裁としては、衆議院議員の任期満了が切迫しているのだから、政治日程をやりくりし、憲法が定める前例がある形で収めようとする。そこで総理・総裁就任後の政治日程は、極めて窮屈になった。
岸田はまず、甘利明幹事長、福田達夫総務会長、高市早苗政調会長以下の党役員人事を決めた。党役員が決まらなければ臨時国会に臨む体制が整わないから、これは必須の作業だ。そのうえで菅内閣で閣議決定していた10月4日召集の臨時国会に臨み、この日の朝の閣議の菅内閣総辞職を受けて
「内閣総理大臣が欠けたとき(中略)内閣は、総辞職しなければならない」(70条)「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決でこれを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立って、これを行ふ」(67条の1)
という憲法の規定に従い、4日に首班指名をうけ、組閣人事・宮中の認証式・初閣議を終え、第1次岸田内閣を発足させた。
〝空き家〟の醜態回避に向けて
ここで楽屋裏の事情を説明することになるが、本稿の締め切りにぎりぎり間に合う執筆時間は、この時点までだ。月刊誌の宿命で、原稿の整理・編集・印刷・製本・流通の段階を踏み、毎月1日という所定の期日に当月号を読者の手元に届けるにはこれが限界で、ここからは、現実は進行しているが記事は予定稿、ということにならざるをえない。
それをお断りしたうえでの記述だが、臨時国会の会期は10月14日までの11日間と決まった。新内閣発足の週内に岸田首相が衆参両院本会議で所信表明演説を行い、週末を質問側の準備期間としてみ、翌週明けに両院本会議で各党代表質問を行えば、そこまで進んだ時点で、衆議院議員の任期は余すところ、ほぼ1週間だ。ここで解散に持ち込めば、通常の手続きになり、現行憲法下初の衆議院の〝空き家〟という醜態は晒さずにすむ。
立憲民主党などの野党は、総選挙を控えてなんとしても〝見せ場〟をつくり、選挙戦を多少とも有利に運びたいという打算から、代表質問のあと衆参両院で予算委員会を開き、コロナ対策をはじめ当面の政策課題について新首相に質すべきだ、と主張した。彼らとしては、会期を延長して21日の衆院議員の任期切れぎりぎりまでの数日間を予算委に充てたのちの解散を、意図したのだろう。そうしてでも憲法が想定しない〝空き家〟状態は免れるではないか、というわけだ。
党利党略のためにはゴリ押しも
立憲民主党の枝野代表や安住国会対策委員長は、菅首相の退陣表明時点で、総裁選挙という自民党の〝私的な問題〟は夜間か休日に処理すべきで、国家公務員として給料を貰っている閣僚や国会議員は、正規の勤務時間中は〝本務〟に専念するのが本来のあり方だ、という奇矯極まる主張をしていた。菅内閣に開催を要求していた臨時国会召集・衆参両院での予算委員会開催を岸田内閣にも要求し、彼らが一問一答で新政権をいじめ抜く姿をテレビ中継で有権者国民に見せつけ、総選挙に向けた景気づけにしよう、と狙ったわけだ。
俗耳に入りやすい、いかにもテレビ情報番組の〝ニュース芸人〟が持ち上げそうな言い草だが、いうまでもなくこれは、国会を国権の最高機関と位置づけ、議会制民主主義・政党政治を明示する、現行憲法の定める政治秩序を無視した、違憲性の強い主張だ。護憲を唱えるなら、首相指名・新内閣構成、任期ぎりぎりの衆議院議員を改選する解散・総選挙を最優先課題とするのは、当然のことだ。しかし、そんな筋論はクソ食らえ、党利党略の前にはケンポー無視のゴリ押しも辞さず、というのが、議席をとるためには共産党との共闘も辞さない〝枝野立民〟の本音だろう。
岸田新首相は、予算委員会開催を回避し、代表質問が終わる10月14日に解散に持ち込み、周知期間・選挙準備期間を極端に短くして19日に総選挙公示、10月31日の日曜日に投票日、という大胆な策に出た。
この結果第1次岸田内閣は、その総選挙の結果を受けて11月中旬早々に召集される、特別国会で改めて首班指名が行われる日までの、ほぼ1か月で終わることになった。総選挙の後に第2次岸田内閣ができるか。自民党中心の連立政権は変わらないが、総選挙の自民党の不振を反映して新しい〝顔〟に変わることになるか。反自民諸勢力が雑然と集まる「悪夢」の再現か。それは選挙結果次第だ。ここで再び雑誌の製作過程の話になるが、選挙結果が出るのが次号の締め切りぎりぎりだ。新しい政権が岸田政権の継続か、すげ替えか、「悪夢」か、そこまでは間に合うだろうが、その前途については、本誌の誌面では年を越した時点で触れることにならざるをえない。いずれにせよ、第1次岸田内閣はいわば仮免許のようなもので、総選挙を経て無事に第2次内閣になってはじめて、それなりの安定度で国政に当たる資格を持つわけだ。
河野太郎、敗北の理由は
そこで本稿の後半は、後ろ向きのテーマになるが、まずポスト菅の自民党総裁選挙で、事前に絶対的本命視されていた河野太郎が、僅か1票差とはいえ第1次投票で岸田の後塵を拝する2位、決選投票では257対170という大差で敗北した、その理由を考える。
1次投票で、議員数と同数に設定される党員票で、総数382票の過半数以上は確実、6割前後はとれる、とテレビの情報番組が囃し立て、本人も自信を持っていた河野が、44%・169票に止まったのはなぜか。
党員票が地方票に置き換わって、各都道府県連当たり1票の47票となり、議員票のウエイトが高くなった決選投票では、高市とのいわゆる2・3位連合で岸田の逆転勝利もありうるという観測が、なかったわけではないが、それでも河野が勝つという見方もあった中で、決選投票の議員票382のうち、岸田は249票を獲得した。これに対し、河野はほぼ半分の131票に終った。これはいったいどうしたわけか。
河野の〝敗因〟に、総裁選の論争で、年金問題を典型として無理な政策提言を仕掛けたり、原子力発電をめぐり過去の反原発の主張とのブレが目立ったり、対中・韓国姿勢の軸が曖昧だったり、した点が指摘されている。自民党員・支持層や議員の感覚から見て〝リベラル〟の方向に偏り過ぎたのが影響した、という見方や、彼の発言や討論姿勢に独走、というより拒否感情を剥き出しにした独善性が強く出ていた、という批判も多かった。
とりわけ財政支出による基礎年金の大幅引き上げ論は、消費税の大増税と直結するのが必至なだけに、党員ことに総選挙を控える議員の抵抗感が強かったはずだ。女系天皇・夫婦別姓・同性婚など、総裁選では触れなかったが日ごろ主張していた点が、テレビが煽る新奇な風潮に流されがちな一般大衆には受け入れられても、自民党員、まして議員には到底受け入れられず、自らの足元を崩しただけでなく、正反対の路線をいく高市を引き立てて、実力以上と思われる善戦をアシストする結果になった、という指摘も否定できまい。
一部の議員には通用しても・・・
〝小石河連合〟という、いかにもテレビ情報番組制作者のネーミングらしい、人気者がスクラムを組むチーム編成をアピールする戦術も、背後に菅・二階の顔がチラつき続けたことも、逆効果だったと思われる。小泉進次郎や石破茂は、テレビに操作される大衆に人気があっても、自民党員、まして同僚議員の多くには、否定感情を持たれていた観もあった。菅・二階の影響力には限界が出ていて、だからこそ菅抜きの総裁選になったわけで、2人の後ろ盾は一部の議員には通用しても、党員票にはむしろマイナスだったろう。
尤もこうした見方も、あくまで自民党員・議員による総裁選挙という前提つきの話で、総選挙での有権者・国民の反応は別だ。第1次岸田体制の顔触れを見ると、かつて中曽根政権初期に、田中角栄の影響が直接及んでいると批判する〝直角政権〟という表現があったことを思い出させる面がある。いまの陣立てでは、第2次安倍内閣いらい9年間続いた安倍晋三・麻生太郎・甘利明の〝3A〟の強い影響下にある〝3A直系〟だと、少なくとも立民や社共など左翼党派や〝リベラル〟気取りのテレビ情報番組などがレッテル張りにかかるのは目に見えている。安倍退陣後も政治面に長期の連載記事を設けてアベ・ストーカーを続ける朝日新聞やその追随勢力も、岸田政権に対して、〝安倍亜流〟と刺すような視線をぶつけてくるだろう。
それが総選挙の結果にどう反映するか。そうした危惧を杞憂に終わらせ、有権者国民から支持・信任を受け、あっぱれ第2次の首班指名を勝ち得て、初めて仮免許を脱した本格的な岸田政権が始動することになる。
スペイン風邪に感染した平民宰相
菅退陣のポイントも押さえておきたい。秋田の農村から首都圏に出て、議員秘書・地方議員を経て代議士・大臣、さらに官房長官として安倍長期政権を支え、ついに政治の頂点に立った時点では、苦労人と好感されて60%を超えた菅の支持率が急落したのは、コロナ対策が無能・拙劣で万事につけ他国に遅れをとっていたからだと、テレビ主導のメディアは口を揃える。しかし、それが正当な評価だとは筆者は思わない。民主主義と自由経済に拠って立つ先進国中、日本が感染者の発生率・死亡率ともに断トツに低い。政府の対策がそんなに無能では、この成績は出まい。
そもそも天変地異の典型である疫病の世界的大流行が先行きどのように動くか、予測できるわけがない。テレビ各局を股にかけて尤もらしい説をぶつ〝学者〟〝専門家〟が目立つが、彼らの所論と占い師の弁に、たいした違いは感じない。早い話が、この夏の〝第5波〟のピークには、もっとひどくなる、コロナの勢いはずっと続く、といっていたのに、彼らは秋に入って感染が沈静化すると、いつの間にかテレビから姿を消していた。なに、秋が深まってインフルエンザ・シーズンに入り、同類のウイルスである中国・武漢発の新型コロナもまたぞろ勢いを強めると、再びシタリ顔で出てくるだろう。それなら要するに彼らはバイキンやウイルスと同じ、季節性の〝はやりもの〟にすぎない。
100年前に、当時の人類の3分の1から半数、6億人から9億人が感染し、5000万人とか9000万人とかが死亡したとされる〝スペイン風邪〟は、日本でも45万人の死者を出した。当時の首相・原敬や、明治維新・大日本帝国建設の功臣で元首相・陸軍の最長老でもある〝元勲〟の山県有朋も感染した。それどころか皇太子の裕仁親王すなわちのちの昭和天皇や、弟宮2人も感染した。
だがその直後、現職首相のまま遊説に赴く東京駅頭で個人テロに斃れた原は、後世〝平民宰相〟と謳われたが、〝スペイン風邪〟に感染した事実は忘れられた。45万人もの国民を死亡させた責任も、皇太子まで感染させてしまった〝失態〟の責任も、問われたことがあるとは、寡聞にして知らない。100年前の新聞の、ことに社会面は、いまのテレビ情報番組に較べ、とても上品だったとはいえなかったが、それでもいっても詮ないことはいう意味がない、という分別はついていた。
菅や彼が率いる内閣に向けられた多くの新聞・テレビの視線は、どう見ても公正・適正ではなかった。その批判はこんごじわじわと世間に浸透し、偏向マスコミの社会的信用・ひいては業績にも影響していくと思われる。
接種率世界最高レベルに
菅首相のコロナ対応に、ミスがまったくなかった、とはいわない。見通しなんか立つわけがないコロナ流行の先行きを、いささか楽観的に語りすぎた。安心・安全のキー・ワードを、安易に使いすぎた。変異を重ねるコロナ・ウイルスに対するワクチンの効果に限界があることは、季節性インフルエンザのワクチンを毎年打たなければならない事実が示している。それなのにワクチン万能論に傾きすぎ、ブレークスルー感染でテレビの〝ニュース芸人〟に揚げ足をとられる羽目になった。
とはいえ、菅が再選不出馬を表明した直後から、コロナ感染者数は東京・大阪・愛知の大都市圏を皮切りに急激に減少し、いまや全国に及んでいる。感染拡大防止の〝緊急事態宣言〟とそれに伴うモロモロの制約は、都道府県の行政姿勢によって多少の濃淡は残してはいるが、ほぼ解消された。10月を迎えた時点では、菅が退陣の記者会見で述べたように、ワクチン接種率は「先行する背中を遠くに見ていたアメリカをかなり差をつけて追い越した」世界最高レベルに達した。
それが菅本人の、訪米中のファイザー首脳に対する供給要請をはじめとする、粘り強い努力の成果であることも、疑う余地はない。ワクチンの効果で当面するコロナ禍が急速に鎮静化に向かった初秋の時点で、悪罵の嵐の中、努力を積み重ねながらじっと耐え続けていた菅が、突然心が折れた感じで溜まりに溜まった感情を堤を越えて奔流させるように、総裁再選不出馬をぶち撒けるのを、あと2週間、せめてあと1週間こらえていたら、政治風景はかなり変わっていたのではないか。
この稿で筆者は繰り返し指摘してきたが、戦勝国アメリカが敗戦国日本に押し付けた現行憲法下では、ごくフツーの主権国家なら問題なく持っている戒厳法制も、非常事態対処法制も、持てない。政府の権限でロックダウン=都市封鎖を断行することは、不可能だ。同様に、GHQが押し付けた日本行政の弱体化・非効率化を目的とする内務省の解体で、かつて内務省衛生局が一元的に管理し、官選知事に通牒という名の指令を出すことで、知事が市町村を指揮・監督し実施していた、世界に冠たる医療・保健行政体制は徹底的に分割され崩壊してしまった。いまの制度では、国の役割は予算措置と企画立案、せいぜいが行政指導に止まり、医療は都道府県、公衆衛生は保健所を持つ市町村が主体で、政府が一元的に強い方針で医療・公衆衛生行政を展開することは、制度的に困難になっている。
菅は記者会見の場に、法律にも経済にも無知な、極端に視野の狭い〝医療専門家〟なんかを侍らせず、首相としての明確な意思・方針を述べて、コロナ禍に対し敗戦憲法と占領法制を引きずる日本は、非常時でもあっても、できることとできないことがある、できないことはできない、と指摘すべきだった。その役割は、岸田内閣に宿題として託される。
(月刊『時評』2021年11月号掲載)