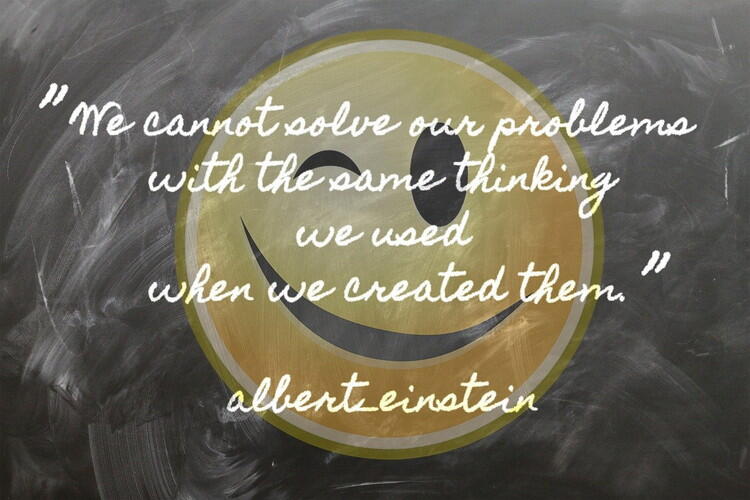
2025/03/03

最後まで開催を巡って世論が二分、と言えば聞こえはいいが、1年延期を決断した以上、東京オリ・パラは国際社会に対する信義の面で開催して当然だし、政権はそれを強く打ち出すべきだった。戦線のインパール作戦を引き合いに出す議論もあったが、むしろ国民感情に引きずられた失敗例としては国際連盟脱退の方が似つかわしい。
〝島国根性〟の歪みが表出
この稿が読者の目に触れるころ、東京オリンピックはすでに終わっているし、パラリンピックも閉会しているはずだ。中止論と実施論が交錯した東京オリ・パラは、すでに結論が出た段階に移っており、開催の是非ではなく、実績した結果がどうだったかが評価の対象になっている時期だ。
したがってこれから述べることは、ケンカ過ぎての棒ちぎり、後講釈の印象を与えるのは避けられまい。しかし筆者は、この開催か否かの議論、世界の、つまり外国の視線に無頓着な、古い日本の〝島国根性〟の歪みがはしなくも現れたと思っている。いまの日本、日本人の品性と矜持のレベルが、すべてを反自民・反菅に持っていこうとする偏向〝リベラル〟メディア、その口まね一色に染まった俗悪を極めるテレビと、テレビ如きにたやすく操作される大衆世論の露骨な癒着が、はっきり露呈されたと思っている。そしてこの点をきちんと整理しておくことは、この半身不随の〝障害〟を負った東京オリ・パラの数少ない遺産を残すうえで、欠かせない作業だと考える。
守るか、破るかの単純な話
そこで本題に入るが、東京でオリ・パラを実施するかどうかは、簡単にいえば、約束を守るか、〝家庭の事情〟を理由として約束を破るか、という極めて単純な話だ。マトモな人間なら、議論の対象にすること自体、論外だろう。この春、いまオリ・パラを東京で開催する意義がどこにあるのか、といった議論を、偏向新聞を筆頭に、NHKという隠れもない政府関係機関を含むすべてのテレビと、そこに住みつく〝ニュース芸人〟が、詰問口調で連呼していた。
子供がコロナの旅行制限で生涯に一度の小学校6年生の泊まりがけ修学旅行にいけないのに、なにがオリ・パラだ、という無茶苦茶な没論理的イチャモンを、テレビが拾い上げる。それを〝ニュース芸人〟がさも重大事のように、深刻な顔で語る。お囃子衆のコメンテーターという無知・無芸のヒマ人連中が、大げさにうなづきあう。こういうマンガにも滅多に見られない珍情景が、臆面もなく演じられていたのだ。
そうしたとき、菅首相は断固として、2020オリ・パラを1年遅れで東京で開く意義は、日本国と日本人の信義と威信と矜持を世界に示すことだ、と喝破すべきだった。それなのに、例の上目使いの自信なげな表情と、モタつく秋田弁で、〝安心・安全〟などと繰り返していたのだから、話にならない。
自ら手を挙げて結んだ契約
13年前、だったと思うが、日本、正確にいえば東京は、だれから強制されたのでもない、自らの意思で、2020年のオリ・パラを東京で開催したい、と手を挙げたのだ。そしていくつものライバル都市と争い、最後には地球の裏側で開かれたIOC総会の場の、トルコのイスタンブールとの決選投票に残ったのだ。
その場に、安倍首相は外遊のついでとはいえ、わざわざ飛んでプレゼンした。安倍首相と言えば2016年リオオリンピックの閉会式でスーパー・マリオの扮装で登場する子供じみたパフォーマンスを演じ、東京大会盛り上げに躍起だった。後に現職の大臣夫人になるタレントは、わざと舌足らずの日本語を使って、東京開催になれば投票権を持つ〝オリンピック貴族〟に対する〝オ・モ・テ・ナ・シ〟を惜しまない、と、古くからのフジヤマ・ゲイシャのイメージそのままの調子で、日本のホスピタリティをアピールした。そして日本は、2020年の大会開催地の権利を得たのだ。
開催地の権利は、開催する権利とはまったく違う。オリ・パラの開催権はあくまでIOC、IPCが握っている。東京が持つことになるのは、所定の競技を実施する会場を整備して提供し、メンテナンスし警備して安全を確保し、世界から集まった選手や競技関係者と〝オリンピック貴族〟のために、それぞれふさわしい競技条件と接遇、そして宿泊施設や社交の場を提供することだ。十分な食事、トレーニング設備、豪奢なパーティ、さらに過去の経験に照らして予想されないものでもないテロなどに対処する、防御態勢を整えることも入る。要するに、大会の場を確保したという点は手中にしたが、それ以外は義務は山ほど背負う一方、権利・権限はほとんどない、かねて不平等条約の悪評が世界に定着している、片務契約を結んだに過ぎない。
そんな面倒なものをなぜ契約した、といってもはじまらない。オリンピックとはそんなもので、オリンピックを招致し開催するということは、そうした立場を甘んじて受け入れることだからだ。それを知らなければ阿呆だが、日本のテレビの〝ニュース芸人〟はいざ知らず、少なくとも招致関係者は、そんなこと、百も承知していたはずだ。そのうえで、ここが重ねて念を押す点だが、自ら手を挙げて、ライバルと争って契約を結んだのだ。
昨春段階で決断すべき中止
7年、8年前に、いまのコロナ禍が予見できたはずがない。しかしすでにこの時点で、世界はニューヨークの9・11、日本は東北東部の3・11を経験していた。超大規模なテロや自然災害なんか起きっこない、とタカをくくっていたとしたら、それはただのバカである。それくらいわかっていたろうに、日本のスポーツ界も政府も、東京都も新聞・テレビも、財界人もさまざまな業界人も、もちろん国民大衆も、それぞれの立場で利害打算を働かせつつ、オリ・パラを歓迎したのだ。
あのころ、ルーピー鳩山・イラ菅・ヤケクソ解散の野田と、3年4カ月間に3代の超無能政権を続けたあげく、もろとも瓦解し、総選挙にも惨敗して虚脱状態にあった、旧民主党を中心とする野党勢力も、敗走の末に四分五裂の姿を晒していて、安倍政権の〝成功〟を指をくわえて見ているだけで、批判のヒの字、中止のチの字も唱えなかった。
筆者は昨年春の時点で、2020東京開催は中止すべきだ、と考えていた。コロナ禍は日本ではまだそう激しくなかったが、欧米はすでに猖獗を極めていて、大流行を横目に最終予選をしたうえで、夏にはるばる東京まで選手団を送る気力は、彼らにはとてもないと見ていたからだ。
そもそも近代オリンピックは、4年を周期とするオリンピアードの初年度、西暦で4で割り切れる年に、IOC=国際オリンピック委員会が主催し、加盟国の中から名乗り出た1つの都市を会場に行われる、芸術的行事を伴う祭りである、と憲章で決まっている。2020東京大会はこのルールに則って決められており、オリンピックには過去に世界大戦で中止された例が3回あるが、延期した例はない。それならルールと前例に沿って潔く中止し、既定のパリ、ロサンゼルス大会を規定通りおこなったあとに、東京に再起の機会を考慮するのが、万事ルールを厳守して行われるべきスポーツの最大行事として適切だ、と考えたのだ。
察して然るべきIOCの打算
ところが2020年春の早いうちに、1年延期が決まってしまった。日本の一部偏向メディアは、IOCは2年延期を考えていたのに任期中の開催に固執する当時の安倍首相の要請で1年になった、とシタリ顔で伝えていたが、筆者はハナから信用していない。前回から6年後に次回大会を開き、その2年後にまた大会を開くという不細工なことを、いくらなんでもIOCが考えるわけはなかろう。かといって2020年の開催は、コロナ禍が激化しているアメリカが応じる状況にない。アメリカ抜きの開催は、オリンピックのテレビ中継権を独占契約しているアメリカのNBCが、黙っているはずがない。NBCの中継権料なしに、ローザンヌの本部ビルを建て替えたばかりのIOCのクビは回りかねる。1年待ちの程度ならなんとか回していけるとしても、それが限界で2年は持たない。こういうことだったと見て間違いなかろう。
逆にいえば、そうである以上、2021年から先の延期をIOCはまったく考えていなかった、ということになる。それくらい察しがつかないようでは、一国の行政、一地方自治体の行政を与かるものとして、それを報道し論議するものとして、アタマの回転が悪すぎる、ということになる。
まさか東京都や政府の責任ある立場で、IOCのフトコロ事情を匂わす説明なんか、できるわけがない。だからこそ新聞・テレビはそうした〝急所〟に触れたオリ・パラ報道・解説をすべきだったのだ。テレビの〝ニュース芸人〟レベルでは、そこまで到底思い至らなかっただろう。感染症や医療システムの専門家と称する連中も、極端に専門バカ的な視野狭窄に陥っていて、問題をウイルスとは別の視野から捉える能力に、欠けていたのは明らかだ。それらは予想できた姿ではあるが、やっぱり、の感を免れることはなかった。
率直にいって再延期論、いまさらの中止論はもちろん、無観客論にしても、低俗で幼稚なテレビが感情論一本槍で煽り立てるのに引きずられた、他者の存在を考えず、自分の都合だけを唯一の尺度に身勝手な言い分に固執する世論と、それに便乗して政局・倒閣に持ち込もうとする野党との、金切り声の大合唱にすぎない。そんなもの、信義・威信・矜持の三点で一喝して退ける度胸のない、〝菅政治〟の情けなさには、重ね重ね、長嘆するほかない。
欧米では試合観戦を再開
以下に示すデータは、日本に関する数値は読売新聞の紙面に載ったもの、外国の数値は同じ紙面に載ったジョンズ・ホプキンス大学が発表する集計によるものだが、
▽7月10日現在の感染者/死者数
アメリカ 3379万2455人/60万6483人
イギリス 504万 402人/12万8601人
▽直近の7月1日から10までも感染者/死者の増加数は
アメリカ 13万9317人/2021人
イギリス 24万8774人/189人
となっている。実はこれらの統計は、ドイツやフランスでさえ、日を追って追跡していると、ありえない矛盾した数字が頻繁に出現して、どこの国も行政のタガが緩んでいるのだな、と思わざるを得ないのだが、一応信用のおけそうな米英と、これも地方の報告数の信用度に疑問なしとしないが、日本の数字をあげると、感染者 81万6810人/死者 1万4983人となっている。7月1日から10日までの増加数は、感染者 1万6293人/死者 214人だ。こうした中で、アメリカは最も感染がひどかったニューヨークでもカリフォルニアでも、ほぼ日常の経済・消費活動を再現していて、すでにシーズンを終えたアメリカン・フットボールやプロ・バスケットボールの・リーグ、現にシーズンたけなわのメジャー・リーグ・ベースボールも、巨大な体育館やスタジアムに、最近はフル収容で大観衆を集めて、自由に歓声をあげさせている。イギリスも、サッカーの欧州選手権を、当初は多少制限をしていたが、イングランドが進出した準決勝・決勝では、収容人員を大幅に増やしていた。それだけでなく、競技場周辺はもとより、ロンドンをはじめ多くの町の広場では大群衆が集まり、ビールを片手に肩を組んで応援している。米英に限らず仏独も、市街地の外出規制や旅行規制は解除されたし、路上席に限らず屋内でも、酒食提供が完全復活していたようだ。
それにくらべて日本は、前掲の数字が示すように、首都圏を中心に感染のリバウンドが心配されるとはいえ、それほど深刻な状況にあるとは思えない。日本人はどう思っていようと、欧米・世界の目からは、日本のコロナ禍はそう深刻ではないと見えるのは、当然の話といわなければなるまい。現に首都県でもプロ野球やJリーグが、一定の制約があるとしても、大観客を集めて通常のスケジュールで進行している。それなのにオリンピックに限っては無観客だというのは、実はおよそ平仄が合わない、説明がつかない話なのだ。
開会式の半月前という早い時点で来日し、大会組織委員会や小池東京都知事、丸川オリンピック担当相らと協議を重ねてきた、主催者IOCのバッハ会長が、日本側の決断を支持する、と前提をつけながら、無観客ではオリンピックを心待ちにしていた世界の観客も選手も失望を免れないだろう、と発言したのは、ぎりぎりの、しかし痛切な、本心の表明だったに違いない。
社説で露呈した極端な分裂症状
もともと一片の理性さえ持ち合わせていたら、実現するはずがないと判断がつく中止論だが、その最大のブチ屋になったのが、5月26日付「朝日新聞」の「中止の決断を首相に求める」という社説だった。オリンピックの成り立ち、そこに由来する仕組みに関し、仮にも論説委員でござい、それ以前に新聞記者でござい、というのなら、ありえない認識不足・知識不足・勉強不足を露呈した、怪文書もどきというほかない〝社説〟だったが、同時に驚かされたのは、最新の決算で社史上最大の400億円を超える赤字を計上した朝日新聞社が、15億円とされる巨費を投じ、IOCが一業一社に限って認めるオリンピック東京大会の、日本のメディア業界を代表するスポンサーシップを、持っていた事実だ。これと〝社説〟の極端な分裂症状。〝朝日人〟は、これぞ編集権の経営からの独立の証左、といいたいのかもしれないが、この図柄は傍から冷静に見れば、朝日新聞社の企業ガバナンスの不始末、というほかなかろう。
編集が暴走も辞さない構えだと経営トップがわかっていたら、あらかじめ根回しして矛盾がないように体裁を整えるのが、企業統治というものだ。企業として醜態を晒さないためスポンサーを降りるか、〝社説〟を押さえるか、どちらかに向けて、然るべき手を打っておくべきだった。管理畑や業務畑から社長が出るのではなく、歴代の社長は編集畑から出ているのだから、この程度の調整もできないのは、組織としておかしい、といわれても仕方あるまい。
ついでにいえは、応援の群衆を集めることといい、予選は都道府県内だが、本大会は全国規模で、〝甲子園〟に向けて膨大な人の流れを生じさせる高校野球は、オリンピック以上に、疫病の感染機会を増やす恐れが高い。当然断じて中止すべきものだろう。ところが前年は中止した、朝日新聞社の販売部数拡張の最大イベントである全国高校野球選手権大会は、今年は中止のチの字も出ず、平然と予選から実施され、甲子園大会に突進した。
社説の見出しにうたった通り、菅首相に的を絞った政権打倒の機運を煽ることが、実は朝日のオリ・パラ中止論の本音であって、この限りでは編集と経営は八百長的に経営側の立場を汲んで対立構造を演出して見せるが、低迷が続く部数拡張の決め手である高校野球のためには、経営と編集はなりふり構わず手を握るのが朝日新聞社の体質だと、これほど分かりやすく示した例も、滅多にあるまい。
例として無理があるインパール
朝日を含む〝リベラル〟論者の間では、前大戦中のビルマ戦線のインパール作戦を例に引き、指揮官の思い込み的な暴走が全軍の崩壊を招いた「失敗の本質」に学ぶべきだ、と菅批判を展開する論法が流行した。
たぶん、防衛大学校などに在籍した少壮学者たちが「大東亜戦争における日本軍の失敗を現代の組織一般の教訓として」(序章)生かそうという狙いで、バブル経済最盛期の1984年に、ダイヤモンド社からビジネス書として刊行し、文庫化もされた著作で、〝賭の失敗例〟として挙げている部分からの、連想だろう。
しかしこの著作は、ノモンハン、ガダルカナル、ミッドウェー海戦、インパール、レイテ島、沖縄戦の6つを対象として、というか、半分近くを沖縄戦に紙数を割いて論じている。オリ・パラの話題に持ってくるには、反菅キャンペーンの偏向報道的意図があるにしても、いかにも無理がある。
むしろ国際連盟脱退に相似
むしろ戦前の日本の行動と今回のオリ・パラ中止論との相似を求めるのなら、満州問題で国際連盟を脱退した選択が、似つかわしいだろう。当時の日本は、日露戦争いらい〝生命線〟だと意識してきた、しかしどう見ても中国領の満州=いまの中国東北部に、強引に傀儡政権をつくり、国際社会から疑惑と批判を招いた。そして国際連盟調査団の現地調査を経て、白紙に戻すように求められた。
当時の日本は第1次世界大戦の〝勝ち組〟の一角に処遇され、現在の国際連合=国連になぞらえるべき国際連盟で、一定の席を保持していた。それなら、なんとか折り合いをつけて円満な収拾を図るべきだった。それなのに陸軍の執念と、〝ここは御国を何百里〟の軍歌が物語るように、日本人が血を流してきた土地だ、という国民感情に引きずられて、国際連盟を脱退してまで強引に日本の内向きの論理に固執して、国策の根本を誤った。
当時の日本のマスコミの大半は、国民感情を重視するのは当然だとして強硬論に与し、結果的に大間違いの〝共犯〟になった。今回もマスコミの大勢は、国民多数の感情論に与して、オリ・パラ中止論に走っていたが、万一にもそれを強行していたら、日本は国際社会で立場を失い、国益を大きく損なうことになったに違いない。無観客開催という邪道に走りながらも、ぎりぎりの線で破綻を回避したのは、正解だったろう。
遺憾だった皇室発言の介入
今回のオリ・パラ問題に関連して、もうひとつ、遺憾ながら言及せざるを得ない点がある。宮内庁長官が、自身の〝拝察した〟ことだとしながら、天皇はじめ皇室が、オリ・パラ中止の方向に、少なくとも心情的には大きく傾斜し同調している、と理解するほかない発言を、定例記者会見で述べた点だ。
仮にも宮内庁長官、それも警察官僚として頂点に立ち、内閣官房にも入った経歴を持つ人物が、微妙な問題に関して迂闊な発言を、勝手な〝拝察〟つまり自分ひとりの想像で、公にするわけがない。そう発言するだけの実態があり、それを定例記者会見という公式な場で明らかにすることに関して、黙示以上の同意があった、と考えるのが自然だ。
それがオリ・パラ東京開催の是非という、国論を二分する、いわば政治的争点で生じたのだから、事態は深刻だ。いうまでもなく、日本国憲法が定める、天皇の政治的超然を前提とした「国民統合の象徴」という立場の根源に、触れうるからだ。
たまたま言葉のアヤで国論二分と記述したが、筆者の見るところ、オリ・パラ開催に対する世論の動向は、新聞の世論調査などが伝えるのとは正反対に、賛成7・反対3といった兼ね合いだろう。賛成の中には、外人観客の入国禁止は、コロナ禍のもと相手も一般人の不要不急の入国は認めていないのだから、相互主義の原則で当然だが、国民に対する無観客の固執は納得できない、という向きも多いだろう。反対の側も、断固反対はそう多くなく、なにぶんコロナの世の中だから、というレベルが多かったと思われる。
そうした微妙な問題、しかも政治的な権力闘争に絡む色彩を帯びている問題について、皇室が立ち入るのは、明らかに具合が悪い。現に皇室は、秋篠宮眞子内親王の結婚決意の件で、国民感情の微妙な揺れの中にある。だからこそ、国民の多数の考え方に沿って、と宮廷官僚が配慮したのかもしれないが、その〝多数の考え方〟がテレビ主導の〝世論〟では、逆効果しか生まない、と考えるべきだ。
(月刊『時評』2021年10月号掲載)