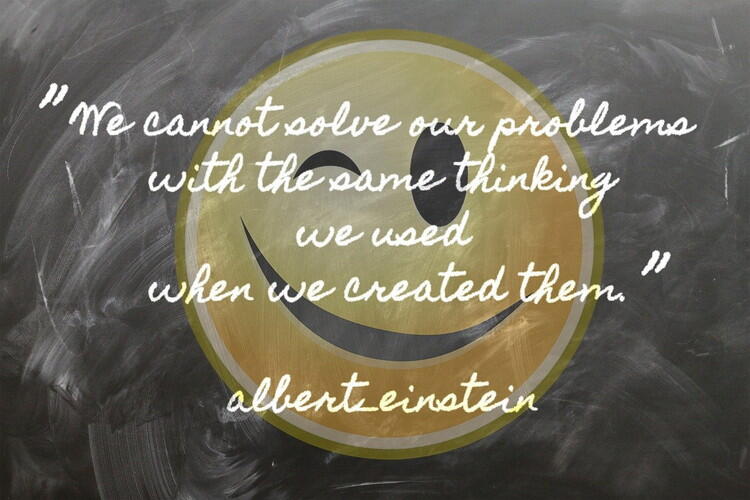
2025/03/03

コロナ禍のもと、何かといえば政府の対策に不満や不平をぶつける風潮がますます強まっているが、もともと日本の公衆衛生行政は優れた機能を発揮していた。しかし戦後、占領軍が日本の弱体化を企図して改革したがゆえに非効率・不都合が生じた。それは〝立法意志〟そのものだ。マスコミが煽る政府批判は、近代日本以後の経緯を鑑みず現象面だけ捉えた思考停止にほかならない。
Tweet忘れられた後藤新平の功績
情報化時代だ、情報社会だ、といわれ出してほぼ半世紀たったが、ホントかね、と思う面が少なくない。情報の切れ端だけは知っていても、それらをつなぎ合わせてものを筋道立てて考える習慣は、この時代、どんどん見られなくなったように思う。それが世間一般の人たちに限らず、テレビの情報番組と称するワイドショーで時事的な話題を扱う〝ニュース芸人〟や、その回りを囲むコメンテーターと称するお囃し方、〝専門家〟と呼ばれる顔触れだったりするのだから、閉口だ。
一例をあげれば、コロナ禍で悪戦苦闘する世界で、いままで最もうまく対応してきたのが台湾だということ。その台湾で、明治後半から大正時代にかけ活躍した日本の政治家・後藤新平がいまも官民の尊敬を集めていること。これらは広く知られているだろう。
しかし後藤新平が日清戦争の賠償で日本の海外領土になった台湾に赴任したとき、清朝政府がそれまで〝化外の地〟としてマトモに統治に取り組まず、未開状態のまま放置していて、町村部はアヘン吸引常習、山岳地帯は高熱が続く風土病に苦しめられているのに驚き、アヘン禁止と公衆衛生の普及・疫病防止に努め、台湾の暮らしを日本内地並みの清潔さに引きあげた、その遺風がいまの台湾の防疫成功の出発点になった、と台湾で語り継がれ、後藤を尊敬する理由になっていることまで、知っている人は多くないだろう。
まして後藤がもともとはドイツに留学した医師で、愛知県の病院であげた実績を認められて内務省衛生局長に抜擢され、アヘン絶滅と風土病の防疫を主な任務として台湾に派遣され、目覚ましい成果をあげて日本の台湾統治全体にいい影響を及ぼすまでの、詳しい事情はほとんど知られていないのではないか。内務省衛生局長という、いまは耳にすることがない肩書に注目することも、世間一般の人はもちろん、テレビの〝ニュース芸人〟や新聞記者にも、まずいないに違いない。
不満を政府にぶつける風潮へのつながり
しかし実は、内務省衛生局長というキーワードと、いまのコロナ禍のもたらす困難をすべて国・政府の責任にして不満をぶつける風潮は、深くつながっている。その構造を説き明かすと、こういうことだ。
国と地方の役割分担とか、地方分権に基づく地域性を生かした独自の試みというと、マスコミはすぐ飛びつき、持ちあげる。その一方で、なにかで困難にぶつかると、二言目には、総理はなにをしている、国のやることはすべて後手後手を踏んでいる、政府の施策はなっていない、と国や政府に文句をつけるのがクセになっている。議論はそこで思考停止になり、打開に向けた建設的な動きにはつながらないのだが、マスコミはそれだけでいっぱしの政治・行政批判をしたつもりになり、そのあり方がおかしいとは全然思わない。
その姿勢に世論も追随して、そうだそうだと、責任追及にふけっているうちに時間だけが過ぎ、困難はいっこう解決せず、延々と続くのだが、そうした姿の根源に〝内務省〟の存在、内務省の興亡をめぐる史実があることは、マスコミも、テレビの視聴者、新聞の読者である世間の多くの人たちも、この際考えてみたほうがいいのではないか。
一歩抜きんでた筆頭官庁
そこで、とりあえず内務省の説明から始めるが、明治維新で成立した新政府は、当初は太政官制という公家=宮廷官僚支配の形をとり、〝お雇い外人〟の知恵を借りながら行政組織の整備を進めた。内務省はその中で明治6=1873年に生まれた、草創期から存在する古参だ。昭和20=1945年の敗戦までは、陸海軍省は別として他の官庁から一歩抜きん出た筆頭官庁として、内政全体の総司令部的存在だった。いまの日本にそういうものがあるか、第2次以降の安倍内閣時代の総理官邸がそうだ、という見方があるかもしれないが、それはさておき、1960年代から80年代の日本の高度成長期・世界第2の経済大国と謳われた時代の大蔵省が、かつての内務省と同様の存在だったといえよう。
内務省の組織だては、太政官制が内閣制度に移行して行政各部の体制が固まる明治18=1885年には、なにぶんにも大日本帝国という神権君主国家の内政を総覧するのだからやむをえまいが、大臣官房の次に筆頭局として神社局を置いていたし、外局には神社造営局というものもあった。しかし、それは一般行政とは別次元の話で、あとは省内人事として任命して異動させる官選知事を置く道府県を管轄する地方局、東京に警視庁・道府県庁にそれぞれ警察部を置き治安を一元的に掌握する警保局、国道や国が管理する一級河川などの整備・維持に当たる土木局、そして公衆衛生と疫病対策に当たる衛生局の4局の、計5局体制をとっていた。
この時点で公衆衛生・防疫を、治安維持や国土建設と並ぶ、現業3部門の一つの局に位置づけて重視した点は、注目に値する。当時の日本が後進国で衛生水準が著しく劣っていたから、というわけではまったくない。幕閣時代から徐々に増えていた来日欧米人が、シナやインドはもちろん、母国とも比較にならぬ日本の清潔さ、公衆衛生水準の高さに驚嘆した事実は、彼らが遺した多くの手記などが証明している。肺結核という呼吸器感染症が〝国民病〟といわれるほど蔓延していて、民生的にも、徴兵制下の軍事運用面でも、看却できない状態だったという視点もあるが、行政組織整備の初期段階から〝衛生〟が欧米先進国以上に重視された事実は、〝東洋清潔の民〟の伝統を示すものなのだ。後藤新平は、こうした日本の近代的公衆衛生制度の構築経験を踏まえて、台湾で衛生局長・民生局長・民生長官を務めたことになる。
〝スペイン風邪〟の総司令部として
時代が下って〝スペイン風邪〟のとき、内務省衛生局は、海外で流行が始まった初期段階から、出先が外務省に報告してくる世界各地の感染状況を、逐次道府県知事に伝えて注意を喚起した。国内で感染が拡大すると、市町村単位で細かく状況を報告するよう各知事に求め、現場で指導に当たる〝防疫官〟を必要に応じて中央から直接派遣している。
一家の稼ぎ手が仕事を失ったり、斃れたりして生活困窮家庭が続出すると、皇室資金を充てた恩賜財団・済生会の〝救恤金〟を配布する手筈を整えた。ラジオ・テレビはまだ存在せず、新聞も一般家庭には必ずしも普及しているとはいえない時代だから、ポスターを張り巡らす国民向けの啓蒙活動を中心に、内務省は地方の行政指導、感染対策、社会福祉から広報までを担う総司令部として、その役割を着実に果たしたのだ。
蛇足の蛇足だが、前にもこの稿に何回か登場した内務省衛生局編『流行性感冒「スペイン風邪」大流行の記録』には、当時のポスターの写真が数多く掲載されている。いまのコロナ対策の政府広報とも共通する、マスク着用、うがい・手洗いの励行、人混みでの咳エチケット、を呼びかけるポスターと並んで、親族や知人の葬儀出席も避けるよう求めるポスターがある。死者の多さと、それでも葬儀は欠礼できなかった当時の生活感覚・家族関係・地域一体感を物語って、注目される。
予防注射の啓蒙ポスターもあるが、ワクチンに関する記述は、本文の各国の防疫対策を紹介する部分のアメリカの項で、流行末期の1919年末に研究が進行中と書いてあるだけだ。ポスターのいう〝予防注射〟が、いま問題の遺伝子操作による新型はもちろん、生ワクチンや不活化ワクチンなど、今まで使われてきたものと同レベルとは、不活化ワクチン代表格の種痘がすでに普及していた時代だが、ちょっと考えにくい。この本の〝スペイン風邪〟治療の部分には、細菌性肺炎や気管支炎、そして〝国民病〟の肺結核治療に関連する記述が頻繁に出てくるが、当時の〝予防注射〟がどういうものだったか、気になる。
社会局の設置、厚生省の発足
本筋に戻って、かつての内務省衛生局は極めて大きな権限、権威、権力を持っていた。パンデミック=タチの悪い伝染病の世界的大流行ともなれば、全面的に指揮をとるのは当然のことだった。その権力は、後述するように敗戦後の占領軍による〝内務省解体〟で大きく損なわれたが、いまも日本のマスコミ、そして世論の深層心理に残っていて、二言目には、総理は無能だ、政府はなにをしているか、という罵声の根っこになっているのは、否定すべくもあるまい。
大正9=1920年、内務省は前記5局に加えて社会局を設ける。第1次世界大戦による社会変動と貧富格差の拡大に起因する〝コメ騒動〟発生が直接の契機で、それまで地方局の一角にあった救恤つまり貧困対策の部署を、工業化が進むにつれて不可欠になった労働問題対応と併せ所管する、新組織だ。その社会局は、関東大震災で被災者支援の必要度が高まったこと、第1次世界大戦後の世界で社会福祉政策重視の流れが強まったこと、日本でも工場労働者対象の健康保険創設に向けた取り組みが本格化したこと、などを受け、2年後に内務省の内局から、外局という独立性の高い実務型組織になる。
健康保険法は工場労働者を対象に昭和2=1927年1月1日に施行されるが、この段階では衛生局は内務省に残った。世界恐慌に続く東北飢饉があり、満州事変・上海事変・支那事変が続いて国家総動員体制が唱えられる中で、昭和13=1938年に厚生省が発足し、この時点で内務省内局の衛生局と外局の社会局は厚生省に移る。
ただし内務省が道府県の官選知事に通牒を出して衛生・防疫行政を一元的に動かす仕組みは、そのまま維持された。つまり内務省衛生局は厚生省衛生局に看板を掛け替えただけで実質的な変化はなく、人事面でも垣根ない異動・交流が自由自在に行われた。
〝日本の社会保障制度の父〟灘尾弘吉
政策がどう固まり、具体的な施策に結びつくか。それによって行政はどう動き、その中で組織はどう変化するか。こうした点はそれぞれの分野のキーパーソンである官僚の履歴から分かることが多い。その一例に戦後は自民党代議士になり、厚相・文相をなんども務め、晩年は大蔵官僚OBの前尾繁三郎や商工官僚OBの椎名悦三郎と並んで〝自民党三賢人〟と謳われ、衆議院議長も務めた灘尾弘吉をあげると、大正13=1924年内務省入省の灘尾は、まず衛生局調査課配属になる。2年後に課長級で栃木県に出るが半年で本省に復帰し、社会局保険部規画課、同局社会部保護課を経て、社会部福利課長、同保護課長になる。まず健康保険制度の企画、次に生活困窮者や社会的弱者が主対象の保護行政、そして社会福祉全般にかかわる諸機関や諸団体の統括調整、と日本の社会保障制度の開拓者の道を、歩かされたわけだ。
厚生省発足とともに社会局保護課長、いったん内務省に戻って土木局道路課長、内務大臣官房会計課長と、警察を除く内務省の要所で経験を積んだうえで、官選の大分県知事になる。知事在任は1年半ほどで、厚生省に戻り民生局長、引き続き衛生局長と、〝古巣〟の行政経験を新設して日の浅い部署に伝授することに努めた。その後再び内務省に戻り、地方局長を経て鈴木貫太郎内閣で内務次官になるが、在任4か月で敗戦に伴い退官する。
内務省は、道府県の課長・部長と本省勤務を往復して官選知事になる地方行政を担う地方局、道府県の警察の警務・警備課長と本省勤務を繰り返しつつ道府県警察部長に進む警保局、技術官僚が主体の土木局畑とコースが分かれていて、官僚もそれぞれの〝畑〟で育つ。灘尾は当初から新しい社会局畑の開拓者と目され、その〝畑〟から大きくは出なかった。内務官僚の頂点の事務次官は地方局畑と警保局畑が交替で占めたが、灘尾は社会局畑出身で空前絶後の内務次官で、いまでも〝日本の社会保障制度の父〟といわれている。
灘尾もよく知る祖父と伯父
筆者が駆け出し記者時代だった時代は地方の幹部級もほぼ内務省育ちで、見習いで出た大阪市警視庁(後述)の総監つまり本部長や警務部長・警備部長ら幹部は元内務官僚が多く、最も若い警備部長は中曽根康弘元首相と同期の昭和16=1941年入省だった。サツ回りの担当管内にあった大阪税関長や、労働組合と革新政党担当を兼ねる労農記者会がある大阪労政局の局長、東京政治部に移り〝60年安保〟取材を第一線で乗り切った後、国民皆保険・国民皆年金の発足期の厚生省クラブも、課長級以上は内務省育ちだった。
したがって、自然と内務省時代と敗戦後のアメリカ軍の占領政策による〝内務省解体〟にからむ四方山話を聞く機会が多くなった。飛び飛びで3回持った厚生省で、2度目に担当した第2次池田勇人内閣で灘尾弘吉が大臣だったころ、よく私邸に〝朝駆け〟して、当面の行政問題だけでなく昔話も聞いた。
実は筆者の父方の祖父と母方の伯父が内務官僚で、祖父は伊沢多喜男らとともに内務省初の東京帝国大学法科大学卒の〝高文〟組。地方畑で一貫し、初任地は沖縄県、以下東京府、鹿児島県、石川県と回り、日韓統合前の朝鮮統監府、引き続き統合後の朝鮮総監府に在勤。内地に帰って三重県・宮城県知事、そして次官と警保畑トップの警視総監と並んで〝内務3長官〟といわれた地方畑トップの北海道長官に、本省の局長はおろか課長も経験しない異例の形で任命された。退官後は民政党から代議士に出て6期連続当選、〝高文〟同期(大蔵省)の濱口雄幸の内閣で商工相を務めたが、〝翼賛選挙〟で東條英機首相直系の〝刺客〟を立てられ落選。2年後に死ぬ。在郷軍人だった〝刺客〟は、なぜか〝8月6日〟に選挙区と背中合わせの〝軍都〟広島にいて、原爆死した唯一の代議士になった。
伯父は警保畑で、戦時中は情報局の課長もしたが、敗戦後は公職追放を危うく免れ、最終任地の京都から初の府知事選に出て落選。〝蜷川(虎三)幕府7選28年〟の端緒を開く不首尾を演じた。その後は吉田茂内閣の事務系官房副長官、京都地方区で参院2回当選後、池田首相が自民党総裁3選を賭けて佐藤栄作と争った〝吉田学校優等生の激闘〟で、佐藤側についたのを怒った池田の盟友の前尾が、手兵の植木光教を新人候補に推したため、参院3期目の出馬を断念。京都市長に転じて間もなく、消防出初式中に脳出血で死んだ。
灘尾はこの2人と筆者の関係もよく知っていて、官歴・議員歴ともに長い祖父の恩給に基づく祖母の遺族扶助料が最高水準なのを指摘し、家内の老後も安泰だ、と笑ったことがある。伯父が、灘尾が親しく、筆者も〝池田番〟当時の官房長官だった大平正芳と近かった池田ではなく、佐藤側についたため、キミがついていながらなんたることだ、とかなり本気で筆者を叱り、監督不行届で申し訳ありません、と謝ったこともあった。尤も灘尾も伯父の娘婿、つまり筆者の従姉妹の、やはり元内務官僚の息子の亭主が、NHKの〝佐藤番〟なのは、まったく知らないようだった。
〝改革〟の中核だった内務省解体
灘尾は、敗戦に伴うアメリカ占領軍による一連の日本改革政策のうち、社会保障政策全般については、必ずしも否定的には見ていなかった。追悼録的な本に載った、内務省解体に関してほぼ唯一の一般書を書いた草柳大蔵との対談で、社会福祉全般を見れば、戦前にくらべ占領下ではアメリカの物質的支援や指導もありかなり改善した、と評価している。念のため付言すると、灘尾はこの時期、占領軍から公職追放を受けて、あらゆる社会的活動から退いていた。ただし対談当時の社会的評価を反映して、いまでは問題視される、占領軍が後押しし社会党首班内閣が推進した優生保護法も、支持する立場をとっている。
敗戦後の占領軍による〝改革〟は、陸海軍解体を筆頭に、旧指導層の公職追放、財閥解体、農地改革、教育・学術改革など、極めて多岐にわたっているが、軍と並んで内務省解体は、その中核だった。組織面で見ると内務省は、地方局が総理府の外局の地方自治庁、警保局がやはり総理府に置いた行政委員会・国家公安委員会の下に置かれる警察庁、土木局が建設省、社会局が厚生省と労働省、というふうに、バラバラ殺人の死体のように切り刻んで解体された。
警察はさらに、一定規模以上の基礎自治体には独立の自治体警察を置き、それらの連絡調整と自治体警察を置くだけの財政力のない自治体をカバーするため、都道府県単位に国家警察組織を置く、という組み立てにした。アメリカの自治体警察つまり独立した市警察と住民が選挙で選ぶ保安官事務所、そしてFBI=連邦警察という組み立てを丸写しにした。前述した〝大阪市警視庁〟は、この結果生まれた一時的な呼称だ。占領軍司令部の動機が、特高=特別高等警察つまり共産主義者・無政府主義者の取り締まりを目的に設けられ、猛威を振るった思想警察制度の破壊にあったのは疑う余地がないが、オマケがひどすぎた。さすがに占領終結直後に吉田内閣が、社会党の猛反対で大揉めしながら国会で警察法を強行改正して、国警と自治体警察の2本建ては消滅した。
地方自治も、地方自治庁―都道府県―市長村として中央の権限を弱め、地方を国と対等の立場に置く考え方は、アメリカの連邦政府と州政府の関係、もともとアメリカの基盤はあくまで州で、連邦は外交や軍事では国家を代表・主導するが、内政は基本的に企画調整機能に止め、実務は州と市・郡が守備範囲を決めて分担する、制度の直輸入の印象だ。
旧内務省の各局は、占領終結後も複数の内閣で〝行政改革〟の標的とされ、有為転変を重ねる。地方自治庁を自治省に昇格させて中央の体制を確立し、専任閣僚を置いたのは当然だが、いまの総務省は甚だピンとこない。旧総理府に〝寄宿〟する雑多な政府機関や、郵政民営化から落ちこぼれた旧逓信省―郵政省所管の電波・放送行政と、栄光の内務省をなぜ一緒にするのか、という感がある。建設省から〝列島改造〟の風に乗って分離した国土庁が〝復縁〟した際、元通り建設省と呼ばずに国土交通省と呼んだのも、不可解だ。
かつての内務省社会局から独立した厚生省を、内務省解体を機に厚生省と労働省に分離したのは、占領改革で唯一の正解と思われ、灘尾の占領政策評価にもそれが反映したと思われるが、それが行政改革の名のもとで厚生労働省という珍名になったのも論外だ。
非効率は〝立法意志〟そのもの
厚生行政の分野で、医療政策や公衆衛生・防疫政策に関し、国は制度設計や施設整備・財政措置、基本方針策定を担当し、個別医療機関を対象とする医療行政は都道府県、地元の事情を踏まえた公衆衛生行政は市町村を主体とするあり方は、間違いとは思わない。ただ憲法92条の「地方公共団体の(略)運営に関する事項は(略)法律でこれを定める」という法定主義は、中央からの〝通牒〟で行政が一元的に動いた旧内務省の姿にくらべれば、機動性が甚だしく落ちるのはやむをえない。まして95条「一の地方公共団体のみに適用される特別法は(略)その地方団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することはできない」という規定はマトモに遵守すれば、地域にマトをしぼった防疫措置は成り立たない。都市のロックダウンが典型だが、戒厳条項も非常時法制もない憲法は厳守しろ、しかし世界各国同様にコロナ防疫のための都市封鎖を断行すべきだ、などという議論は、ありえないのだ。学術会議をめぐる敗戦下の教育・学術改革に触れた前稿でも述べた通り、現行憲法制定を含めて占領支配下に行われたモロモロ〝改革〟は、基本的には仇敵日本を弱体化しようというアメリカの意図に発した制度変更なのだから、非効率・不都合が生じるのは〝立法意志〟そのものであって、その是正には憲法改定が不可欠だと考えざるをえまい。
昨年大往生を遂げた旧内務省育ちの唯一の宰相・中曽根康弘の〝戦後政治の総決算〟の悲願は、まだまだ達成されていないのだ。
(月刊『時評』2021年4月号掲載)