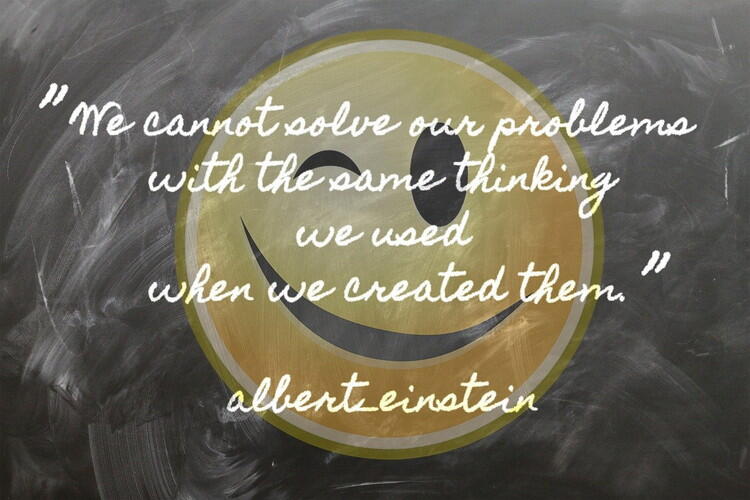
2025/03/03

日本学術会議の一部学者への任命拒否を野党や左翼メディアが非難しているが、この会議はそもそも当初から日共の陣地だった。国の行政機関として税金が投入され任命権は首相にあるのに、拒否されたから〝学問の自由が侵される〟というのでは、学者としての独立的知的人格が伴わない羊頭狗肉のペテン師集団と呼ばれて当然だ。
Tweet学会として成立?〝未来学会〟
90年余生き、見習い期間を含めて67年9か月を報道・言論の場で過ごしてきた筆者にも、〝学会〟なるものに参加していた時期が2度ある。1回は半分シャレのような感じで「日本未来学会」に関与した。
〝未来学会〟にそれなりの活動実績があったのか、そもそも学会として成立・存在していたのかには、疑問の余地がある。前回も触れたが、第2次世界大戦後の混乱が一応修復され、新しい技術革新が進み始めた1960年代前半に、ハーマン・カーンやデニス・ガボールなどの中欧ユダヤ系の在米学者が先陣を切り、日・米・仏の政府機関や英の王立、西独の経団連の研究組織がそれぞれ1985年を共通ターゲットに、新しい社会像を目指す政策づくりの競争を始めた。
カーン、ガボールの著作を日本に紹介した大学教授の坂本二郎・香山健一、官庁エコノミストの林雄二郎(香山はGaborをアメリカ流にゲイバーと表記し、林は元々ハンガリー人だからとしてガボールと呼んだ)に加藤秀俊ら少壮学者、星新一・小松左京らのSF作家、イラストレーターの真鍋博、来日したカーンとの数少ない対談相手だった筆者も末席に連なってグループができた。大宅壮一だったか藤原弘達だったか、いずれにせよ当時の大評論家に、〝学会と名乗るが学問と関係ないもの二つあり、創価学会と未来学会〟とからかわれつつ、ホテル・オータニの一室で設立世話人会かなにかに出た記憶がある。
しかしそれ以降、〝学会〟として集まって議論した憶えがない。マスコミ分野全般にわたるその日暮らし的な繁忙を続けていた筆者が欠席していたのかもしれないが、真鍋、坂本、星が早々に亡くなり、香山も早世して、小松・加藤ら関西勢は健在だが東京では軸になる存在が欠けたのが、影響したかも知れない。〝未来学〟自体、いまや死語だ。
由緒正しい「日本倫理学会」
もう一つは「日本倫理学会」。こちらは由緒正しい学会で、東京大学文学部倫理学科には、卒業者はたとえ学職と無縁の職業に就いても学会に入って会費を納め学恩に報いるべし、というジッテ(習俗・掟)があった。哲学科は抽象哲学、思想史は倫理学科、と棲み分けていた東大文学部で、新聞記者志望の筆者が駒場の教養学部から本郷の文学部に進む第1期生となる2年前に退官された、和辻哲郎教授由来のジッテが2か条ある。一つは大学院生から新入生まで教室全員が(といってもせいぜい30人ほどだが)参加する〝1泊遠足〟を毎年晩春に実施すること。もう一つが卒業後の学会加入だ。
『風土』や『人間の学としての倫理学』で知られる〝和辻学派〟にとって、ジッテは善悪以前の人間集団を律する根源である。そのジッテが、和辻教授の次に教室を主宰された金子武蔵教授の代に、1か条増えた。万難を排して(たとえ無経験・運動音痴の女子学生を外野に立たせてでも)チームを編成し、毎年秋に農学部グラウンドで開かれる文学部伝統の全学科対抗野球トーナメント大会に、不動の1番打者・2塁手に金子武蔵選手を起用して出場すること、だ。大正期の日本財界の総帥・金子直吉の子息で日本哲学界の泰斗・西田幾多郎の女婿であり、ヘーゲル、ヤスパース研究の権威として国際的に著名で、謹厳峻烈な学風で学生に畏怖された金子先生は、教室外では明朗快活な人柄で、和辻教室の助教授時代から、在職中にこの大会で優勝するのが学問領域以外では唯一の念願だった。
教室を継いで3年目に、東大野球部史上2年だけ存在した独立した2軍の教養学部野球部から、投手(かく申す筆者)と都立1中・旧制浦和高校で野球部だった万能選手の2人と旧制学習院高等部野球部のキャッチャーが入ったのだ。先生は狂喜し、この大会で優勝したらキミらに優を与える、と断言された。
豈奮起せざるべけんや。オール素人の軟式野球だから、低めに投げていれば三振かピーゴロ、せいぜい内野ゴロにしかならない。教養学部組が交替で投手とショートを務め、大差をつけるまでは2塁方向もカバーする。捕手は学習院の本職、1塁は大学院生で運動神経のいい城塚登(のち東大教養学部教授)が固める。4人を二手にわけ、間に置いた選手が4球か敵失で出塁したのを長打で一掃すれば、まず勝つ。実際に2年連続で優勝し、金子先生ご担当の倫理学概論と近代精神史の2科目で、2年分4つの優を頂戴した。
そこまではいいが、新聞社に入社が決まった卒業寸前、金子先生に教授室に呼び出されて、思ったより優の数が多いし卒論もそこそこ書けているから邪道に走らず大学院に進んで学職を志せ、といわれたのには閉口した。基礎学力も語学力もないのは百も自覚している。優が多いとの仰せですが、先生の4つは野球で頂戴したもので成績の評価ではありません。こう申し上げてご容赦いただいた。
その学会も、学士会や日本記者クラブとともに高齢を理由に退会して久しいが、会員時代にはときに学術会議議員選挙投票に関する文書が届いた。例外なく無視して捨て置いたが、あれは党派性、正確にいえば日本共産党の党派支配が目に余るとして再三改められた、議員選出規定の2代目の時期、学会ごとに票を取りまとめていたころだったろう。
日本倫理学会、少なくとも東京大学倫理学科では、学術会議は関心外だった。帝国学士院いらいの伝統を誇る翰林院・国家アカデミアである日本学士院に、和辻・金子両先生が推挙されている。それと較べれば日本学術会議は問題外、売名学者のゴミ溜め、政治的には日本共産党教員細胞の一形態にすぎない。
「戦争加担の反省」は真っ赤なウソ
日本学術会議が生まれたのは1949=昭和24年、GHQ(占領軍総司令部)にマッカーサーが君臨していた敗戦・占領下の真っ只中だ。戦前・戦中に学会が戦争に深く加担したのを反省して生まれた、というのは左翼が唱える真っ赤なウソで、実態は占領支配の一環である愚民化施策の一端だ。ノーベル賞を受けた物理学者が〝戦争協力の反省から生まれた〟と書き、バカ・マスコミが伝言ゲームをしているが、学問には専門・非専門がある。物理学に秀でた彼の政治知識は、筆者の超貧困な物理学の知識程度の水準だろう。
GHQは敗戦―占領開始翌年の1946=昭和21年に、日本の教育制度の根本的な組み替えに着手した。そして1872=明治5年の学制頒布いらいドイツに範をとって営々と構築してきた、序列化した道府県立旧制中学―旧制高校―帝国大学を行政と知識社会の中枢を担う人材の養成所とし、工・商・農などの分野は中等教育から専門化して実務者を育て、この分野には別途高専・大学を置いて研究者や指導者をつくるという、6533制が基本の複線教育システムを廃止し、ノッペラボーな6334制単線のアメリカ式大衆教育システムへの切り替えを強制した。
その〝学制改革〟のラフなデッサンは、反日・親支那の民主党政権下のアメリカ本国から追い出され、GHQ民政局に拾われたニューディール左派の〝学者〟が描いたが、彼らにそれ以上を構想する能力はない。そこで1947年に旧制高等小学校と中学校・女学校の初級を一本化し、義務教育の3年制新制中学を発足させた機会に、アメリカから〝教育使節団〟を呼び、後期中等教育・高等教育の肉づけや、各級地方自治体での教育委員会設置など、具体策の構築を図った。
〝マック教育改革〟の完成記念碑
帝国学士院に対抗する日本学術会議の設立も、その一環だ。1949=昭和24年、帝国大学を廃止し、4年制の国立大学をアメリカの州立大学並に駅弁を売る程度の駅のある町に置く、新制大学の発足に合わせて民政局のケリー顧問が出席し、設立総会を開いた。ちなみに旧制中学の上級2学年を分離して1年拡大した新制高校の発足は、新制中学と新制大学がそれぞれスタートする年の中間に当たる、1948年だ。47年が中学、48年が高校、49年が大学と、年次進行で学制を切り替え、最終年度に前年に法制化した教育委員会発足、日本学術会議創設と続け、教育分野の占領政策が完成したことになる。
敗戦・占領下の日本庶民はこれを〝マック教育改革〟と呼び、その本質はつまるところ〝3S(スポーツ・セックス・スクリーン)政策〟と〝駅弁大学〟だと断じ、〝63制 野球ばかりが強くなり〟と川柳にした。憲兵と警察、〝隣組〟の在郷軍人や国防婦人会が目を光らせていた戦時下でも、庶民は〝世の中は 星(陸軍)と錨(海軍)と闇と顔〟と川柳で憂さを晴らしたが、「朝日新聞」の記事を咎めて日本軍部もできなかった日刊紙の発行停止を命じた(「朝日」はこれに懲り、〝マック万歳〟の占領政策全面追従に完全転向した)GHQの言論統制下でも、この程度のささやかな抵抗は存在していたのだ。
日本学術会議は〝マック教育改革〟の完成記念碑であるとともに、旧制大学にくらべて格落ち感が強い〝駅弁大学〟教員への〝箔づけ〟を兼ねた。仰々しいネーミングや日本政府に巨額予算投入を強いたのもその現れだ。
そこらの学術会議の現役やOBにくらべれば先輩格の筆者は、〝マック改革〟の渦中で旧制中学最後の卒業生となり、新制高校の3年に横滑りして翌年卒業し、新制大学1期生になった。歴然たる〝マック改革〟当事者であり被害者だ。イマドキの〝学者〟や、テレビの〝ニュース芸人〟らのウソ八百を、的確に看破・論破できる生き証人の立場にある。
当初から日共の陣地
そこでついでにいくつか、学術会議の〝秘密〟に触れると、最初の議員210人は登録された学会員つまり〝自称学者〟が組織票で争う選挙で選ばれ、1947年の最初の参議院選挙と同様に上位半数は正規の6年議員、下位半数は半人前の3年議員となり、3年後の次期改選で任期6年、3年ごとに半数改選の本則通りになった。このとき最初の当選者210人中3人が、当選を辞退している。理由はいずれも49年1月に行われる総選挙に日本共産党公認で立候補するためで、うち2人、風早八十二と渡部義通は当選した。この事実は、学術会議が当初から日共の陣地だったこと。ただし学術会議議員の価値は日共にとって衆議院議員以下だったこと。つまり共産主義の常識で学問は政治の下僕と明確に位置づけられていたこと、を示している。
1949年の総選挙は、新憲法下最初の内閣の社会党首班・片山哲連立内閣が内紛で、後継の連立の片方の進歩党首班・芦田均内閣が昭和電工疑獄で、ともに倒壊したあと、GHQ民政局が蛇蝎の如く嫌っていた吉田茂・自由党内閣が政権に復帰して断行した。ニューディール左派の支援を受けた日共は、この選挙で35人を大量当選させた。学術会議はその流れの中の産物で、だからこそGHQは〝来賓〟を派遣し、別途祝電も打ったのだ。
朝鮮戦争で主従構図一変
この主従の構図は、1950=昭和25年の〝朝鮮戦争〟勃発で一変する。GHQの中枢はGS(民政局)からG2(参謀第2部)に移り、ニューディール左派は放逐される。GHQの対日共姿勢は一変し、前年に当選した衆議院議員や1947年に当選していた参院議員の大半は占領軍指令で公職追放を食った。書記長の徳田球一や敗戦直後に延安(戦時下の中国共産党根拠地)から英雄気取りで帰国した野坂参三らは、密航船で中国に逃亡した。日共系の労組連合体・全労連は解散指令で消滅し、1950年8月には反日共系労組連合の総評が結成された。総評の結成大会も、自らの肝入りでつくったのを誇示するため、日本学術会議と同様に、GHQ民政局労働課長が〝来賓〟で出席し、祝辞を述べた。
学術会議も総評も、占領下・朝鮮戦争中は〝主命〟に沿っておとなしくしていたが、1952=昭和27年4月の占領終結後は、本性を現す。総評は日共とは一線を画し続けたが、1953=昭和28年の破壊活動防止法制定に反対する〝労闘スト〟で〝ニワトリがアヒルになった〟と評される変貌を遂げ、米ソ冷戦下のソビエト共産党に直結する社会主義協会―日本社会党左派とブロック体制を組んで、〝政治闘争〟を激化させた。
学術会議は、日共で〝50年問題〟と呼ばれる徳田・野坂の主流派と、志賀義雄・宮本顕治の反主流派との抗争が飛び火したため、外向きの活動を停止する一方で、内に籠もって日共両派と社会党左派系(つまりソ連系)が三つ巴の勢力争いを続ける。このため学術会議は社会的信用を完全に失墜し、〝自称学者〟の選挙ごっこでは体質改善はできないとして、所属学会で議員を選ぶ方式に変えた。
しかしこんどは、左翼の牙城である憲法学会を例外として概して無関心な文系学会と、科学研究費の分捕り合戦が絡む理系学会との温度差や、一部の学会内部で党派抗争を続けたのが問題になり、現行の議員選出方式に改められたとされる。その〝現行方式〟もいい加減で、改選を機に辞める議員が実質的に後任を推薦し、その数が定員枠を超えればボス議員の談合で105人の定数に絞り込んだリストを内閣に提出し、任命権者である首相がメクラ判を押して自動承認していたようだ。
タックス・イーターへの反省無く71年
いうまでもなく日本学術会議は独自の設置法を持つ国の行政機関で、運営は税金で賄われ、特別職公務員である議員の任命権は首相にある。人事の仕組みは下級裁判官のケースと同じだ。司法試験をパスした裁判官志望者は、法務研修所を終え、判事補となる。10年の経験を積めば、最高裁判所事務総局があげる名簿に基づき、首相が判事に任命する。
任命された判事が法定の10年の任期を終えて更新・勤続するときも、同じ手続きを踏む。そのとき任命権者の首相は名簿をそのまま承認するが、当然ながら一切の審査がないわけではない。新しく判事になる見習い裁判官や下級判事の個別事情を首相がすべて知っている道理はないし、知る必要もないから、〝司つかさ〟が積み上げた判断を首相が行政トップとして承認し最終責任を負うわけだ。
名簿の作成過程では、裁判所行政の頂点に立つ最高裁判所の裁判官会議やその意を受けた最高裁事務総局が定めた規範・職務規律・評価基準に沿い、高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所が、それぞれのレベルに応じ名簿作成過程で審査を行うし、恆常的に人事異動による統制も機能している。
ところが学術会議の場合は、議員とは別に事務局も抱えてはいるが、行政組織としての最低限の規範・職務規律・評価基準がない、〝学問の自由〟という大義名分を盾に、議員が漫然と無秩序・無規律を続けてきた。こうした姿はタックス・イーター、税金食いのあり方として問題に決まっているが、この点の反省が成立から71年、学術会議の中からはまったく出てこなかったわけだ。
〝学者〟の世間的なルール、けじめに対する非常識さ・独善ぶりを裏書きするというほかない実態だったのだが、今回の騒動を契機に、日ごろ世間の関心外にあった学術会議が注目を集めたのは、遅きに失した観はあるとしても、まことに結構なことだ。
彼らは2007年以降なんの答申もしていない、設置法が求める科学技術政策に関する方策の提言も2010年以降ゼロだ、と自民党の〝文教族〟議員が指摘したのに対し、学術会議元会長の1人は、諮問がないのだから答申のしようがない、と居直った。もう1人は、われわれは年に130回から140回も意見表明や声明を出している、と〝反論〟した。しかし、これらは反論になっていない。諮問がないのは、聞いても意味がない、と設置者が思っている証明であって、存在意義のなさの反映だ。年に意見や声明を100回出そうが1000回出そうが、設置法が定める本来の責務を逸脱した党派的な寝言、偏向した政治的悪態の連発では無視するのが当然、相手にされないのは自業自得にすぎない。
1人1か月100円寄付すれば
日本学術会議に対する税金の投入は、憲法89条『公の財産の支出利用の制限』の、
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」に触れると、元大阪市長・前府知事の橋本徹は指摘している。この条文は私学助成を批判して、税金投入を止めるかわりに企業や個人の私学への寄付税制の緩和・拡大について徹底的に見直すべきだ、という文脈で主張されることが多い。
筆者も委員だった臨教審=臨時教育審議会や財政審=財政制度等審議会でしばしば同じ主張をし、役人衆はその都度、私学も学校教育法などの〝公の支配〟に従っている、と答弁する一方で、文部官僚はともかく、少なくとも大蔵―財務官僚は、審議会後に、ご発言が正論とは思いますが、日本にはアメリカのような寄付文化がないもので当面はご理解・ご辛抱を、と弁解にきていたものだ。
憲法89条に関し、学術会議が、オレたちは学術団体で「教育の事業」ではない、というなら、これも論外だ。学術を離れた教育が存在しないように、教育を離れた学術もありえない。政治ごっこに耽る学術会議に支出される税金はほぼ10億円だが、学術会議に会員登録した〝学者〟は85万人という。日本にそんなにたくさんのガクシャがいるとは、90年生きてきた筆者も初耳だが、それなら1人当たり1カ月100円会費を負担すれば10億2000万円。ぴったり同額だ。学問の自由だ、自主独立だ、と大口を叩くなら、せめて小学生の小遣いにも及ばぬこのくらいのカネは自弁し、国家国民の扶養家族にはならず、そのかわりにガクモンとは無縁の放言を、思う存分ぶてばいいではないか。マトモな学問には、他にも科学研究費はじめ多種多様な補助金・助成金が国庫から支出されているのだから、なんの不便も問題もない。
学術による情報供与への監視を
学術会議の一部のメンバーは、今回の人事問題で、こんなことが罷り通れば日本の学者は社会的発言や学説の表明に際し、圧迫感を抱いたり萎縮したりして、学問の自由・言論の自由が侵される、と強弁するが、呆れた話だ。こんなことで信念を曲げ、学問的発言ができなくなるとすれば、彼は到底学者の名に値しない、最低の独立した知的人格の主でもない。そんな手合いが、学術会議の議員でござい、役員でござい、で通るとすれば、それだけでも、日本学術会議は羊頭狗肉のペテン師集団といわれて、当然だ。
日本学術会議は、創立いらい〝軍事研究〟は行わない、と再三表明してきた。しかし共産主義国として、名目上はともかく実質的にはすべて〝国営〟で、一部は軍が直接関与する〝副業〟も少なくないとされる中国の企業体や、それらと密接に関連する〝学術団体〟や〝研究組織〟と、組織間の人事・情報の交流を決議・協定しているだけでなく、特別職国家公務員である議員個人が、特別職としての〝公務〟に直結する分野で、〝学術交流〟という名の情報供与に深く入り込んでいる、といわれる。すべての技術分野で、民生と軍用の線引きが不可能になっている現代にあって、これは大問題だ。
アメリカでは、留学生からビジネスマンを装う人物、果ては米国籍を持つ〝移民〟の中からも、多数の中国の軍事スパイ、産業スパイが摘発され、刑事訴追されている。ポンペオ国務長官は、同盟国に対して、共同歩調で中国のスパイ行為に対応するよう、呼びかけた。〝民主主義・自由と人権・市場経済という価値観を共有する国〟がスクラム組んで中国の知的財産の盗賊行為、それによる軍事力の強化と世界全域での市場荒らしに対抗しようとしているいま、日本学術会議の現状認識は余りに牧歌的でなければ、確信的な対中従属姿勢だ。国家機関なら当然のこと。仮に民間機関に改組・転換したとしても、〝スパイの協力者〟として、不断の監視が不可欠だ。
(月刊『時評』2020年12月号掲載)