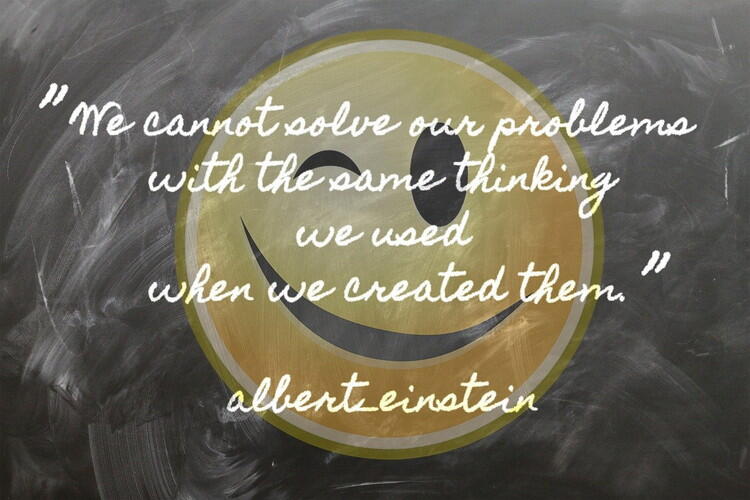
2025/03/03

通算して憲政史上最長の在任記録と言えば聞こえはいいが、7年8カ月の安倍政権は当人の実力ではなく、文字通り敵となる存在が絶無ゆえの所産だった。その遠因は小選挙区・比例代表並立制にあり、現在の自民党派閥は変化も活気もない徒党に成り下がってしまった。
Tweet苦い前回体験からの学習
安倍首相の退陣表明に驚きはなかった。
共産中国の武漢に始まるコロナ・ウイルス感染症流行の対応に忙殺され、5カ月近く休養がとれない中での持病再発が原因と、本人が記者会見で語った。しかし具体的には分からなくても、東京の酷暑がことに苛烈だった8月に入って、テレビに現れる安倍の表情・挙動のはしばしには、だれもが気づくほど明白な、単なる疲労の蓄積というレベルを超えた病的な異様さが現れていた。高校時代からの持病という大腸の自己免疫性疾患の主治医がいる慶応病院で受診、7時間の〝検査〟を受けたと公表し、1週間後の再受診が明らかになった時点で、政界人やマスコミ関係者のだれもが、退陣は時間の問題と感じたろう。
安倍は13年前にも、第1次政権の首相在任1年と1日で、同じ病気の急激な悪化で突然退陣表明している。秋の臨時国会を開いて衆参両院で所信表明演説を終え、1日の休みを挟んで衆議院本会議で代表質問を受ける日の朝、自らの演説に対する質疑に答えるという当然の責務を放棄しての辞意表明だった。持病の急激な悪化とはいえ、仮にも一国の宰相の余りの不首尾に呆れ、当時の本誌に、議政壇上に血便の一滴くらい落としてもいいから、紙パンツを重ね穿きして下半身を固め、答弁すべきだった、と論じた憶えがある。
それにくらべれば今回は、コロナ禍が1段階・2段階を刻んで一息ついた時点で、次なるフェーズに対処する基本方針を設定したのに加え、自民党の役員任期切れや秋の臨時国会が予定される政治状況を睨んで、それなりに計算された、余裕ある退陣表明だった。本人も記者会見で述べたように、13年前の苦い体験から学び、考慮したのは明らかだ。
2期6年ですべきだった禅譲
しかし筆者は多くのマスコミのように、あるいはそこに出没した多くの論者のように、持病の悪化ならやむを得ない、と思わない。日ごろ叩きに叩いておいて、いざ退陣となれば採点を甘くして持ちあげる、〝弔辞では批判的言及は避ける〟という処世術に走る気もない。もちろん「朝日新聞」に代表される、積年の悪口雑言を改めて一挙にぶち撒け、死屍に鞭打つようなサド趣味もない。しかし、この際いうべきことはいうべきだと考える。その前提でまず指摘したいのは、今回の安倍の出処進退にはやはり問題がある、という点だ。一国の宰相を務める以上、危機に直面することを常に覚悟しなければならない。危機に際し主権と国土と国民を守り通す、そのための強靭な精神力と不眠不休で責務を果たす体力を、常に維持しなければならない。
日米安保条約でアメリカの核の傘に守られているとはいえ、日本の周辺には必ずしも友好的とはいえない核武装国が3つある。急迫不整の侵略に絶対に見舞われないという保証は、どこにもない。たかがコロナ、といえば世界的に見て〝奇跡〟といわれるほど人口10万当たりの死亡患者数がケタ違いに少ないとしても、1500人に達する死者が出ているから、不穏当だと非難する声は出るだろう。しかし、されどコロナ、たかがコロナだ。核攻撃を伴う侵略に限らず、今回のコロナを重症度や感染力で格段に上回る人工悪疫の大流行や、民主党政権がマトモに対応できずに右往左往する醜態を晒した東日本大震災も超える天変地異など、深刻な異変の突発は常に起き得る。そのとき国家国民の安危を一身に引き受けて対処に万全を期すのが、一国の首相の絶対要件だ。
それを的確に自覚するなら、新薬出現で持病が軽快したとしても、過去の失敗も意識して限界を弁え、断じて再び不覚をとることがないよう、心掛けねばならなかった。具体的には、自民党則が数次にわたって改められ、総裁任期2年2期まで3年1期、3年2期、3年3期と伸びる中で、2期6年を終える前に複数の後継候補を育成しておき、この時点で総理総裁の座を譲るべきだった。それなのに一部の側近や腹に一物ある旧式党人の甘言に乗って3期目に入り、党則をさらに改めて4期目にも挑もうという甘言も斥けないまま、3期目の途中で突然の退陣に至ったのは、仮にも宰相の地位にあるものとして、不見識・不覚悟といわれて返す言葉はあるまい。
新記録更新は夢想だにせず
安倍が雌伏5年ののち自民党総裁に返り咲いたときは、へぇ、とは思ったものの、そんなに意外感があったわけでもなかった。民主党政権が断末魔を迎えていた時期、つまり野党・自民党は遠からず政権の座に返り咲くのが確実と見られていた時期だが、自民党総裁の座を争う顔触れが、安倍を含めて帯に短し襷に長しで、だれが勝っても意外でないが、たいした期待も持てなかったからだ。
その後3カ月余で安倍・自民党が野田佳彦率いる民主党政権を衆議院解散に追い詰め、総選挙に圧勝して第2次安倍政権を発足させたときも、テキがあのザマなら勝って当然、という以外に評価の余地はなかった。
当時は筆者を含めた外野席の観客はもちろんだが、安倍本人もこの政権が第2次、第3次、第4次と7年8カ月も続き、第1次のほぼ1年を足せば、安倍の郷土・山口の大先輩の桂太郎が明治から大正にかけて飛び飛びの3次の政権で築いた、首相在任通算記録を超える新記録をつくるとは、夢にも思わなかったはずだ。第2次以降の連続在任で大叔父の佐藤栄作が残した7年8カ月、2797日の最長記録を、実際の退任より20日も早い、しかしそれでも4日は超えた時点で退陣表明する巡り合わせになることも、まったく思っていなかったに違いない。
桂、佐藤の格には遠く及ばず
安倍に記録を塗り替えられたとはいえ、桂太郎は笑顔を振り撒いて肩を叩くのを議員掌握術の常道として〝ニコポン宰相〟と軽く見られたが、伊藤博文・山縣有朋と並ぶ〝長州3傑〟の1人として、長く初期の憲政に貢献した。日露戦争の全期を通じて国政を担い、結果的に伊藤・山縣よりも長く政権を維持した。佐藤栄作は、彼の実兄であり安倍にとっては母方の祖父に当たる岸信介の、〝妖気〟を孕むと評された知謀縦横という面はなかったが、〝吉田学校〟の保守本流路線を愚直に貫き通し、沖縄返還を実現してノーベル平和賞受賞者になった。はっきりいって2人とも政治家として、宰相として、安倍とは断然格が違うといって、いささかの誇張もない。
安倍は在任期間の後半、アメリカのトランプ大統領とケミストリーが合って日米関係、ひいては先進自由諸国との良好な外交関係を築いた。また若干の無用の忖度が惜しまれるとはいえ習近平・中国、なによりも文在寅・韓国と、本来あるべき背筋の伸びた外交姿勢を定着させる成果をあげた。一方で経済・内政面は、再度の消費税小幅引き上げを実現したものの、財政規律を軽んじ、バラ撒き施策と赤字国債の乱発、そして低金利・低成長に終始して、自負するほどの成果には乏しかった。総理総裁として傑出した力量を示したとは到底いえず、大きなキズとはいえないとしても、スキャンダルめいた失点もあった。
物理的に、〝敵〟が絶無
その安倍がなぜ通算でも連続でも憲政史上最長政権の記録保持者になり得たのか。理由は端的にいえば、敵がいなかったから、の一点に尽きる。敵がいない、といっても、安倍の能力・人格が抜群に高くて敵対できる存在がいなかった、というわけではない。文字通り、物理的に〝敵〟と呼ぶほどの存在が、与野党を通じて絶無だったのだ。
その状況を端的に示すのが、第2次以降7年8カ月の内閣支持率の推移、正確にいえば内閣支持率調査の設問の定型である支持の理由、不支持の理由の回答分布だ。この期間の世論調査を当たり尽くしたわけではないし、他の内閣の数値と精密に比較したわけでもないが、安倍内閣の支持率は上がったり下がったりしながら、中位安定というか、他の自民党内閣とくらべて突出して高くなったこともないかわりに、低下の度合いも小さい状態で推移していたといえる。政権末期にはいくつかのミスに武漢ウイルスの感染拡大という突発要因が重なって低支持率になったが、それでも過去の内閣支持率の最低値にくらべれば必ずしも低くない水準を維持していた。
その中で支持するという回答であげる理由のトップが〝他の内閣よりよさそうだから〟で、不支持の最大理由が〝首相の人柄が信用できないから〟とハンで押したように決まっていたのが、安倍内閣の際立った特徴だ。
〝他の内閣よりよさそう〟が、先行した鳩山由紀夫・菅直人・野田佳彦の民主党首班内閣にくらべればマシのようだ、というのか。過去の自民党内閣の水準よりよさそうだ、というのか。この設問でははっきりしない。
〝よさそう〟としながら、〝よいと思う〟とはしていないのは、中立的なるべき世論調査の設問として、穏当とはいえまい。不支持の理由が〝人柄が信用できない〟という断定調で〝信用できない気がする〟とか〝信用できそうにない〟とか婉曲な聞き方ではないのも、意識的か無意識的かは別として、いつまでも左翼気取りが消えない「朝日」のスタンスに引きずられがちな、新聞にもNHKを含むテレビやそこに出没する〝ニュース芸人〟にも共通する、偏向・偏見の現れだろう。
〝他の内閣〟には民主党政権以外に、安倍と総理総裁の座を争った谷垣禎一・石破茂・野田聖子らがトップに立った内閣、さらに枠を拡げて、野に下った旧民主党の枝野幸男や玉木勇一郎、最大限に対象を拡げて小沢一郎や山本太郎を野党横断で担いだケースも考えられるとしても、そのどれをとっても、ジョークにさえならない、というほかない。
政権転落後も続く失態
旧民主党の場合、単に3年4カ月の政権が超無能だっただけでなく、政権を失ってからも、これ以上の失態はありえない姿を延々と晒した。鳩山由紀夫は、下野後に衆議院の議席保持も怪しくなって政界を引退したが、身軽さに口も軽くなったか、中国や韓国訪問を重ねて文字通り土下座姿勢で歯の浮くような迎合・追従を並べる一方、日本政府を誹謗中傷する発言を繰り返した。菅直人は下野後にいったん落選して返り咲いたが、その際も小選挙区では落選、菅内閣で経産相を務め野党転落後の旧民主党で代表を務めた海江田万里と、たった一つの比例復活のイスを争い、僅差で辛くも浮きあがる始末だった。
東日本大震災のときの危機対応の劣悪さ、ことに巨大津波による原子炉の水蒸気爆発が迫る中で自衛隊ヘリコプターによる現地視察に固執し、対応に苦闘する現場をディスターヴしまくった愚行は、いまも非難の的だ。
鳩・菅は政治的に過去の存在だが、現に野党第1党・立憲民主党代表を務める枝野幸男も、菅内閣の官房長官として原発爆発の緊急避難をよびかける役目を担い、(放射性物質が身体に降りかかったとしても)直ちに生命に危険が及ぶものではない、と能面のような無表情さで繰り返していた姿が、有権者国民に焼きついている。これでは、いまなら、コロナに感染しても直ちに生命に危険が及ぶものではない、ただし後のことは知らないよ、と無表情で繰り返すに決まっている、と思われても仕方ない存在だとしか、いいようがない。〝立民〟議員が国会質問で、テレビのワイドショーの〝ニュース芸人〟の口調を真似て政府のコロナ対応の非を鳴らしても、お前らの大将は放射能が降り注いだときになんといったか、と反発を招くのがオチだろう。
出戻り総裁の例、いまだなく
自民党内でも安倍の対抗馬は出現するべくして出現しなかった。谷垣禎一が趣味のサイクリングで転倒して大ケガをし、政治家として再起不能になったのも響いた。石破茂や野田聖子はなぜかマスコミ人気が高いが、ともに自民党議員の二世・三世で、当初は自民党から国会に出たのに平成初期の自民党苦難の時代に後足で砂を蹴る感じで離党し、のちに復党した出戻り議員という共通点がある。
自由党と民主党が保守合同して1955=昭和30年に生まれた自民党は、もともとが合併政党だからシキイが低く、出入り自由の観があるが、総理総裁となるとそうはいかない。国民協同党からの三木武夫・振り出しは社会党右派だった鈴木善幸の例はあるが、出戻りが総理総裁になった例はまだない。石破・野田に関してこの点が議論された形跡がないのは、いまどきのテレビのワイドショー的政治論議がいかに底が浅いかの、例証だ。
自民党は多岐多様な保守勢力の複合体であり、本質は基礎単位を〝派閥〟とする〝連合政党〟だ。自民党政権が圧倒的に長い日本では、政界用語で〝政局〟という自民党内の派閥力学を反映した総裁争いが起き、〝政変〟という総裁交替が先行し、国会の首班指名を経て総理の座が動くのが一般的な姿だった。
そのためには、いくつもの派閥が存在・機能し、派閥間で合従連衡が行われ、政治路線や政策をめぐる党内論争が働かなければならない。ところがリクルート事件を受けた1990年代前半のいわゆる〝政治改革〟で、衆議院の選挙制度が中選挙区制から小選挙区・比例代表並立制に変わり、派閥の合従連衡のメカニズム、ダイナミズムが、失われた。
当時の〝政治改革〟のいかがわしさについて、筆者は1993=平成5年に学習研究社から刊行された、中川八洋筑波大学教授(当時)との共著『対論 政治改革の非常識・常識』いらい、一貫して厳しく批判してきた。衆議院の中選挙区制が必然的に招来する政治腐敗を根絶し、政権交替を可能とする2大政党制を定着させるべく、小選挙区制に移行する一方で、少数政党を保護するための比例代表制と並立させるとともに、選挙・政党資金の公営を推進する。こういう〝政治改革〟の能書きが、実際は不純な動機と不正確な展望のもとに強行された、と指摘したのだ。
中選挙区制は、実質的に派閥という名の保守小党の連合政党である自民党と、本来原理的に一致する道理のない共産党と複数の社会民主主義政党、さらに宗教政党である公明党という多党間で、3から5の議員定数を争う制度だ。競争は激しく、それなりの選挙資金と運動量を必要とするのは避けられない。
しかしそもそも、それぞれの政党・候補者の支持者・受益者が醵金して自らの代表を国政の場に送り出すのは、議会制民主主義の基本だ。常に衆議院の多数を制することを絶対命題とする自民党は、中選挙区制ではどうしても同士討ちにならざるをえない、財界は、中央では自民党内各派に、事業所・工場がある地方では地元候補に対し、資金提供、選挙支援が求められてきた。
それに対抗する野党も、少ない当選枠の中での競り合いを避けられず、総評―社会党、同盟―民社党のブロック関係で臨んできたが、労組の不振で資金と選挙労務の提供に対する負担感が強まる。創価学会も自家用政党・公明党へ物心両面の支援に疲れ果てている。
〝政界浄化〟のスローガンのもとに
そこで財界・労働界・創価学会の3者が、なんとか選挙を合理化・公営化して自らの負担を免れる手はないものか、と密かに談合した。そして創価学会系の論壇誌『潮』の常連筆者の〝学者〟グループを表に立て、販売面の配慮からともすると強面になる創価学会―公明党ブロックに対し卑屈な姿勢をとらざるをえない新聞社の経営幹部を巻き込み、〝政治改革〟に向けた世間の空気を煽った。建前は〝政界浄化〟だが、その実は生臭いソロバン勘定が先行していたのだ。
当時は〝労働戦線統一〟の名のもとに〝連合〟が成立し、総評―社会党、同盟―民社党のブロック関係を整理統合する条件が生まれていた。それを受けて小選挙区制を導入し、久しく〝社公民〟3野党共闘態勢をとって国会対策レベルで歩調を揃えてきた公明党を加えて候補者調整をし、一本で総選挙に臨めば自民党に取って代わって政権交代を実現して政治を浄化するのも夢ではない。こういう方向に世論を引っ張っていったのだ。
そもそも2大政党制は、古くは王党派と民権派、下って資本家党と労働者党というふうに、2項対立の階級社会・政治構造が前提で成立する政治制度だ。19世紀から20世紀半ば過ぎまでは政党政治の理想のようにいわれてきたが、固定化された階級社会・分断された政治構造が大前提の仕組みであって、多様化がキーワードの現代に必ずしも通用するものではない。それを麗々しく20世紀の世紀末に持ち出すのだから、『潮』の常連〝学者〟グループの見識の程度も知れたものだ。
致命的な二つの欠陥
それに加えて、この論法を現実に日本で通用する政治論とするには、他に致命的な欠陥があった。その第1は、2大政党対立は政権担当能力のある政党が二つ存在しなければ成り立ちようがないが、現実問題として社公民にそのための素養も研鑽も決定的に欠如していて、自民党が大分裂して二つにならない限り2大政党実現はありえないが、同士討ちが避けられない中選挙区制ならまだしも、小選挙区ではその展望はなくなる、という点だ。
第2は、民主主義社会の議会政治、議会制民主主義は自分で政治資金を調達するか、支持者・支持団体から集められるもの同士で争われるべきもので、選挙公営といえば美しく聞こえて錯覚する向きも現れないとも限らないが、そうなれば国庫から支払われる資金を一手に握る党主流・執行部の独裁になることは火を視るより明らかで、議会制民主主義の根幹である政党内部の言論・行動の自由が完全に封止され、社会主義・共産主義・ファシズム政党と大差なくなる、という点だ。
30年前に、筆者も中川教授もこの2点を指摘して、いわゆる〝政治改革〟に徹頭徹尾反対したが、現実はまさにわれわれが主張した通りになった。保守政治のあらゆるメニューを漏れなく取り揃え、その中から選択して一つのコースを組み立て、ときには原則に忠実な理念型保守政治、ときには社会民主主義に接近した福祉型保守政治と、派閥の合従連衡によって自由自在・融通無碍に政策の幅を動かすことで日本に活力を注ぎ込んできた自民党政権像が消え去り、柔軟性にも活力にも欠ける、変化もなければ活気もない、そして新しいリーダーが生まれる余地もない、アタマは弱いが押しだけは強いボス議員と党官僚がテキトーに操作できるトップを長期在任させる、徒党に成り下がってしまったのだ。
党内派閥は烏合の衆に
その具体化が、7年8カ月の安倍内閣の存在だったといっても、決して過言ではない。そもそも安倍は、一軍一派の将として戦いに臨んで勝利を掴んだわけではなかった。勝者にはなったが、精魂込めて戦い武運拙く敗れた敗者はいない、という構造の所産で、〝一強〟とはいうものの、その実は〝敵〟が存在しない、いまふうにいえばリアル首相ではない、エア首相だったのだ。
そうした〝政治改革〟の美名がもたらした日本の政党政治の超空洞化は、突然の退陣表明に続いて演じられたポスト安倍の自民党総裁選挙にも、如実に現れている。税金が化けた党の政治資金を一手に握り、選挙に際して議員候補者の公認権と、彼らへの資金配分の実権をほしいままにする幹事長のサジ加減ひとつで、つまるところは〝公選〟の結末は決まってしまうのだ。事実は仕組まれた通りに動き、いまや名ばかりの、政策集団はおろか選挙互助会としての機能も失って名存実亡した自民党内の派閥は、幹事長の思惑通りに動く烏合の衆になってしまったのだ。
〝敵〟の生まれようのない仕組みの中で、凡庸な政権が、むしろ凡庸であることが唯一の強みになって7年8カ月続き、治政の成否ではなく健康問題というアクシデントによって終わりを告げ、後には継続感・安定感はあるものの、さて、前途に期待するなんの論拠もない政権が続く。そこに、税金バラ撒きは要求しても国民負担や財政規律には目もむけない一群が集まる。それが〝政治改革〟がもたらした政治の荒涼たる風景だったことを、いま、噛み締めるべきなのではないか。
(月刊『時評』2020年10月号掲載)