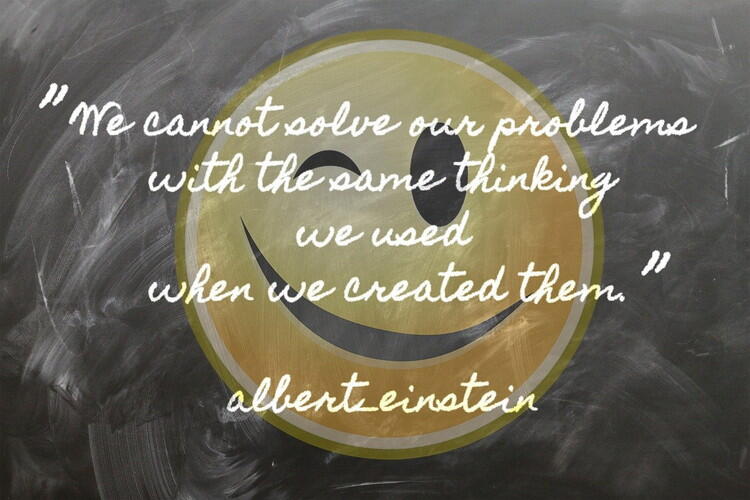
2025/03/03

ジャーナリズムの世界に入って68年目の筆者が、常に心に刻んできたのがこの言葉だ。
〝独立の気力なき者は国を思うこと深切ならず、という矜持は今こそ必要だが、現実社会は逆に、滅多にないほどのポピュリズムが蔓延している。
Tweet
二つの言葉を生き方の指標に
新聞記者を振り出しにジャーナリズムの世界に入って68年目。16年4か月勤めた新聞社を辞めフリーになって半世紀余。この稿をはじめ、いまも多少はものを書く場に恵まれつつ、90歳を目前にする筆者が、ずっと心に刻み、ものを考え執筆するうえの基準、生き方の指標にしてきた言葉がある。
孟子の「恆産なければ恆心なし」。
福沢諭吉の「一身独立して一国独立す」。
この二つだ。注釈するまでもあるまいが、かつては旧制中学で必修、高等教育に進む入学試験でも少なくとも文系では必須だった漢文が、顧みられなくなって久しい。国語力の低下も、生徒・学生の域を超えて社会問題化している。そこで老婆心ながら若干の注釈を加えると、孟子は2400年ほど昔の儒者、つまり小国乱立のシナ大陸で割拠する王のもとを巡り歩き、当世風にいえば治世のコンサルタントの役割を果たした思想家だ。
孔子をはじめこの種の人たちの思想は、王や論敵・弟子たちとの対話を弟子が編纂した〝語録〟の形で伝わっている。前掲の言葉は孟子と梁の恵王の問答を集めた、『孟子』巻頭の「梁恵王篇第一上」にある。原文は、
無恆産而有恆心者。惟士為能。若民。則無恆産。因無恆心。苟無恆心。放辟邪侈。無不為巳。
漢字カナまじりの和文で読み下せば、
恆の産無きも恆の心あるは、惟だ士のみ能くすとなす。民のごときは、恆の産なければ因りて恆の心もなし。かりそめにも恆の心なければ、放辟にして邪侈、為さざることなからんのみ。(朝日新聞社「中国古典選」8 『孟子 上』 金谷治による)
砕いていえば、
それなりのカネがなくても平然として節度ある言動ができるのは、英雄豪傑だけだ。凡人は一定のカネがなければ節操を貫くことができない。もし節操を保てなければ邪道に走り、結局はとめどなくなってしまう。
さらにつづめて処世訓ふうにしたのが、
恆産なければ恆心なし、だ。
「〝同等〟を主張するなら学問が不可欠」
福沢諭吉の言葉は『学問のすゝめ 三篇』にある。引用は「現代かなづかいによる書きかえ」をした岩波文庫版によるが、
「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずと言えり」という衆知の文章で「初編」が始まる『学問のすすめ』は、先に『西洋事情』を世に問い、慶應義塾を開いていた福沢が、「学問の趣意を記して旧く交りたる同郷の友人に示さんがため」に綴った、のちに初篇と位置づけた文章が起点だ。これを「或人」が読み、「独り(故郷)中津の人へのみ示さんより、広く世間に布告せばその益もまた広かるべし」(初篇〝端書〟)と勧めたので、小冊子で公刊したら20万部、ニセの版で無断印刷した分も加えれば、3500万の当時の人口比で160人に1人が読んだ計算(岩波文庫版の小泉信三の〝解題〟)の22万部も発行された。そこで明治5=1872年2月から明治9=1976年11月まで、不定期に「読書の余暇随時に記すところ」の17篇を小冊子で出していたのを、明治13=1880年11月に1冊に(福沢自身の〝合本学問之勧序〟)したのが、現在の姿だ。
「初篇」に続く「二篇」は「人は同等なる事」、「三篇」は「国は同等なる事」。前者は身分差別・階級差別を糾弾する一方、〝同等〟を主張するなら学問が不可欠だ、と論じる。後者は富強の先進国も貧しい新興国も国家としては同等だが、それを裏付けるには国民各自が他力に依存せず独立して自ら生計を立てることから始めねばならない、と説く。
「一身独立して一国独立する事」という言葉は、「三篇」の後半の中見出しに登場し、
「国と国とは同等なれども、国中の人民に独立の気力なきときは一国独立の権義を伸ぶること能わず」として、3条をあげる。
「その第一条 独立の気力なき者は、国を思うこと深切ならず。
独立とは、自分にて自分の身を支配し、他に寄りすがる心なきを言う。自ら物事の理非を弁別して処置を誤ることなき者は、他人の智恵に依らざる独立なり。自ら心身を労して私立の活計をなす者は、他人の財に依らざる独立なり。人々この独立の心なくしてただ他人の力に依りすがらんとのみせば、全国の人は皆依りすがる人のみにして、これを引受くる者はなかるべし」
第2条は、独立心のない者は外国人と対等にはなれない。第3条は、独立心のない者は「人に依頼して悪事をなす」と続く。講釈の必要もなかろうが、要するに自力で生きる国民が揃ってこそ、国家は他国の植民地にならず独立を全うできる。その気概のない者に愛国心があるとはいえない。自力でなく国家など他力に頼る連中が横行したら、同胞を助けようとする人もいなくなる。こういう主張だ。
〝深切〟という言葉は福沢の造語だろう。筆者の見聞する限り、明治初年にこの言葉を使った例は他にないと思うが、深く、切に、国の姿を思い詰める、という意味か。深刻、切実、という言葉を組み合わせて熟語にした点に、福沢の心情が籠もっていると感じる。
孟子を取り上げる背景
この二つの言葉を、筆者はどう捉えてきたか。そしていま、この状況下で二つの言葉を取り上げる所以は、どこにあるか。
まず孟子だが、旧制中学入学早々、漢文の授業で聞いたのが最初だと思う。そのときの印象は記憶にないが、筆者は当時から、将来は現実政治と政治史・政党史について報道・研究・論評に当たりたい、と思っていた。
その背景に祖父が内務官僚出の民政党幹部代議士だったこと。東條英機に睨まれ〝翼賛選挙〟で陸軍在郷軍人の〝刺客〟(この男はなぜか8・6当日に島根県西部の選挙区から中国山脈を越えた〝軍都〟広島におり、原爆死した唯一の衆院議員になった)を立てられ6期連続当選した議席を失い、翌年急死したこと。祖父からも旧制中学の校風からも、戦時下で時流の反米英軍国主義とは正反対の、自由主義思想を学んだこと。家庭にも政治・時局の話題が多く、教科では歴史が一番好きだったこと。これらが影響したのだろう。ただ政治家になろうとは当時も全然考えなかった。
閑話休題。祖父の落選と急死、再度の空爆被災、父親の戦後混乱に巻き込まれた果ての破産。そのあげくの一家離散、大学の寮に転げ込み、19歳4か月で日本育英会の奨学金と週6日の家庭教師で、完全自活した。
それでも志は変わらない。筆一本で立とうと思えば、それ相応の能力と生活基盤を築く必要がある。とりあえず新聞記者になり修行しようと思い、朝鮮戦争休戦と旧制・新制大学の2学年ダブル卒業の空前の就職難の中、幸運にも産業経済新聞大阪本社に入れた。
大阪で6年半修行し、東京政治部に移ってほぼ同期間を経て、入社13年で論説委員を兼ねた時点から外部執筆を始め、独立準備を進めた。半世紀以上昔の当時は、草創期のテレビの報道面は系列新聞社が支配している。週刊誌は出版社系と新聞社系で10誌ほど、月刊の総合雑誌は出版社系と新聞社系・各種団体系で10誌を超えた。敗戦・復興期の活字文化の最隆盛期で、社によって規制の強弱に多少の差はあったが、新聞記者の外部執筆は他流試合と呼ばれて、活発だった。
土屋主幹による外部活動の奨励
産経は規制・拘束が緩かったが、そこに朝日新聞で、内外政治の笠信太郎・外信の秦正流・社会の入江徳郎と並び、経済で広く活躍する土屋清が、笠・秦ラインが進める左翼路線を嫌って産経に移り、論説主幹・編集総長として筆政を統括する。彼は自身の外部活動を一層活発化したうえ部下にも、世間に能力を認められれば社務を十全に果たした余力を充てて大いに外部活動すべし、と奨励した。筆者は系列電波のニッポン放送とフジテレビで不定期に討論番組の司会役を務め、文化放送のニュースに随時コメンテーターとして登場し、さらに創刊直後の産経の『正論』と文藝春秋の『諸君!』中心に署名原稿を書き、週刊誌のアンカー(数ページの特集のまとめ役)もしていた。講談社の『週刊現代』に署名で10週ほど連載を書いたこともある。
テーマは、フランス・アカデミーのドゴール直属メンバーを始め、アメリカのケネディ直属チーム、イギリス王立協会、西ドイツ経団連、日本の経済企画庁も競争に加わって、「1980年」を共通ターゲットに、始動したばかりのビッグ・サイエンスによる工業生産とコンピュータが主導する情報化社会の未来予測を競争で模索する、国家プロジェクトとそれに呼応する民間企業の動きのレポートで、土屋主幹も注目してくれていた。
ところが連載中盤に、元社会部長の出版局長が『週刊サンケイ』の編集長を引き連れて論説室に、ライバル誌に看板企画を書くとは怪しからん、と怒鳴り込んできた。そのとき土屋主幹はいささかも動ぜず、出版局長に、キミたちは俵クンにこの企画で連載を書けと依頼したのか、と聞き返した。依頼されなければ書きようがない、足元に書ける筆者がいるのに執筆を依頼しなかったキミらの落ち度だ、反論があるか、と追い払ってくれた。
フリーになるなら事前準備を
土屋主幹に、キミの出演料や原稿料は給料より遥かに多いはずだが、税務処理はどうしているか、と聞かれたことがある。給与所得者の雑所得として白色申告で処理している、と答えたら、それじゃ必要経費の概算率が極端に低くて大半を税金に取られてしまう、本業を著述業に変え給与は副収入にしなさい、ボクは長く政府税制調査会委員をしていて当局に聞いてこの方式で通しているから問題ない、という。主幹はそれで通るでしょうが私ごときチンピラは多分通りません、当面武士の一分でヤセ我慢します、と応じ、昔気質も極まる、と呆れられたこともあった。
雑談中に「恆産なければ恆心なし」が話題になり、私のモットーだ、といったら、土屋主幹は、ボクもこの点をずっと意識してやってきたがキミもそうか、この道で生きようと思えばそれが鉄則だよな、といったものだ。フリーで筆1本の言論の道に立つなら、権力に圧迫を加えられても、主張が対立する集団から妨害されても、執筆先や出演先に干されても、毅然として3年は食っていける〝恆産〟がなければ自らの立場を貫けない、というのが土屋主幹の主張だ。招聘した水野成夫会長が退陣したのに伴い、彼も退社した直後に筆者も退社・独立したが、当然このときにはそれなりの〝恆産〟はない。だが署名の、あるいはテレビに顔を曝す仕事だけでなく、無署名のアンカー仕事が第2の定職になって〝恆産〟の乏しさを補った。そうした備えのないフリー転身は考えられなかったし、フリーになるなら事前準備は必須といまも思う。
大新聞・小新聞を分かつもの
福沢に関していえば、そもそも筆者が育った産経新聞は福沢の時事新報の流れを汲んでいる。日本の新聞史と無縁の人には信じがたいかもしれないが、明治時代の新聞には大新聞(おおしんぶん)と小新聞(こしんぶん)の別があった。いまの新聞でいえば、朝日・毎日は生まれながらの小新聞。読売には大新聞の残滓も若干入っているが本体は小新聞にも入らぬ新興紙。産経が多くの要素を交雑しながら最も大新聞の系譜につながっている。
大新聞・小新聞を分かつのは、部数や経営の規模とは異質の尺度だった。大新聞とは政治記事主体の政論新聞で、明治時代に薩長藩閥体制から疎外された旧幕臣や、新しく登場した西洋型の知識層が創刊・執筆し、彼らに共感する層が購読した。小新聞は社会ダネ主体、市井の出来事を伝える江戸期の瓦版の後継格で、商人層を主な読者にしていた。大小を区別する決定的な一線が、花柳界の消息を一切黙殺するか、売り物記事にするかの違いだ、という笑い話のような言い伝えがある。
朝日・毎日は大阪の小新聞が、日露戦争で一挙に大衆読者を獲得して東京に進出、全国紙化した。読売は関東大震災3か月後の大正12
=1923年12月に、病気の大正天皇に代わって帝国議会の開院式に臨んだ摂政宮(のちの昭和天皇)が狙撃された〝虎ノ門事件〟の責任を取って警視庁を辞した内務官僚の正力松太郎が、援助を得て買い取った東京の小新聞を土台に創刊。社会面に新味を出して東京のサラリーマン層に浸透、太平洋戦争で紙勢を伸ばし、戦後関西に進出した。
産経は大阪市内の毎日新聞販売店主が出したローカル紙にも及ばぬ地域紙を足場に、戦時統合で群小紙が大合同した成り立ちだが、編集の中枢は大阪時事。本拠の大阪では戦後長い間、社長は大阪時事出身で、編集局長はやはり大新聞の国民新聞を率いた山路愛山の嫡男という布陣をとり続けた。東京に進出したとき板倉卓造・伊藤正徳を中心に敗戦後も存在していた時事新報を統合。一時は『産経時事』の題号を名乗った。伊藤の「連合艦隊の最後」は東京進出初期の看板連載だ。編集の要所要所に時事出身者が座り、山路愛山の嫡孫は夕刊フジの社長を務めた。その人脈が伝える社の体質・気風が、朝日・毎日の向こうを張る紙面にいまも残る観もなくはない。
自力経営する新聞がとらねばならない立場
最近、新聞社の沿革を反映した記者気質の違いについて考える機会があった。NHKテレビの、読売新聞・渡邉恒雄主筆へのインタビュー番組だ。彼は筆者にとって60年余続く親しい先輩だが、インタビュー中に、毎日の西山太吉記者が沖縄返還交渉に伴う〝日米密約〟報道で罪に問われた事件について触れていたくだりが、気になった。
渡邉は西山記者の行為を新聞記者として当然のこととし、自ら弁護側証人として出廷してそう証言した、と語ったのだが、そこで思い出した。当時彼は筆者に電話してきて、自分は西山に弁護側証人になってくれと頼まれてOKしたが、内田健三(当時は共同通信論説委員長だったと思う)とキミにも加わってほしい、という。内田は受けたようだが、すでにフリーになっていた筆者は即刻断った。 内田とも多くの記者クラブや、後には中曽根内閣の臨時教育審議会で席を共にしたが、外務省記者クラブには彼以外の3人が同時に在籍したことがある。ヒマなとき、渡邉はポーカー組、西山と筆者は麻雀仲間だった。
だが筆者は、西山が罪に問われた情報の入手手段の問題以前に、そもそもこれはニュースではない、ニュースとして記事にすべきものではない、と考えていた。あらゆる外交交渉には機密がある。有事の際の米軍の沖縄への核持ち込みは、日米安保条約があり、日本がアメリカの〝核の傘〟の下にいる以上、ありうる。協定を表に出せないのも、日本の世論の実情に照らしても、核の所在場所を明らかにしない米軍の原則から見ても、当然だ。それをスクープだと鬼の首でも取ったように誇るのは、極言すればワイセツ物陳列みたいな話で、書かずもがなのことだ、と思っていた。いまも同様に考えている。
あのとき筆者は即答したが、新聞社では上司、テレビでは出演契約の相手方で、筆者の師匠というべき存在であり、板倉・伊藤の直弟子の時事新報育ちだった吉村克己に相談しても、言下に同じ反応が返ってきたろう。そこが反権力を記者の本領とする、社会部体質を拭えない根が〝小新聞〟の毎日・読売と、痩せても枯れても、野にあって現実政治に言論の立場で応分の責任を分担する〝大新聞〟の矜持を残す、時事―産経との体質の差だ。
「独立の気力なき者は国を思うこと深切ならず」は、よくいわれているように〝福沢精神〟の核心をなす一語だ。毎度引き合いに出すが、ゼイキンまがいの視聴料という悪銭で成り立つNHKはいざ知らず、自力で経営する新聞は、民主主義国家の共同統治者の一員として、常に〝国〟を、深く、切に、考える姿勢をとらなければならない立場にある。
滅多にないほどのポピュリズム
といえば、いまこの二つの言葉をあげる意味を、読者諸賢はすぐ察するだろう。そう、的確な治療法のない悪辣極まる武漢ウイルスの嵐の中で、国民1人当たり現金10万円を一律でバラ撒く〝政策〟の問題だ。野党が反対のための反対として唱えたアイデアに、NHKを筆頭にテレビが飛びつき、与党の片割れの公明党が同調して安倍首相が屈したのだが、これほどのポピュリズムも滅多にない。
安倍首相は所得が半減以下になった中小事業者や個人を対象に、30万円の現金給付を考え、今年度第1次補正予算案に組み入れ、閣議決定を経て国会提出、審議目前だった。仮にも自立を志して創業した事業主を施しの対象にする、見方によっては無礼極まる発想だが、それでも受給には一定の制約・要件・手続きがある。誇りと自負があれば支給要件を満たしても無視し、請求しなければいい。そこでこの種の法制の最低の節度が保たれる。だがこれでは、公明党支持層の大宗を占める高齢者が多い創価学会員には、一文にもならない。たぶん彼らの突き上げで創価学会中枢が動き、指示を受けた公明党代表が、党所属大臣も閣議決定に署名した補正予算案を取り下げて、1人一律10万円バラ撒き案に差し替えるよう、安倍に迫ったのだろう。
そうだとしたら、筋も理屈も恥も外聞もない、ただのゼニほしさ、欲呆けに迎合する、最低の所業だ。公明党は、小渕内閣の〝地域振興券〟いらい、なにかにつけ、現ナマ寄こせ、と連立相手の自民党の首相に強要し、自民党も結局はそれを呑んできた。その背景には、テレビ主導のマスコミが醸し出す世間の雰囲気も、作用していたに違いない。
我ながら品のない表現だが、筆者がときどき使う、出すのは舌を出すのもイヤだが貰うものならネコの死骸でも貰って皮を剥いで三味線の胴に張って輸出するぞ、というのが戦後の日本人の一部の性根だ、という言葉。これはすでに世界の標準税制になっている消費税を、10年かけて3%の超低税率でやっと実現したのに反対し、〝オバタリアン〟を動員した土井たか子・社会党を頭目とする、当時の社公民野党を諷した表現だ。当時の参院選で彼らに肩入れした大方のマスコミの体質、彼らを勝たせた日本の民度も、どうやらそのころとまったく変わっていないようだ。
「深切」な国民の数を示すべき
率直にいって筆者はそれを、卑しい、浅ましい、と思う。人間はそんなものではあるまい、と考えるのだが、テレビの〝ニュース芸人〟やそのお囃子方のコメンテーターは、今回も〝10万円〟を連呼し、いつ出るのか、早く出せ、と言い募った。そのくせ番組が切り替わると、グルメものや遊興行楽案内、秘境探検やリッチ礼讚になるから世話はない。
今回の手法で唯一の救いは、申告制で求めなければ出ない仕組みにした点だ。届け出は郵送以外、メールでもスマホでも受け付けるが、キカイも通信料も決して安くない、筆者も持たないエレキ仕掛けを持つ一方で、生活が苦しい、明日食うものもない、公の援助を要求する、という連中にロクなのはいまい。
麻生内閣当時のリーマン・ショックのときも、請求すれば一律1万2000円をだれもが受け取れたそうだが、筆者はそんなゼニを受け取った覚えはない。請求手続きせずに権利放棄したのだろう。今回も当然そうする。
渇しても盗泉の水は汲まず、断じて他の施しは受けない心意気の〝同志〟は、いまも少なくないと信ずる。国が悪疫に曝され、苦難に喘ぐいま、「国を思うこと」「深切」な日本人がどれだけいるか、政府は正確な数を示すべきだ。総人口から受給者数を引けば、日本人の矜持・品格のレベルが明確に現れる。
公明党の強要で10万円バラ撒きを決めた安倍内閣も、閣僚は総辞退する。自民党の国会議員も同様だ、2割削減したとはいえ月100万円超の歳費とボーナス、無税の文書交通費100万円を貪り、党では政党助成金と立法調査費も受けたうえに、10万円を取る議員の党名・氏名は、公表すべきだ。公人の税金の使い方に関する国民の〝知る権利〟行使を阻む、隠蔽行為は絶対に許されない。
(月刊『時評』2020年6月号掲載)