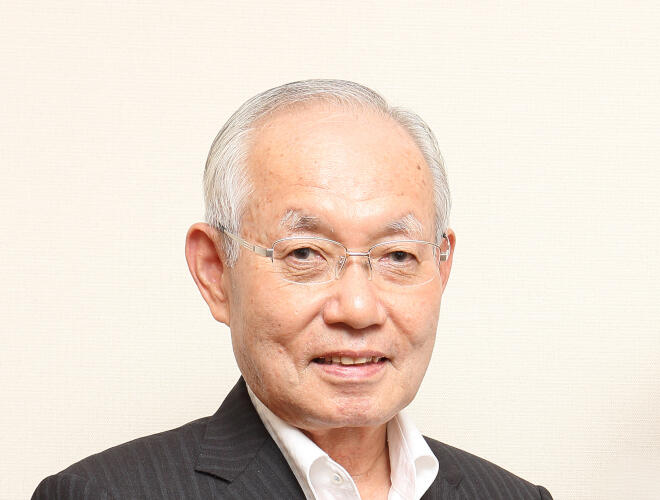
2025/04/02
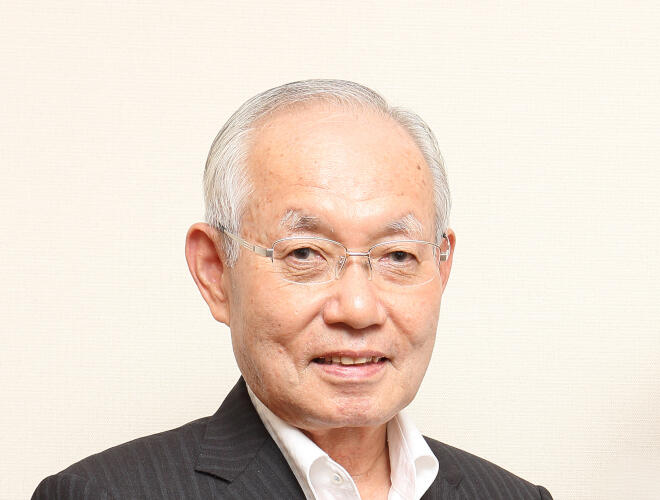
多言なれば数々(しばしば)窮す(老子)
――人は、あまりしゃべり過ぎると、いろいろの行きづまりを生じて、困ったことになる。
ある情報筋によると、カナダの経済学では日本の経済的現状について、次のように論じられているという。
「日本の貧困者は、薬物をやるわけでもなく、犯罪者の家族でもなければ移民でもない。教育水準が低いわけでもなく、怠惰でもない。勤勉で労働時間も長く、スキルが低いわけでもない。(国民の貧困化は)世界に例を見ない完全な政策ミスによるのである」
極めて残念なことだが、この指摘は見事に本質を突いている。しかし、日本の政治にこの自覚が全くなく、政治家は「国民の貧困化を救うことよりも、財政の健全化が大事なのだ」と叫び回っている有様だ。そもそも財政の健全化は国民生活の豊かさの実現や貧困の撲滅の条件と考えるからこそ大切なのではないのか。まるで主客が転倒しているのだが、それで国民の福利を預かる政治家と言えるのか。
メディア論の再論のようになるが、その典型が国民民主党が掲げた「手取りを増やすための103万円の壁を破る議論」である。このレベルの低賃金労働者は、少しの課税でも大きく収入が減少するため、年収が103万円に近づくと働き止めをしてしまい、低所得のまま課税対象とならないように労働時間の調整をしている。
これは低賃金労働者の労働参加意欲を削ぐと同時に、こうした労働者に依存せざるを得ない企業にも事業の縮小などの影響を与え、利益が失われる事態を生んでいる。
この103万円は1995年までは最低賃金のアップに連動して改訂されてきたのだが、この年の自社さ政権による財政危機宣言以来、財政が厳しいからと固定されてしまい、その後、最低賃金が70%もアップしたのに据え置かれてきたのだった。連動していたら178万円になっているはずなのだ。国民の手取り確保よりも税収減を恐れる政策(=政治家)が、若年の、低賃金の労働者の労働参加機会(参加意欲も)を失わせてきたのだった(これこそがカナダの経済学が指摘する大問題なのだ)。
そこで、近年の一般会計税収の推移を見てみよう。近年のボトムは2009年の38・7兆円で、1990年代から見ても最低の水準であった。ところが、近年は順調に伸びてきており、2020年の60・8兆円以降、67・0、71・1、72・1、73・4と増加して、2025年の見込みは78・4兆円である。
一般会計税収は、2020年からの4年間で約12・6兆円も増加したのだ。これで若者や主婦層の働き止めを103万円で継続しなければならないといえるはずもないではないか。減税は無責任だという人は何を見ているのか。そもそも減税は国民への現金の贈り物ではないか。
この103万円の壁議論をめぐって、石破茂総理は「減税は今さえよければいいという考え。次の世代に負担を先送りして、本当にいいのか」と述べたが、黙っていた方がいいのにと嘆かざるを得ない無知蒙昧な認識である。国債は将来世代の負担だと本当に考えているのだ。
ここで、経済評論家の三橋貴明氏の国債についての見解を紹介しよう。
1.政府が国債を発行し支出すると、民間の銀行預金が増える
2.政府の国債発行は、民間への貨幣供給である
3.国債の金利が問題なら中央銀行が国債を買い取れば済む
4.中央銀行が持つ自国通貨建て国債は、政府は利払い・返済の必要がない
5.国債発行の上限は残高ではなく、需要拡大によるインフレ率である
これらの認識は民間の金融資産が大きく伸びている事実と、財務省のホームページでの「自国通貨建て国債のデフォルト否定論」や日銀の国会答弁と完全に整合している正解である。
この認識と石破総理の「国債は次世代への負担先送り論」とは全く不整合であり、つまり「先送り論」は成立しないことは明白なのだ。以前にも野口悠紀雄氏の見解として紹介したことがあるが、「将来国債を償還することがあっても(借り換えで問題ないのだが)、将来の国民は償還のための金を取られた直後にその金額分の国債証書を政府に提出することで、償還金の還付を受ける」のであるから、完全に「行って来い」なのだ。
憲法に規定する「国民が福利を享受する」ことができることが政治である(国民の代表者の仕事である)ことに照らして、日本国の現在地を眺めてみよう。
①2025年の一般会計税収見込みは78・4兆円で過去最高である。この5年間で、約17兆6千億円も伸びている(国は豊かになっている)。
②実質賃金は、2024年5月で26カ月連続しての縮小となった(国民は貧困になっている)。
③上半期の企業倒産は、21・9%増加しており、前期からの増加は3年連続である。
④GDPはマイナス成長である。
⑤個人消費は、4四半期連続で減少している。2024年7月の内閣府発表では、需要不足は年間8兆円にもなり、つまり1995年以降のデフレが継続している。つまり、金利など上げられる状況にはほど遠いのである。日本銀行の利上げなど、逆噴射もいいところなのだ。
日本の国政政治家は、国民の福利の向上のための仕事を何もしていないことが、これほどに明確なのだ。
埼玉県八潮市の県道で大陥没事故が生じてしまった。これは、国債発行が後世への付け回しだなどと言って、十分なインフラの維持管理の強化や管理体制の充実も図らず、点検や長寿命化のための投資や技術開発を怠ってきた結果と考えなければならない。
ベトナム戦争での戦費優先のために、1970年頃からアメリカのインフラは荒廃し始め、1981年には「America in Ruins=荒廃するアメリカ」といわれる時代を迎えてしまった。1930年頃のニューディール政策によって膨大なインフラが整備されて50年も経過したにもかかわらず、維持管理点検や更新のための予算が不十分であったためである。
日本も高度成長期に整備された橋梁や上下水道施設の多くが、間もなく材齢50歳を迎えようとしている。しかし、戦争もしていないのにインフラの整備費を1995年頃に比してほぼ半減させてきたために、必ず「荒廃する日本」の時代を迎える。この事故はその幕開けである。
(月刊『時評』2025年3月号掲載)