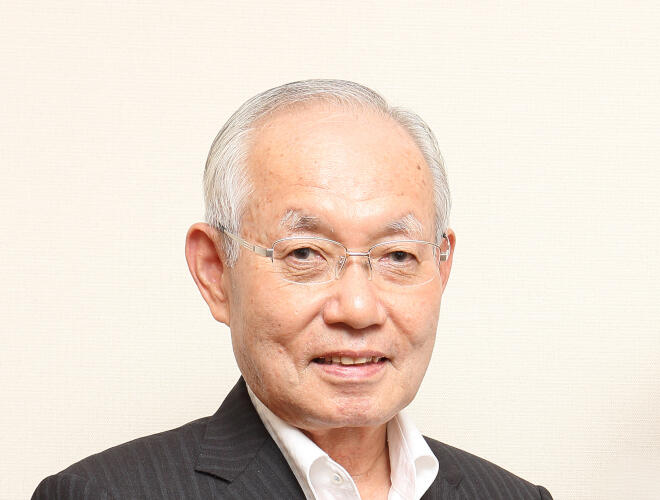
2025/04/02
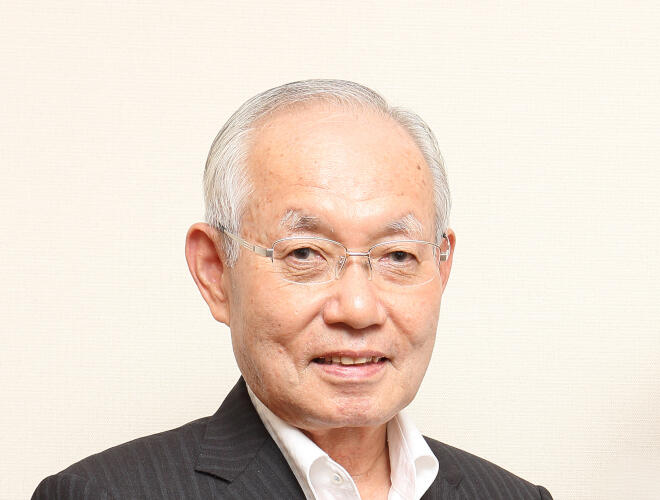
多言なれば数々(しばしば)窮す(老子)
――人は、あまりしゃべり過ぎると、いろいろの行きづまりを生じて、困ったことになる。
能登半島地震を経験してジャーナリストの鈴木哲夫氏は『シン・防災論』という示唆に富む書籍を上梓した。このなかで、特に参考になったのが「行政の限界と政治の役割」という観点で紹介されているいくつかのエピソードである。
カミソリと言われた後藤田正晴氏は1995年の阪神・淡路大震災発生直後に、当時の村山富市首相の元へ駆けつけ、「天災は人間の力ではどうしようもない。地震が起きたことはどうしようもない。しかし、起きた後のことはすべて人災だ」と述べ、「だから生命最優先でやれることは何でもやれ。ルール違反だってかまわない」と述べたというのだ。
これは、官僚は法や制度を超えることはできないが、政治家にはそれができるとの考えから紹介されている。
そこで鈴木氏は、今回の能登半島地震に際して、岸田首相が「ミニ霞が関を作って素早い対応をする」と国会で述べたことを批判し、「まるでわかっていない。法令に縛られる官僚ではだめなのだ」「彼らの職務上の独自行動や臨機応変には限度がある。当然だ。彼らが公平性や法を超えて動き出したら国の統治は崩れる」と言い、「法や制度を破ってでもいま被災地優先でやるべきことを決断できるのは政治家以外にないのだ」と述べる。
先述のように後藤田氏に言われた村山首相は、「現場から離れた官邸では結局何も分からない。ならば現場に決定権を持つ政治家を派遣しよう。そこで現場にしか分からないことを現場ですべて判断してもらって、最優先ですぐに着手しよう。法律違反というなら後で法律を作ればいい。すべて現場で決め、その責任はすべて私が取る」と述べて、自民党の小里貞利氏を現地に派遣して陣頭指揮を執らせたのだ。
だから災害の最前線では、「もう一つの霞が関」ではなく、政治主導の「もう一つの政府」こそが必要だというのである。
この村山氏の判断と行動は最大級の賞賛に値すると考える。大震災発災時には「何しろ、初めてのことじゃからのう」と方言丸出しで語ったことが批判されたりもしたが、実際は見事な判断をしていたのだ。
次のような話も紹介されている。2007年の新潟中越地震では、地域で暮らす高齢者などが集う「お寺」が倒壊してしまった。ところが宗教的建造物の修復などに公金を入れることは憲法で禁止されているため、税金で再建することは難しい。
そこで新潟県や長岡市では「復興基金」という仕組みを作り、財団法人で運用することとした。資金には地方債を使ったが、国費を投入したわけではなかったから法規制をクリアできて、寺の再建への支出を決めることができたというのだ。
東日本大震災でも基金が運用された部分もあるようなのだが、東北出身の小野寺五典衆議院議員は、「新潟県中越地震のことを知っていましたから、その経験を生かして基金にしてほしい。そうすれば自治体がすぐに対応できるわけですよ。でも財務省が基金制度というのを最後まで嫌がりました。やっぱり自分たちの手が及ばなくなる。口が出せなくなる」と述べ、「財務省の言いなりだった民主党政権を崩せませんでした」と財務省の壁を証言している。余談だが、今回の能登半島地震では情けないことに補正予算すらも組めていない。
長々と鈴木氏の著作から紹介してきたのは、政治と行政の機能は異なるのではないかという問題提起に共鳴するからである。大臣や首長が政治家として、行政を指揮指導するのが基本的な形なのだが、その政治家が有すべきファンクションは「行政の上に乗っている」というだけのものでは決してないと考える。しかし、今の政治家にその自覚がまるでないのだ。
何という不幸なことか、半年を優に超える時間が経つにもかかわらず、能登半島地震の被災地のまだ瓦礫の撤去も十分ではなく、未だに上水道すら回復していない地域もあるというのに、今度は100年に一度級とも言われる集中豪雨が被災地を襲った。
なんとか能登半島に残って頑張ろうと思っていた人たちの中にも、「もうダメだ。故郷を捨てよう」と決意せざるを得ない人びとも増えている。これに対してメッセージを出せるのは政治なのだ、「国家・国民の最終にして最大の保険機関である国・政府の責任において、能登半島を以前以上に住みやすい、多くの人が訪れる地域に責任を持って復興していきます。頑張って生き抜いてください」との声明を出せるのは。また、出さなければならないのは政治しかないのだが、水害から何日も経つというのに国政のトップから何の決意も発せられてはいない。
政治とは国民に生きる力を与えるメッセージを出しながら重要な判断を重ねていくものであって、行政の範囲内で行政各部を指揮するためだけの存在ではないのだ。行政のトップであることだけが大臣や知事の役目であるのなら、事務次官が順次大臣になればいいし、古参の副知事から知事に上がればいいのだから政治家など不要なのだ。
法や制度を超えた判断ができ、それが実行できるのは「選挙民の支持を受けた」ことが支える政治家以外にない。災害では人命救済への判断を法規範の解釈のギリギリのところを超えて行い、その結果は次の選挙という形で審判されるのが政治家の使命なのである。
となると政治家が持たなければならない能力とは何かということになる。自己の行政範囲にとどまらざるを得ない行政官を超える俯瞰的な眼力を政治家は獲得しなければならない。
では、その能力をいかに磨いていくのかということになるのだが、やはり意識ある国民とどれだけ深い会話、情報の授受ができるのか、できているのかに尽きるのではないか。民主主義下の選挙制度を持つ国で、戸別訪問を禁止している唯一の国・日本でそれができるのか。
この国は、アジアの人びとからも「日本は没落して行っているが、大丈夫なのか」と心配されているし、何度も紹介するように、この30年で国民が驚くほど貧困化した唯一のG7国となった。本来、政治が解決に向けて最優先で挑むべきこの課題が、最近の二大政党の代表選挙で「まったくと言っていいほど話題にもならなかった」という事実を見ると、述べてきたような判断ができる政治家がこの国にいるのかと暗然たる気持ちを抑えられないのだ。
(月刊『時評』2024年12月号掲載)