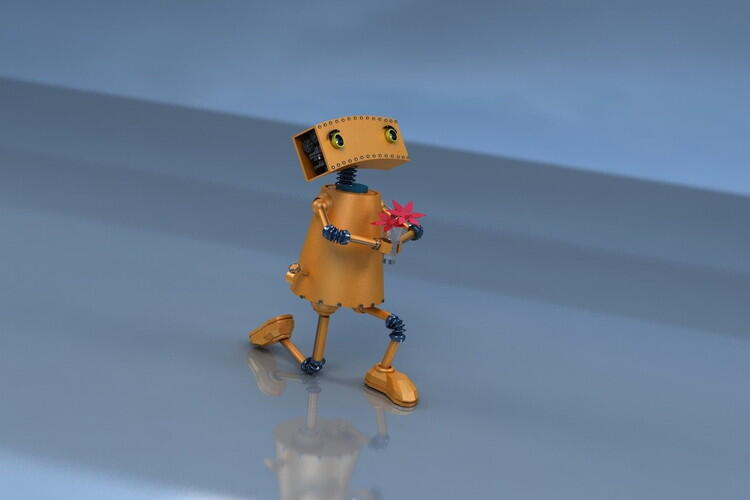
2023/07/06

人工知能は人間を圧倒しつつあるが、われわれの最後の砦は創造性ではないだろうか。1980年代後半、カリフォルニア大学サンタクルーズ校の音楽学教授デイヴィッド・コープはEMI(「音楽知能の実験」の意、エミーと読む)というコンピューター・プログラムを開発し、歴史的な作曲家の作風に似せたまったく新しい曲を機械に作らせ、「AI新時代」対「人間の芸術性の破壊」という賛否両論を巻き起こした。
ユーチューブで「David Cope」と検索すると「バッハスタイル・コーラル」「モーツァルトスタイル・ソナタ」などが視聴できる。バッハ「スタイル」と表示されているように、作曲家の傾向に沿った新曲ということである。
私はバッハの曲をすべて聴いているわけではないし、熟知しているわけでもないので、真正バッハと「バッハスタイル」を比べて「どちらが本物?」と聞かれても、区別はつかない。それくらい(私の耳には)完成度は高く感じられる。
しかしユーチューブの画面の右側に出てくるリコメンデーションをスクロールしていくと「マーラースタイル・アダージョ」が出てきた。クリックしてみると、交響曲第9番の第4楽章を基礎にした別の曲であることがわかる。
これに関しては少し語ることができる。その資格を示すために、恥ずかしい個人的な話をすると、私はマーラー狂で9番には特にこだわっている。生演奏に30回近く行き、CDは50種類以上を集めてきた。一部のCDは数十回かけているから、おそらく私は今までマーラー9番を数百回聴いてきたであろう。
その耳でエミー作曲のマーラースタイル・アダージョを視聴した瞬間、「そのままじゃないか!」(本当はもっと汚い言葉)と思わず吹き出し、爆笑してしまった。もし知らない人が聴けば、私がバッハを聴いた時のように、本物との区別はつかないだろう。
ここまでの話はAIが人間の芸術的創造力に迫りつつある証拠として受け取られるであろう。しかし実際のところは、そのプログラムの生成過程を理解しないと、断言することはできない。
コープがコンピューター・プログラムに「音楽知能の実験」と名付けたのは、自らの音楽学の研究成果を機械によって拡張しようとしたからである。細かい話をすると、プログラムを書くためには、まず論理形式を人間の頭で構成しなければならない。これを「アルゴリズム」という。「何々の時は、こうこうせよ」とか「こんな条件が揃ったら、そういう結論を導け」というインストラクションとお考えいただければよい。この法則を既製のプログラミング言語に書き換えれば、コンピューターで使えるようになる。
ということは、エミーにおいて最も重要な部分はコープの「読み」となる。コープは音楽学者としての知見を駆使してバッハの楽譜を読み込み、そこにパターンを発見した。「この音符の次には、あの音符が来る」とか「こういうメロディーの後は、こういう流れになる」ということである。
これを綿密にすればするほど、バッハの作曲パターンが再現されて、それを法則にして(アルゴリズム化して)、プログラムにする。そうすれば、そのプログラムに、例えば最初の数小節分の曲を入れれば、後は機械が自動的に作曲してくれる。要するに、コンピューターはゼロからバッハ似の新曲を作ったのではなく、むしろコープの見識を応用しているだけである。だからマーラースタイルは「マーラーそのまま」となる。これはコープの業績の秀逸さと称えるべきことであろう。
もし私の理解が正しければ、AIがしていることは「創造」ではなく、人間の知見の「応用」であり「拡張」である。ならばもっと得意なことをやらせればよい。
事のついでにマーラーに再登場いただこう。マーラーは交響曲第10番を完成させることなく亡くなる。マーラーは(私の言い方だが)「横」に作曲していく。オーケストラの曲は主旋律をある楽器が奏でると、別の楽器が伴奏の役を担う。その重層性がシンフォニーの醍醐味だが、マーラーはまず全体のメロディーラインを書き、その後で伴奏を加える。これを「オーケストレーション」という。「横」(メロディー)を完成させてから、「縦」(オーケストレーション)を付けていく。
マーラーが亡くなると、10番は第1楽章だけ「縦」が整っていたが、あとは「横」しかなかった。誰もが「ここまであれば聴きたいな」と思うもので、英国のデリック・クックという音楽学者が1960年代に「縦」を付けて聴けるようにしてくれた。
クックはマーラーの楽譜を研究し、「このメロディーの時は、こういうオーケストレーションになる」というパターンを見つけ、厳密にその法則に従って伴奏部分を創作した。
要するに、メロディーは人間の創造性がなければ不可能なことで、オーケストレーションこそAIが得意とするところであろう。誰かマーラー・アルゴリズムを開発して、10番の別バージョンを機械に作らせたらどうだろうか。
(月刊『時評』2021年6月号掲載)
