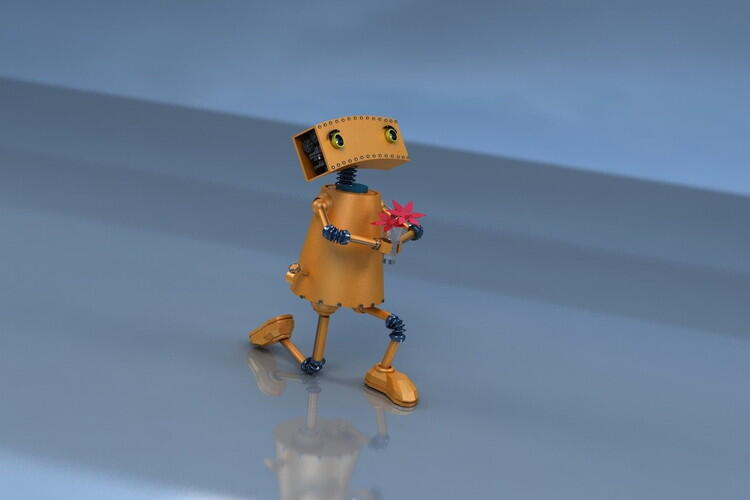
2023/07/06
70年近いAIの歴史は二つの流派の興亡として描ける。「論理派」対「学習派」で、前者が思考=推論を、後者が脳をモデルとしている。人間の推論を精緻化したのが論理学であるが、論理をプログラム化できれば、それは即、人間の思考と同じになるというのが論理派のスタンスである。
初期の大物サイモンとニューウェルは『プリンキピア・マテマティカ』(ホワイトヘッド&ラッセル著)が扱った1+1=2の数学的論証を自分たちのAIシステムで再現しようとした。人間の論理的思考過程を機械上で走らせれば人工知能になると考えたからである。
対する学習派は、脳が行っている物理的な働きをコンピューター上でたどらせれば、結果として人間の心の働きを機械化できるとの立場である。脳は140億のニューロン(神経細胞)からなるが、一つ一つのニューロンは隣の細胞から送られてくる信号が特定の値より大きいと発火して、さらにその隣の細胞に信号を送る。信号を無数のニューロン間で行き来させることで、人間は高度な心的能力を獲得した。
これをコンピューター・プログラムで再現するが、まず多数のユニットを設置して、そこに隣から信号を送る。閾値を超えたらその隣に信号を送り、閾値以下ならば何もしないというように脳の物理的状況をプログラムに反映させる。
1960年代は学習派が優勢だったが、この方法では解けない課題があることが発見されて急速に衰えてしまう。そこから80年代までは論理派の時代である。論理派は人間の推論を一つ一つ文字にして、それをさらにプログラム言語に書き換えるため、人間の思考方法を意識化し、明確にしなければならない。
しかし人間が日常的に認識・行動していることの大半は無意識のうちに為されているので、これらをすべて具象化・細密化させることは不可能である。例えば目の前のコップを取るという人間にとって簡単なことでも、それを機械にさせるとなると、見ること・距離を測ること・つかむことなど、無意識の領域を意識の世界に移さなければならない。これは無理なので、論理派は課題の大きさに潰される。
1990年代以降、再び学習派が隆盛なのはコンピューター能力が飛躍的に向上したからである。先に説明したように、人間の脳を再現するには膨大なニューロンに相当するユニット間の相互作用を計算しなければならないが、それには驚異的な処理速度と記憶容量が必要になる。それでも追いつかず、2010年代前半までは、まだ画像認識ソフトを動かすのにコンピューターを数日にわたって24時間こき使わなくてはならなかったくらいである。
学習派が飛躍したもう一つの理由は研究者の数学的資質である。論理派も数学者が主導していたものの、道具はむしろ論理学だった。学習派は線形代数や微分方程式を用いることで人間の脳のニューロンと似た働きをアルゴリズム化することに成功した。ユニット間の信号の受け渡しにより、画像や言葉の認識で、試行錯誤しながら正解に到達する術を機械が身に付けられるようになった。
論理派の素材が「推論の筋道を言語化した命題」ならば、学習派の肥やしは「データ」である。数学的なプログラムが書けたら、後はそこに大量のデータを読み込ませてプログラムをトレーニングしなければならない。これは個々のユニットのウエートを微調整することであり、最適な設定ができるかがプログラマーの腕の見せ所となる。
マスコミで「AIにたくさんのデータを読み込ませて、云々」という話をよく聞くようになったが、これだと万能プログラムがすでに存在していて、データを与えれば与えるほどプログラムが進化するようなイメージだが、間違いではないものの、必要なのはデータ量だけでなく、というよりも、プログラマーの才能や感性の方がAIシステムの出来を決めると言っても過言ではない。
今回、改めてAIの歴史を振り返ったのは、今は学習派全盛期だが、それで終結するとは限らないというイメージを持っていただきたかったのと、その理由として、最近になって、学習派の限界が語られるようになったからである。
AIの任務は人間の知能の再現だが、学習派のAIが人間にはあり得ない間違いをすることが次々と明るみになっている。近年最も衝撃的だったのは、AIがアフリカ系アメリカ人の写真に「ゴリラ」というキャプションを付けてしまったことである。原因は事前に読み込ませたデータに偏りがあった、つまり白人の写真が多かったことだと見られているが、これはデータ至上主義の限界でもある。
解決策の一つとして提示されているのが論理派の復権である。多数のデータを無作為に読み込ませるのではなく、論理的筋道をきちんと機械に書き入れておくべきとの主張が今一度、見直されている。
これからは学習派と論理派は対立ではなく、補い合う関係に発展していくことが望まれる。第三の道とも言うべきAI新時代の到来である。
(月刊『時評』2021年4月号掲載)
