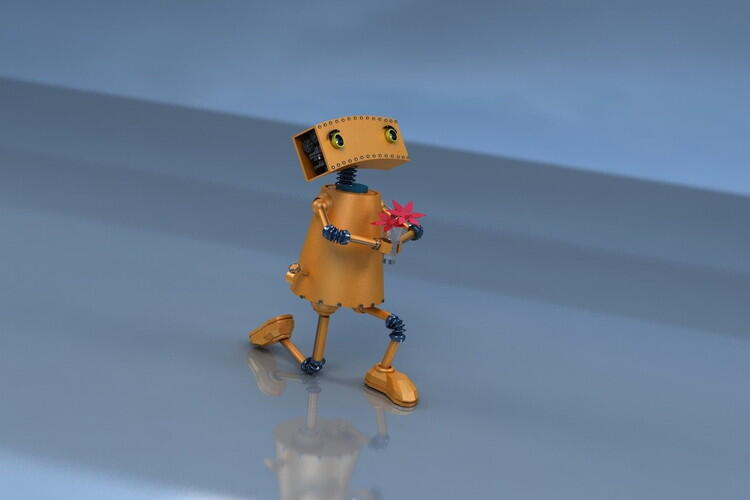
2023/07/06

人工知能(AI)は何かと問う時、AIと「AIでないもの」との間に境界線を引いてみると分かりやすいだろう。個別の事例を挙げて、「これはAI側」「あれはAIの外側」というふうに区分けしていく。先に難しい話をすると、私は具体例の積み重ねである「統計的手法」はAIではなく、人間の認識をコンピューター的なやり方で再現することのみをAIとすることで、AIを狭く、明瞭に定義したいと考えている。
最初からテクニカルな話になってしまったが、事例はいたって不真面目で、一方、時代を共有していない人には意味不明になってしまうだろう。ご自分にとって馴染みの事例に置き換えて、一緒にお考えいただきたい。
この4月から5月の「巣ごもり」中、ユーチューブを利用された方も多かったのではないだろうか。私はこれさえあれば、1日中、何でもできた。日本のニュースから海外のニュース、政府の公式発表から感染症専門家の記者会見、暇つぶしの音楽鑑賞からスポーツ名場面集まで、ユーチューブにはすべてがあるから、これは21世紀の百科全書である。
さて、ある日のこと、なぜか突然「エリック・クラプトン」の名前が思い浮かんだ。ユーチューブで何曲か視聴すると、ユーザーならご存じのように、右側にリコメンド欄があるが、そこにクラプトンの他、マーク・ノップラー、スティングなどの「Money for Nothing」(1997年9月収録)が出てきた。ここから過去に遡る心の旅が始まる。
これを聴いていると、「次の動画」に同じ曲の1985年「ライブエイド」版の映像が出てきた。私は自宅のコンピューターを前に、まず23年前のロイヤル・アルバート・ホールにタイムスリップして、次にワンクリックで35年前のウェンブリー・スタジアムに飛んでいった。
もうこの時点でユーチューブさん、要するにグーグルさんは、私がクリームとか、ポリスとか、ダイアー・ストレイツを聴いていた昔懐かしの洋楽ファンであることを知る。するとグーグルは「このユーザーは1980年代ロックを聴いていた」と判断して、私の心をくすぐる動画を右側に延々と掲げていく。そして私はグーグルの術中にはまり、Totoの「Africa」をクリックする。ただし、ここは好みの分かれるところで、私は1982年のオリジナル版ではなく、2018年に行われた40周年記念ライブ版を観る。
ここで私はグーグルに、さらに余計な情報を与えた。グーグルは今回の私の選択から「このユーザーは学生時代に聴いていた曲を、同じバンドが過去数年間に歌い直したものを好むようだ」と理解し、「あなたへのおすすめ」として、見るも無残にぶくぶく太り、全盛期の高音に届かない初老ロッカーたちの〝昔の名前で出ています〟を並べていく。
いくつか列挙すると(カッコ内は元の発表年と収録年)、イエス「Owner Of A Lonely Heart」(1983年、2016年)、フォリナー「I Want to Know What Love Is」(1984年、2019年)、ヨーロッパ「The Final Countdown」(1986年、2018年)などを自粛中の夜長、ダラダラと楽しむことができた。私はグーグルにたくさんの情報を提供し、広告料を稼がせた分、存分に堪能させてもらった。ちなみに、ここで画面上に中年向き腕時計の広告が表示される。グーグルは私が50代半ばの男であることを承知しているわけである。
遠回りしたが、結論を言えば、私の定義によると、これはAIではない。私のような暇人は世界中に何億人もいるから、これらの数十億を超えるクリックからグーグルが積み上げた統計的傾向であって、必ずしもそこに優秀なプログラマーにしか書けない計算法則が介在しているわけではない。専門用語では、不特定多数の情報群から法則性を導くルールのことを「アルゴリズム」という。つまりユーチューブの検索には天才的なアルゴリズムが使われているわけではない。
その意味では、AIの多くが特別なアルゴリズムで動いているわけではないが、これは程度の差であり、それなりに高度化すれば、AIの境界内に入れて良いだろう。例えば、顔認証は原理的にはユーチューブ検索と大差ないが、計算力においては圧倒的なので、AIとしておきたい。
顔認証の理屈は簡単で、顔のパーツどうしの長さをデータ化できれば、本人確認の正確さは保証できる。目と目の間、黒目(瞳孔)の大きさ、両目の真ん中から鼻までの縦線、両目の端から鼻の下までの三角形、鼻の下から口まで、口の縦と横の長さ、唇の厚さ、頬骨の高さ、両方の頬骨と両方の口の端を囲む台形など、これら数限りない長さを数値化して保存すれば、コンピューターは私が銀行のATMの前に立っただけで、キャッシュカードがなくても現金を出してくれる。というのも、ここまで数多くのパーツ関係が完全に一致する人は世界中に誰もいないからである。
このようにAIは誇大広告されている面と、無限の可能性を秘めている面を兼ね備えている。まだじっくり議論する必要がありそうだ。
(月刊『時評』2020年8月号掲載)
