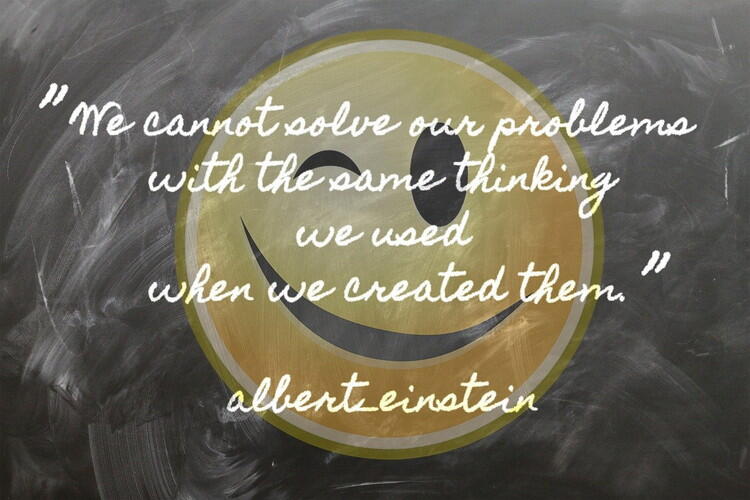
2025/03/03

過去最多の9人が立候補して争った異例の自民党総裁選を経て、10月1日に石破政権が誕生した。
連立政権を組む公明党では、15年ぶりに代表が交代し、石井新代表となった。
また、最大野党である立憲民主党でも代表が交代し、野田元総理大臣が再び代表となった。
永田町界隈や霞が関界隈では、9月中から年内の解散総選挙は既定路線との認識も強かったが、実際に、石破総理大臣は着任前から10月27日の衆議院総選挙実施を宣言した。
本評論が読まれる頃には、すでに総選挙の結果が出て、新たな議会の構成も決まっていることであろう。
こうした一連の目まぐるしい動向を日本の政治のダイナミズムとしてみれば、民主主義が機能している喜ぶべき証左ともいえよう。
他方で、そもそも「国の形」はどうあるべきか、そのあるべき「国の形」をいかにして実現するのか、という政治が本来取り組むべき本質的な議論が十分に深まっているかといえば、正直なところ疑問が残る。
確かに、さまざまな政治的場面で耳当たりのよいキャッチフレーズは飛び交ったが(そして、おそらくは衆議院の総選挙においてもさまざまな声があったことであろうが)、誤解を恐れずにあえて言えば、批判を受けにくい論点に関する抽象的な次元にとどまっていることが多くはないだろうか。
しかし、言うまでもなく、私たちは具体的な世界で生活を営んでいる。
私たちが直面する具体的な世界を直視すれば、日本人は経済的には総体として貧しくなっている中でさまざまな格差が拡大して社会の分断が進んでおり、安全保障環境が悪化しており、地震や豪雨といった自然災害が頻発している一方でインフラは老朽化しており、明るい未来が描けないことを背景として少子化は進み、高齢者を支える社会保障制度は軋んでおり、国家財政は傾いている。
こうした国難ともいうべき状況を一気に解決する魔法はないが、ポピュリズム的で場当たり的な対応を続けることは状況を悪化させるばかりとなるだろう。
こうした状況にあって、熟議を通じて望まれるゾレンとしての「国の形」を提示して国民的なコンセンサスを形成することこそ、政治の基本的な責任だ。
さらに、あるべき「国の形」をいかに実現していくかという現実的で実行可能な筋道を国民に示すことが、いまほど政治(および専門家集団としての行政)に求められている時代はない。
政治にはロマンも必要であろうが、何よりも政治は現実世界を相手にして結果責任を負うべきものであって、「机上の空論」、「評論家的議論」、といった言葉は、政治に
対する最大限の侮辱であることを知らなければならない。
選挙における公約が空手形に終わりがちであるのは、その目標自体が正しくない場合もあるが、その実現手段を欠いているからであることも多い。
例えば、多くの心ある有識者は、日本の中間層が下方に崩壊していったことが多くの問題の根源にあることを指摘している。
政治的目標として「日本の中間層を復活させる」という目標を掲げることは誤りではないだろう。
問題は、それをいかに実現するかという点にある。
政府による再分配に頼ることは、ソ連という社会主義の壮大な歴史的実験の失敗が示す通り、大きな弊害がある。
他方で、労働者の保護を手厚くして、いわゆる正規雇用を増大させることを今さら目指せば、企業の合理的判断としては、雇用自体を控えてロボットやAIで代替するということになるだろう。
雇用の手厚い保護が、特に若年層の雇用の抑制になってしまう例は、いくつかの諸外国で経験済みである。
迂遠なようだが、中間層を復活させる道筋は、相応の所得にふさわしい生産性を多くの国民が身につける以外にはない。
特に、少子化の反転が見通せない日本においては、一人一人の生産性を高めることの重要性は特に高い。
労働分配率を上げるべきとの主張は正しいが、労働分配率をあげるための道筋は、政府の要請ないしは圧力によるべきではない。労働者の生産性向上によって労働分配率が結果として向上するべきだ。
日本の中間層の復活という点から述べてきたが、この議論を敷衍するならば、私たちは市場機能への信頼を基礎とした経済システムを放棄すべきではないということになろう。この原則を忘れてはならない。市場機能を信頼し、生産性向上を図り、
結果として中間層を復活させることで経済の好循環を実現する、という経路を地道に追求することが、現下のわが国には必要な選択ではないか。
同様の「国の形」に関わる議論は、安全保障を含めた外交にも必要であることは言うまでもない。
そうした「国の形」を熟議し、その実現のための筋道をしっかりと国民に示して納得させることを、新しい政治には強く期待したい。
(月刊『時評』2024年11月号掲載)