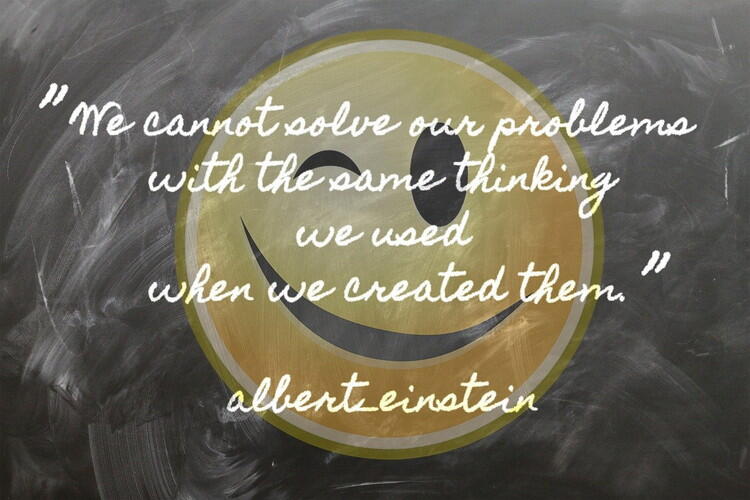
2025/03/03

2024年も半ばを迎えようとしているが、ちょうど30年前の1994年を思い起こしてみたい。
1月には、米国クリントン政権下において、北米自由貿易協定(NAFTA)が発効した。議会での承認に際しては、共和党からも民主党からも賛成者が多くあった。
2月には、かつて長く激しい戦争を戦ったベトナムに対する禁輸措置を米国が解除し、貿易関係が復活した。
4月には、東西冷戦時代に東西間の貿易を長らく統制してきた対共産圏輸出統制委員会(COCOM)が解散している。
そして、同じく4月には「世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定」が署名された。
こうして30年前の世界を振り返ると、自由な貿易の利益を信じ、その円滑化と振興に向けて皆が力を尽くしていたように見える。
その後、WTOの前身であるGATTの域外国であった中国やロシアも、自由貿易の利益を拡大する流れに合流したように見え、それぞれ、2001年、2012年にWTOに加盟するに至った。
歴史を振り返れば、各国にとって正しい政策的な選択として、自由貿易が重視されていたことがわかる。
しかし、近年に至って、自由貿易が死ぬ恐れが生まれているように見える。
WTOは、紛争解決手続き上の重要機関である上級委員会が、委員選任に加盟国が合意できないために、2019年12月以来、機能不全に陥っている。
今年2月から3月にかけて、交渉が難航したために期間を延長してアブダビで実施されたWTO閣僚会議では「国際貿易秩序の礎として、WTOが果たす役割や今後の取り組みの方向性について議論」されたというが、実質的な成果は乏しかったと言わざるを得ない。
米国では、自国経済の振興や保護に政策的な重心が移り、貿易が重要な政策課題として意識されることがなくなってきた。
今まさに、11月の米国大統領選挙に向けてさまざまな主張や議論が聞こえているが、その中に自由貿易を拡大させようという声はない。
そもそも米国が打ち出したTPP(環太平洋パートナーシップ協定)は、2017年に米国が離脱し、その後CPTTP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)として「米国抜き」で2018年に成立した。
バイデン政権が打ち出したIPEF(インド太平洋経済枠組み)は、貿易を通じたマーケットアクセスの要素を欠いており、その行く末については悲観的な見方も少なくない。
こうした状況にあって、かつては泣く子も黙ると言われたUSTR(米国通商代表部)は、いまや閑古鳥が鳴いている。
中国は、経済を武器化して、レアアースなどの輸出制限や、各国からの輸入を禁止するなどの経済的威圧を頻繁に行うようになった。自由貿易よりも国家的目的が優先されているのだ。
そして、国際的に広まりつつある経済安全保障政策の拡大の流れの中で、中国との貿易には警戒感が高まり、過度な委縮も見られている。
また、ウクライナに侵攻したロシアには種々の経済制裁が発動されていて貿易も自由ではない。
いま、世界は分断され、かつて高く掲げられた自由貿易の旗は、くすんでいる。
世界は、グローバルな自由貿易の重要性を見失いつつあるのではないか。
実際のところ、国連貿易開発会議(UNCTAD)が昨年末に発表した報告によれば、2023年の世界貿易額は2022年から5%縮小して約30兆7000億ドルにとどまり、2024年は全体的にさらに悲観的な見通しだという。
そもそも貿易の利益とは、大胆に要約すれば、ある国が比較優位のある産業に特化する一方で、比較劣位産業の財を他国から相対的に安く輸入できる、という国際的な分業の利益に他ならない。
その利益は、輸出側、輸入側の双方においてWIN=WIN(互恵的)となるものだ。
だからこそ、私たちは冷静な合理的判断によって自由貿易の振興を正しいことと認識して、WTOを創設し、また地域の自由貿易協定を結んできたはずである。
そうした冷静で合理的な判断が失われ、自国優先で自国の利益のみを追求しようとすると、結果として、皆が敗北することになる。
それは、講学上の議論にとどまるものではなく、私たちが歴史的教訓として学んできたことだ。
日本の置かれた環境を鑑みれば、特にわが国にとって、自由貿易の重要性は否定のしようがない。
経済構造も、地政学的条件も、歴史的条件も、日本が貿易に頼らずに存立し繁栄することを許してはいない。
今こそ、わが国は、自国のために、そして世界のために、互恵的な貿易の重要性を再認識し、国際的な自由貿易を発展させるために知恵を絞り、汗をかくべき時だ。
(月刊『時評』2024年5月号掲載)