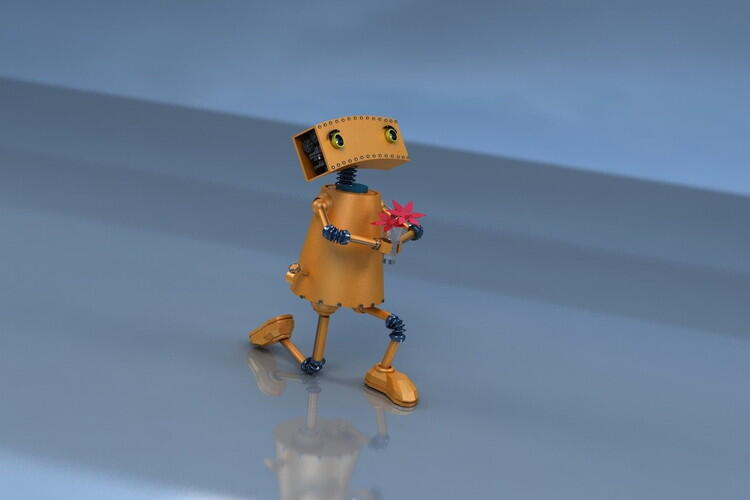
2023/07/06
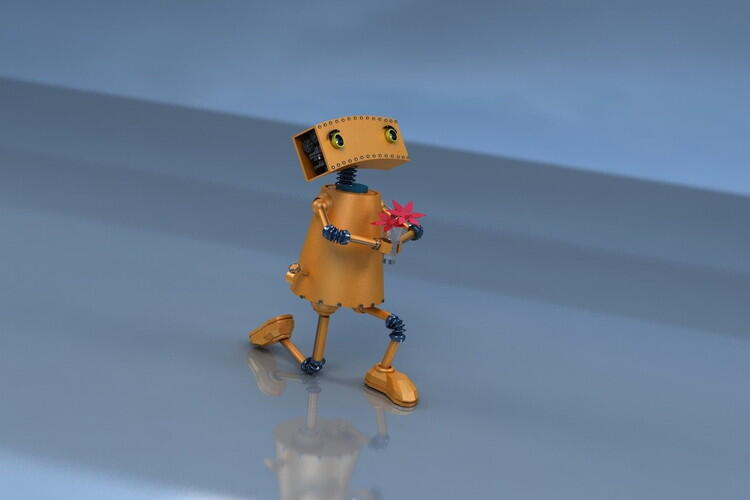
インターネット上にある大量のデータを学習することで、利用者の求めに応じて文章や画像などを自動で生成するAI(人工知能)が急速に進歩している。
例えば、文章生成を行うChatGPTをめぐっては、国会答弁の準備に官僚諸君が使用してはどうかといった議論が(一部では国会論議の在り方を揶揄するように)報じられたが、一部の自治体では実際に業務に導入されるに至っている。
GPTとは、Generative Pre-trainedTransformerの略であり、こなれた日本語はないようだが、あえて和訳すれば、「生成可能な事前学習済みの変換機」だ。
人間が問い掛ければ、それに応じた答えを返すAIであり、例えば「宇宙を舞台として、地球の危機を救うヒーローの物語を書いてくれ」とインプットすれば、十分にハリウッドで映画化できそうなシナリオをあっという間に示してくれる。
文章生成に限らず、AIの実力は、これまで人間にしかできないと言われてきた芸術分野でも大きく伸びている。
例えば、ドイツのアーティストであるボリス・エルダグセン氏は、今年のソニー・ワールド・フォトグラフィー・アワードにAIが生成した「偽の記憶:電気技師」という作品で応募し、一般応募のクリエイティブ部門で最優秀作品に選ばれた。受賞自体は辞退となったが、AIの進歩を示す話題性の大きな事例であった。
さらにAIの進歩は、私たちの生活においても身近に感じられるようになりつつあり、テレビのニュースをAIがアナウンサーとして伝えることも増えている。
そうした中、スイスでは、テレビの画面を通す限り実際の人間と区別ができないほどのAI「お天気キャスター」が登場して話題となった。
こうしたAIの進歩をめぐっては、その有用性が評価される一方で、個人情報の漏洩、著作権の侵害、偽情報の拡散、等のリスクも指摘されている。
国際的には、開発と利用に前向きな日本と、規制の必要性を強く意識する欧州との間の懸隔がある中、今年4月末のG7デジタル・技術相会合において、イノベーション促進とリスク管理のバランスの取り方が議論され、新しい技術のルール整備に関して、①法の支配、②人権尊重、③適正な手続き、④民主主義、⑤技術革新の機会の活用、という5原則に各国が合意した。
こうした動きは、イノベーションのリスクを考えたとき、必要な第一歩であり、前向きに評価すべきものであろう。
しかし、近時のAIの急速な進歩については、そうした議論だけで事足りるとするわけにはいかない。
SF映画のように、AIが自らの欲求や感情を持ち、人間と対立するという未来を予想して危機感を煽るわけではない。
もちろん、そうした可能性はゼロではなく、AIに欲求を与えることは厳に禁止すべきだが、それはすでにG7でも議論されているルールの問題だ。
しかし、AIの急速な進歩が私たちに突き付けている深刻な問い掛けは、そうしたルールを作れば解決できる類ではなく、そもそも人間存在とはいかなるものであり、その社会はどのようなものであるべきか、という根本的で哲学的だが、切実で現実的な問題である。
第二次世界大戦中の英国において、ドイツのエニグマ暗号解読に従事・成功する過程でコンピュータの黎明期の研究を進め、現代において「コンピュータ科学の父」とも「人工知能の父」とも称されるアラン・チューリングは、ある機械が「人間的」か否かを判定するためのテストを考案した。
「チューリング・テスト」である。
簡単に言えば、人間の判定者が通常の言語で会話を行って、相手が機械か人間かを区別できなければ、それは「人間的」だ、と判定されるテストだ。
ChatGPTなどの現在のAIの多くは、チューリング・テストにおいて「人間的」と判定されることだろう。
いまや、私たちは「人間的」なAIと向き合うことを求められており、それはさらに、そもそも「人間的」であるとはどういうことか、という問題につながっている。
歴史上のイノベーションは、人間の生活や社会の在り方を大きく変えてきたが、AIが過去のイノベーションと質的に異なるのは、それが「人間的」だという点だ。
産業革命期のラッダイト運動は、経済原理を理解しない無謀な行動であったと評価されることもあるが、あくまでそれは「人間」対「機械」という構図における出来事であった。
しかし、私たちが直面するのは、「人間的AI」対「人間」という新たな構図だ。
人間が「人間的」であることの本質はどこにあるのか。その答えを知性や知能に求めるならば、AIは多くの人間の職を奪っていくだけではなく、人間が「人間的」であることを阻害するおそれすらあるのではないか。
一部の論者が主張するベーシック・インカムでは到底解決できない、人間存在に関わる問題がそこにはある。
そうした深く困難だが切実な問題について、真剣に考えることが求められている。それこそが、私たち「人間」の営為であるべきだ。
(月刊『時評』2023年6月号掲載)