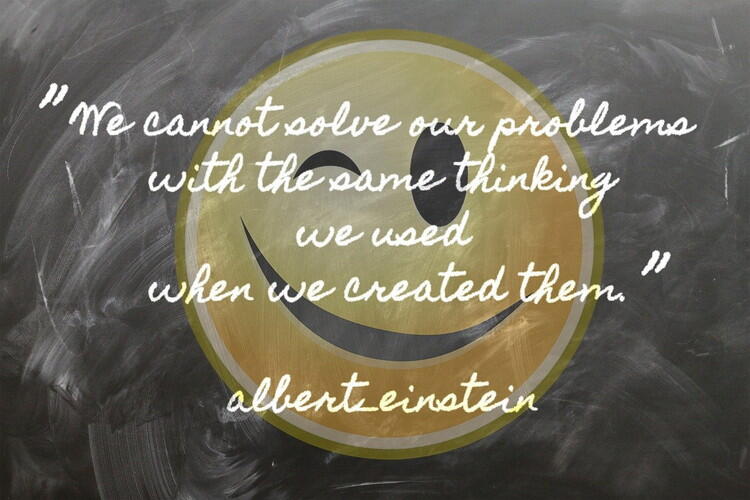
2025/03/03

世界には、同じく民主主義を掲げていても、さまざまな政体がある。大統領制もあれば、議院内閣制もある。一院制もあれば、二院制もある。
さまざまな政体はあるが、これらに通底する根本原理は何かと言えば、人々の支持や信託によって統治権力が正当化されるという原理である。
従って、国家の統治権力を得ようとする者、保持しようとする者は、国民の望みに寄り添うことを旨とする。
しかし、皮肉なことに、そのことこそが民主主義が失敗する理由となることが多いと歴史は教えている。
塩野七生は、「民主政は、民主主義者を自認する人々によって壊される」と述べた上で、古代のアテネの歴史を引き合いにして「われわれはペリクレス死後のアテネと同じに、国民のニーズを満足させることとその国民に寄りそうことだけを考えて実行したあげくに、自滅していくしかないのであろうか」と問うた(文春新書『誰が国家を殺すのか』)。
古代ギリシャまで遡らずとも、満州事変後の日本の転落の歴史において、国際的孤立の契機となった国際連盟脱退もまた、国民の望みに寄り添った結果であったと言われている。
国際連盟脱退の主犯と言われてきた松岡洋右は、実は脱退に反対であった。国際連盟による制裁を回避するためという理由をつけながらも、世論動向を受けとめた本国こそが国際連盟脱退を決定したのである。
日本の転落の歴史において大きな意味のあった三国同盟の相手であったドイツにおいて、あのヒトラーが政権を掌握したのも民主主義的な普通選挙を通じてであった。
1919年に結成されたナチスは、13年後には第一党となり、1933年にヒトラーが首相となる。選挙においてナチスは、経済的苦境にあった国民の望みに応えることを訴えた。彼らの宣伝文句は「我らが最後の望み、ヒトラー」であった。
国民の思いに寄り添って、そのニーズを満たすことを短絡的に追求することが、大きな禍根につながることを私たちは知っているはずである。
だからこそ、統治のシステムにおいては、権力の分立がさまざまな形で図られ、また、国民全体の代表者たる「選良」による長期的な視点に立った熟議が求められる。
しかるに、現下の日本政治の情景は、いかがであろうか。
ロシアのウクライナ侵攻や、北朝鮮の度重なるミサイル発射、そして中国の軍事大国化と覇権的振る舞いを見て、わが国の防衛体制を強化すべきだと多くの国民が思ったことを受けて、防衛費のGDP比2パーセントへの増額方針が決定された。
他方で、そのための安定的な財源確保のための増税については、国民の過半が反対であることを背景に、総理の指示を受けて方針だけは決まった形にしたものの、これからさらに議論していくという「大人の解決」風の先送りとなった。
政権もまた、「支持率に一喜一憂しない」と言いながら、現実には「国民に痛みを強いることになるが必要なこと」への踏み込みには慎重にならざるを得ないようだ。
こうした傾向が強まってきたことの証左が、わが国の財政危機の深刻化だ。
国に対してあれもしてほしい、これもしてほしい、という人々のニーズに応える一方で、負担はしたくないという思いにまで寄り添ってきた「民主主義」の結果が、マーケットで消化しきれないほどの国債依存だ。中央銀行たる日本銀行が、国債の過半を保有する状況は危機的な奇態である。
このように、過度に民意に迎合的だと思われる状態にあっても、さらに新たな形で「民主主義」は民意を反映させるべきだという主張がある。
成田悠輔は、「民意データを無意識に提供するマスの民意による意思決定(民主主義)、無意識民主主義アルゴリズムを設計する少数の専門家による意思決定(科学専制・貴族専制)、そして情報・データによる意思決定(客観的最適化)の融合」を「無意識民主主義」として提言している。そして「選挙はアルゴリズムになり、政治家はネコになる」という(SB新書『22世紀の民主主義』)。
政治の現状に対する不満と不安から、かかる斬新な提案も出てくるのであろう。
しかし、データから無意識の人々の「民意」を探り当て、科学的に政策を決定していくのだ、という主張には賛成できない。
むしろ、そうした主張を現状に対する批判として受け止めて、まっとうな民主主義を運営することを考えるべきだ。
まっとうな民主主義とは、国民のニーズを満たすことを考え、国民の望みに寄り添っていくことでは、ない。「民主主義」を掲げて「国民が、国民が、」と叫び続けることは、民主主義の失敗を招く。
いま、世界のあちらこちらで、国民のあからさまなニーズを満たすことを「民主主義」として訴えて権力を握る傾向が強まっているが、その隊列に日本が加わることは、民主主義の失敗と敗北につながるだろう。
そういう風潮があるからこそ、私たちは民主主義をまっとうに運営すべきだ。
そのために、ペリクレスのような政治家と、彼を支持し続けたアテネ市民のような成熟とを、私たちが持たねばならない。
(月刊『時評』2023年2月号掲載)