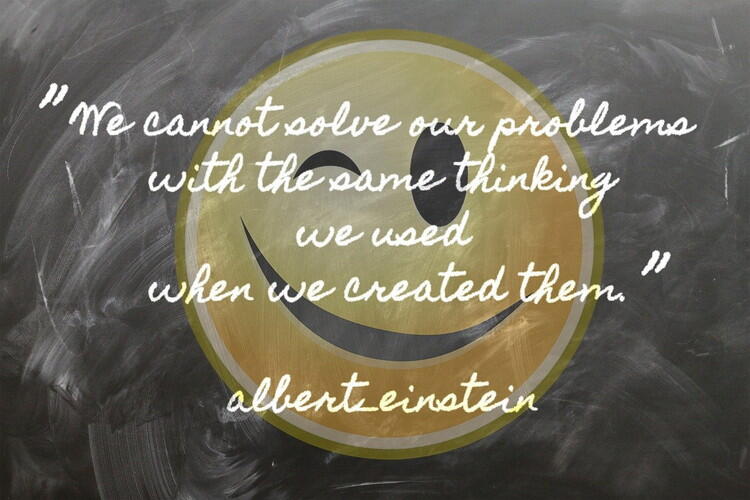
2025/03/03

今年4月末に開催された日本銀行の金融政策決定会合において、大規模な金融緩和政策を維持する方針が決定された。
日銀が公表した「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」では、2022年度の物価上昇率見通しを従来の1・1パーセントから1・9パーセントへと引き上げたものの、物価上昇は一時的であるとして、現行の金融緩和政策を堅持する方針だ。
金融政策決定会合後の記者会見で、黒田日銀総裁は「2パーセント物価目標の持続的、安定的な実現を目指す観点から、緩和を粘り強く続けて経済を支えていく」と述べた。
金利上昇を抑えるため、10年満期の国債を0・25パーセントで無制限に日銀が買い入れる指し値オペ(公開市場操作)を毎営業日実施するという。
こうした日銀の方針を受けて、外国為替市場では、実に20年ぶりとなる1ドル=130円台まで円は下落した。
記者会見において黒田総裁は、急速に進む円安について日本経済全体としてはプラスだという評価を変えたわけではないとしつつ「過度な変動はマイナスに作用することも考慮する必要がある」などと述べたが、これを嘲笑するかのように一段の円安がまさに記者会見中に一気に進んだ。
世界経済は、コロナ禍による停滞から「ウィズ・コロナ経済」へとかじを切って活性化に向かい、他方でロシアのウクライナ侵攻もあってエネルギー価格が高騰するという局面にあって、強烈なインフレ圧力にさらされている。
IMF(世界通貨基金)は、今年4月の時点で、2022年の世界の消費者物価(年平均)上昇率=インフレ率が前年比7・4パーセントになるとの見通しを公表した。これは、昨年10月時点の3・8パーセントという見通しから大幅に上方改訂されたものである。
このような情勢にあって、米国FRB(連邦準備制度理事会)も欧州ECB(欧州中央銀行)も、従来の金融緩和からの出口戦略を大急ぎで展開している。
5月初め、米国FRBの金融政策を協議する連邦公開市場委員会では、米国のインフレ率が歴史的な高さを記録する中、2000年5月以来となる0・5%の大幅な利上げに踏み切るとともに、量的緩和策で膨張した保有資産の縮小も決定し、物価安定の回復に向け強い意志を示した。
欧州ECBは、4月14日の理事会で、量的緩和政策の縮小を続けると決めた。債券の新規買い入れをめぐり、声明文で「7~9月期に終える見通しが強まった」と明記している。
他方、一人日本だけが異次元の金融緩和を継続することで円安がさらに進行し、輸入価格の高騰につながり、さらなる国内でのインフレ圧力が高まるという悪循環に陥りつつある。
円の実質的な通貨価値は、金融緩和が開始された2013年頃から下落しており、現時点ではおよそ50年前と同じレベルにまで低下している。この間の輸入物価の円ベースでの上昇は、企業努力で吸収されてきたが、ここに至って限界に達し、一気に消費者物価への転嫁が進みつつある。
すでに企業物価指数は1年以上にわたって上昇し、3月速報値では、2015年の平均を100とした水準で112となり、1982年12月以来、39年3カ月ぶりの高さとなった。こうした動きを受けて、消費者物価指数も徐々に上昇している。
日銀による金融緩和政策は、インフレ圧力によって脆弱性を露呈していると言っていい。
足元の景気に配慮するあまり、経済の基礎となる通貨価値を不安定化させては本末転倒だ。日銀は、早急に金融緩和政策の出口を明示して政策転換し、インフレ・ファイターとしての本来的な責務を果たすべきである。
今さら言うまでもなく、中央銀行の本来的な責務は、通貨価値の安定を図る金融政策を司る「通貨の番人」であることだ。
日本銀行法第2条にも「日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする」と規定されている。
日銀自身、そのホームページで「各国の歴史を見ても、中央銀行の金融政策にはインフレ的な経済運営を求める圧力がかかりやすいことが示されています。物価の安定が確保されなければ、経済全体が機能不全に陥ることにも繋がりかねません。こうした事態を避けるためには、金融政策運営を、政府から独立した中央銀行という組織の中立的・専門的な判断に任せることが適当であるとの考えが、グローバルにみても支配的になってきています。新日銀法において、独立性確保が図られているのは、こうした考えによるものです」と述べている。
こうした認識に立って、世界経済およびわが国経済の情勢を虚心坦懐に見つめれば、金融政策を転換すべき時に至っていることは明らかだろう。
かつて、円高不況をおそれるあまりに大胆な金融緩和を実施してバブル経済を生み出し、強烈なインフレとなってから急激なバブル潰しに走った結果、長きにわたる日本経済の停滞を招いた私たちの「黒歴史」を忘れてはならない。
(月刊『時評』2022年6月号掲載)