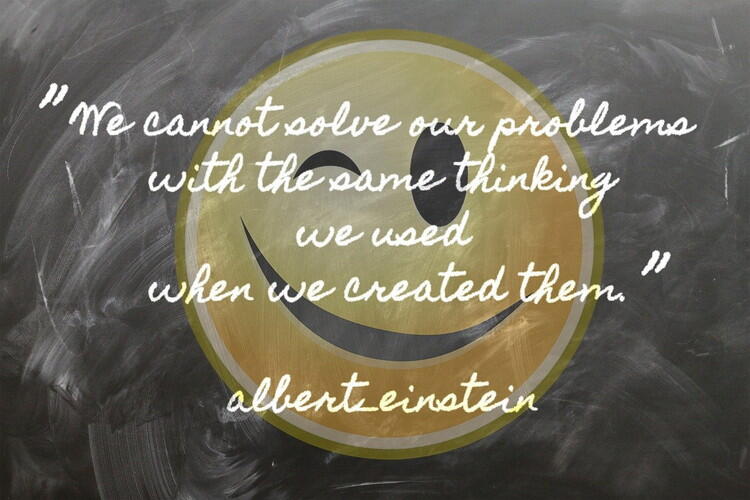
2025/03/03
新年度に入る。
中央官庁の「年中行事」で言えば、来年度の予算獲得や租税特別措置(政策減税)などのプロセスがスタートし、各担当が夏の概算要求等に向けて、本格的に頭をひねり始める頃だ。
予算で100兆円超(2022年度の予算は、過去最大の107兆5964億円)、法人税関係の租税特別措置適用額で4兆円超(2020年度)というスケールの話であるから、国家・国民のために、まずは、優秀な官僚の皆さまに知恵を絞ってもらわねばならない。
状況を冷徹に観察し、問題点をあぶり出し、必要な法律案を考え、予算措置や減税などの政策ツールを検討し、査定官庁を納得させ、与党プロセスで政治の了解を得て、最終的には国会の議決を経て政策を実現していく。毎年繰り返される政策プロセスだ。
こうした政策プロセスが毎年繰り返される中で、政策が洗練されていくという良い面もあるが、実際には「何かしらの手を打ちました」という言い訳を用意するための「アリバイ政策」ではないかと思われるパターンが繰り返されていることもある。
本来、政策の有効性については、エビデンスを持って示すことが求められるはずだが、「作文」で切り抜けてきたようなケースも、残念ながら散見される。
例えば、創業支援策として、一定の条件の下、会社を設立した際に必要となる登録免許税を半額にする政策が平成26年度から続けられている。
会社設立登記に係る登録免許税は、株式会社で15万円、合同会社等で6万円だ(それぞれ創業時の資本金が低いことを想定した最低額)。つまり、この租税特別措置は、7万5千円ないしは3万円の話である。金額的なインパクトに疑問はないか。
しかも、登録免許税は、そもそも創立費の一部として、新たに創立された会社の繰延資産に計上して、黒字となった時点での任意償却ができる。将来的に黒字が見込めない企業の創業を支援したいのだろうか。
こうして見れば、登録免許税の軽減は、「それなら創業しよう」と思わせるインセンティブになるとは考えにくく、政策的プライオリティは認めがたくはないか。
他方、このような有効性に疑問がある租税特別措置のためにかかる行政コストも考えねばならない。業務に精励する皆さんには敬意を払いたいが、要望側、査定側、そして執行側で、一体どれだけの業務量を負担し、おそらくは残業をしていることか。
確かに、わずかながらでも初期コストが低い方が創業は容易になるという「説明」は可能であろうが、実際上のインパクトはほとんどない。むしろ、数万円の減税のために求められる事務手続きの時間と費用を惜しむくらいの起業家でなければ、ビジネス上成功しないのではないか。
実際、この制度の適用件数は1800件弱であるが(2020年度)、この間の起業件数は、10万件を超えている。このインパクトに乏しい数字からも、この政策の有効性に疑問を感じるべきだろう。
この例に限らず、首をひねりたくなるような政策は少なくない。もちろん、それぞれに何かしらの事情もあろうし、少なくとも、国の姿勢を示す意義はあるだろう。
しかし、有効性に疑問のある「アリバイ政策」を展開していく余裕は、もはや、この国にはないはずだ。
日本は30年間の長きにわたって経済的に立ちおくれ、国民の可処分所得は停滞し、国際的プレゼンスも低下してきた。
将来を見通しても、少子高齢化は進み、社会保障などさまざまな課題が山積している。
他方、毎年の予算の4割が借金で賄われる一方で歳出面では予算の2割超が借金返済に充てられるなど、政策経費の柔軟性は失われている。国の債務残高はGDPの2・5倍を超え、国際的に見て突出している。
このような厳しい状況にあって、「アリバイ政策」を展開することは、国家・国民に対して犯罪的ですらあろう。
優秀な政策担当者には、わが国の状況を正面から見据えて、広い視野から本当に意味のある政策を打ち出してもらいたい。
例えば、先の創業支援を例にとれば、開業率をあげること自体ではなく、廃業率もあげて資源の最適な配分を実現し、この国全体の生産性をあげることこそが政策目的となるべきだ。
すなわち、産業活動の新陳代謝によってマクロでの生産性向上を図ることが本来の政策目標であり、そのために必要な政策は競争的環境の整備だ。
しかし、実際には既存の企業を保護する政策が多々採用されており、しっかりとブレーキを踏んでおいて、アクセルをふかして音だけさせている感がある。
そんな「アリバイ政策」を続けて、本当に求められる「困難で痛みもある政策」を避けてきた結果が、この30年間の日本の停滞ではなかったのか。
いろいろと「政治」との関係もあろうが、政策立案のプロフェッショナルとして、官僚の皆さまには、痛みはあるが有効な本当に必要な政策を立案し、「政治」に説明し、了解を得ることも求められるはずだ。
新年度に入る今、国家・国民のために、あらためて、政策立案のプロフェッショナルとしてのプライドをもった仕事を官僚の皆さまに期待したい。
(月刊『時評』2022年4月号掲載)